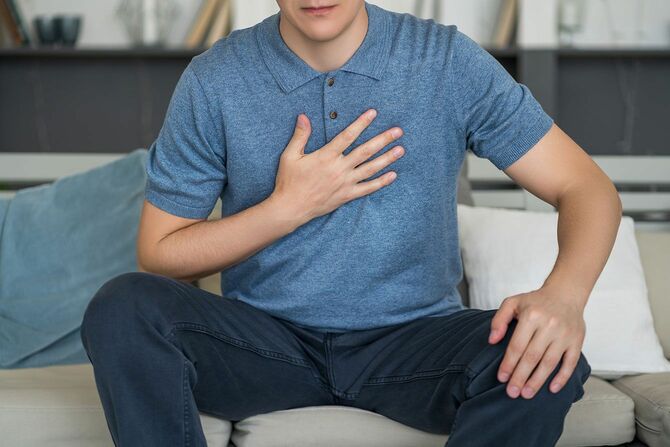息切れや動悸を「歳のせい」にしてはいけない
階段や坂道で息が荒くなったり、息が切れたりする──少し前までは呼吸を乱さずにできた行動で、息切れがするようになったら、「心臓不安」のサインである可能性が高い、とみてよいでしょう。
息切れや動悸などは、加齢にともなう生理的な心肺機能や筋力の低下でも起こります。これをただただ「歳のせい」と思って放置すると、心臓の病気を見逃してしまうことになります。老化による息切れは、運動不足によるものも少なくありません。
階段や坂道を上がるなど少しきつい動きをするとき、体は多くの筋肉を瞬時に動かすために、大量のエネルギーを消費します。呼吸で酸素を取り入れるのですが、激しい運動ほど酸素を多く必要とします。そのために、呼吸が荒くなります。日ごろから運動不足だと、血液を送り出す心筋の力が弱くなっているので、息切れを起こしやすくなるのです。
何もしていないときに、呼吸が速くなり息が切れることがあります。これは不安やストレスに起因していることも考えられます。こうした息切れが加齢などの生理的なものなのか、あるいは心臓不安を示すものなのかを見分けることが大切です。「息切れがひどくなってきた」「ちょっと歩いただけで息苦しくなってきた」など、息切れの症状の悪化がみられる場合、心不全などの心臓病の可能性が高くなります。
体が発している「心臓不安のSOS」
症状の悪化は、多くの場合、心臓や肺の病気が原因で、血液中の酸素が不足して引き起こされています。心臓は呼吸の乱れだけでなく、体の各部位の痛みや変調などで心臓不安のSOSを出しています。
●痛み
狭心症の場合、左側の胸部に締めつけられる痛みや圧迫感があります。階段や坂道を上がるときや、重いものを持ち運んだりするときに生じます。心筋梗塞でも前兆として胸痛や背部痛、歯痛が起こることがありますが、大半の人は自覚症状も前兆もなく突然、発作に襲われます。
●むくみ(浮腫)
血管やリンパ管(静脈につながる)を通して全身をめぐる水分がそこから漏れ出して、皮膚の下に溜まることで起こります。
下肢をめぐる血流は、ふくらはぎの筋肉のポンプ作用で押し上げられ、心臓に戻ってきます。デスクワークが多い人だと、ふくらはぎの筋肉を動かすことがあまりないので、血流は重力の影響を受けて下肢で滞ってしまいます。そのために、血管から漏れる水分も下肢に溜まってしまい、脚がむくみます。夕方になると脚がパンパンになるのは、水分が下半身にどんどん溜まってしまうからなのです。
むくみは、塩分や糖分の過剰摂取にともなう水分の摂りすぎが原因となって生じることがほとんどです。とくに、塩分の摂りすぎは、むくみに直結します。体には塩分濃度を一定に保つ働きがあり、塩分を摂りすぎると、それを薄めるために水分を溜め込んでしまうからです。