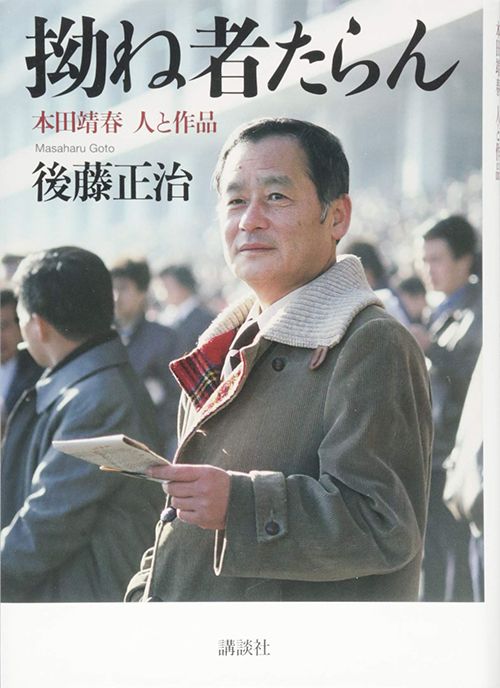引っかかるようなところが全くない自然な文章
「本田作品」の魅力について、後藤さんはこう話す。
「読んでいて非常に面白いのは『警察(サツ)回り』ですね。昭和30年代、本田さんと同じく警察回りだった若い記者たちの逸話と、彼らがたまり場としていたバーのマダムの半生を描いたものです。戦後の渋谷を牛耳っていた安藤組の幹部・花形敬を描いた評伝『疵(きず)』なども、たいへんに魅力的な作品でしょう。しかし、本田さんの作品の中で圧倒的に優れているのは、やはり『不当逮捕』と『誘拐』です」
「今回、本田さんのことを書くにあたって、あらためて作品を読み直していて気付いたことがありました。それは彼が本当に自然な文章を書くこと。決して美文家ではないのですが、読んでいて引っかかるようなところが全くない。その極めて巧妙な表現力にあらためて感銘を受けたんです」
例えば、『不当逮捕』の中では、スター記者の立松が次のように描かれる。
彼がそうしたときにのぞかせる心の翳りは、生まれつきからくるものなのか、あるいは、育った環境に由来するのか、それとも、戦争体験が落とした影であるのか、私にはいずれともいえない。ただ、職場で称賛や驚嘆や憧憬を以て語られる立松和博は、多分に本人自身によって演出されたものであり、彼のたぐいまれな人づき合いのよさは、むしろ、深い人間不信から出ているのではないかと思うときがあった。(『不当逮捕』より)
無頼の極みのような男を、文学的な筆致で描く
「本田さんの最も画期的な表現は、やはりこうした立松を描いている部分だと思います。無頼の極みのような男である立松の人物描写を、このように文学的な筆致で描いた。淡々としていながら、あるいは、淡々としているからこそ伝わる文章、と言うのでしょうか。書かれた側もこういうふうに書かれたら、もう降参するしかない。私はノンフィクションの書き手として、物事を『伝える』ための文章とは本来、このように静かであってこそ効果的なのだ、ということを彼の作品から学んだと感じています」
「もうひとつの魅力は対象を『複眼』で見つめる姿勢でしょう。悪い奴を糾弾したり、強い者をたたえるだけであったりするだけの一面的な作品は、時間の経過とともに消えていくものです。トータルに人を描きたいと希求する作品が、時代を経ても生き残っていくことを彼の作品は教えてくれる」
「『誘拐』がまさしくそうなのですが、本田さんの作品は被害者、加害者、警察などそれぞれの視点から、一つの事件のさまざまな面に光を当てていくところに特徴があります。常にさまざまな面から物事を見る。一度止まって見つめ直してみる。考え直してみる――そうした作業を必死にされていた人だと思いますね」