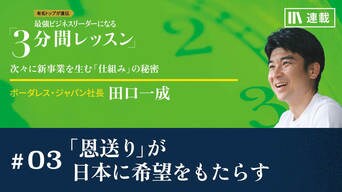判断力、包容力、洞察力…年を取ってから伸びる能力
俳優の世界でも、若手が次々と登場するなかで、ベテランでも魅力を保ち続けている方はめずらしくありません。
若いほうが絶対に美しい、魅力的とはいえません。能の世阿弥がいっているように、若いときは「時分の花」がありますが、それがなくなった中高齢期に「真の花」を咲かせる方は多いのです。
つまり、日本は美しさについては「若さ」に価値を置いてきましたが、そろそろ見直すべき時期になっているのだと思います。
人間の能力が試験の成績や偏差値だけでは測れないように、人間の総合的な価値も、体力や見た目だけでは測れないものなのです。
生物としての若さだけでなく、これまでの経験や磨いてきた技を評価される分野もあります。それには評価する「目利き」が必要とされるのです。目利きになるには経験が大事です。
知的能力でも集中力や記憶力のように、若い時期のほうが優れている分野もありますが、判断力、包容力、洞察力、類推力、共感力のように、年を取ってから伸びる能力もあります。
創造性も若いころのほうが豊かだといわれますが、ゼロから生み出す創造だけでなく、スマートフォンのように、すでに存在していた電話と音楽、動画などを結びつけて新たなものを創造するケースもあります。
そちらの創造力のほうが、現実には社会に広く受け入れられています。
年を取ると「そうだったのか」と知ることがたくさんある
そうはいっても、老化とともに細胞が新陳代謝の力を失うことは事実です。原因は活性酸素など有害なものの蓄積とか、染色体の末端にあって細胞分裂をつかさどる「テロメア」の枯渇など、いろいろ研究されていますが、まだ特定されていません。
コロナパンデミックの時期も「高齢者は免疫力が衰えているから重症化しやすい」と警戒が呼びかけられました。
でもその一方で、年を取るからこそ身につく力もあるのです。1997年、作家で芸術家の赤瀬川原平さんが「老人力」を提唱して、「もの忘れも老人力がついている証拠」といって話題になりました。
スポーツや芸術の面だけでなく、社会や職業生活でもいろいろな能力があって、それぞれピークを迎える時期は異なります。
新しいスキルや情報については若い人のほうがよく知っているかもしれませんが、人間関係の調整力、表現力、人間性への洞察など、年齢を重ねたことによって得られるものもたくさんあるのです。
私も昔は、どうしてあの人が私に意地悪だったのかわからなくて、きょとんとしていたことがありますが、当時の相手の立場や苦しかった状況がいまになってわかるようになりました。
このように、年齢を重ねると、若いときには知らなかったことを「そうだったのか」と知ることが、たくさんあります。