毎年発表される「各国ジェンダーギャップ」。2015年、日本は145カ国中101位という結果だった(前年は104位)。さらには「女性登用30%目標を7%に軌道修正」という話も出てきている。政府が女性登用クオータ(割当)を下げたのは諦めなのか、それとも現実を見据えてのものなのか……?
「急激な少子高齢化で、日本の労働生産人口が確実に減少してゆく。それを前にしたとき、公務に従事する者としては2つの方法論を考えるわけなのです。『人口を増やす』か、『1人当たりの生産性を高める』か。その生産性向上のほうに、私たちは取り組んでいます。どうしたら能力の高い一流の人材が集い、さまざまな条件にとらわれず平等に切磋琢磨できる環境を作れるのか」。
とある行政機関でのインタビュー。若く聡明な女性課長がくっきりとした口調で説明を始めた瞬間、それまでの単調な場の流れが変わったのを感じて、インタビュアーの私はノートパソコンから目を上げた。その日の話題はある施策の話だったのだが、担当者としての思いを語っていただく段になって、やがてそれはダイバーシティの話へとつながっていった。「能力の高い一流の人材が、条件にとらわれず平等に切磋琢磨できる環境」という言葉を口にしたとき、冷静な彼女の瞳の中にキラリとした微かな光を見たような気がしたのは、彼女自身のキャリアへの思いが映っているように思ったからだ。
帰途、微かな光の残像は私の頭から離れなかった。「10年後、ああいう女性がどんどん成長して偉くなって、政治や行政の要職にたくさん当たり前にいてくれたらいいな。日本の風景が変わるだろうな」。そういえばこれまでにも、政治界やビジネス界の女性で、インタビュー後にもその話が頭から離れないような印象的な人材がたくさんいた。「女がほれる女」とでも言おうか。だが誰1人として、そこから連想しがちな、どこかのドラマに出てきそうな男性的な人でもアグレッシブな人でもなかった。見るからに強烈な個性の持ち主など1人もいなかった。みんなごく普通の「女の人」で、ただ話し出した途端、その場の空気をグイッと変える引力を持っているのだった。

男女平等指数ランキング、日本は101位
世界経済フォーラムが毎年発表する各国ジェンダーギャップ指数(The Global Gender Gap Report 2015)で、今年は日本が145カ国中101位になり、昨年の104位から3ポイント上げたと報道された。それを見て微苦笑した人は多かったに違いない。「あれだけ『女性活躍推進』の大旗を振っていたのに、世界的にはそんな評価かぁ」と。
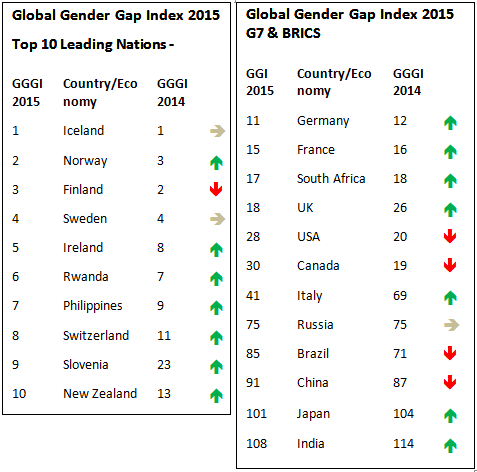
「女性が活躍する社会づくりを政府が掲げているんだって」という認識だけは広がっているが、現実レベルでは遅々として進んでいない。いよいよ先日は「女性登用30%目標を政府が断念」との報道もあり、「社会のあらゆる分野で2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%にするなんて、目標値実現は到底無理。現実的な数値(7%)へ軌道修正」との話に、確かに現実の女性管理職の数を見るとそれが身の丈なんでしょうね、と思う。
「指導的地位」とは、役所や企業では「課長級以上」と定義されるのだそうだ。まさに冒頭の彼女は行政組織の「指導的地位」にいるわけで、その女性割合(国家公務員)は現在3.5%程度なのだそうだから、私は希少な女性課長にお目にかかれたということらしい。
「30%」と数字を割り当てることの意義
先日このPRESIDENT WOMAN Onlineで公開された記事「『ワーク・シフト』リンダ・グラットン教授に聞く、“働き方の未来”」(http://woman.president.jp/articles/-/727)では、ベストセラーとなった『ワーク・シフト』(2012年)の著者で、経営組織論の世界的権威として知られる、ロンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットン教授が、女性管理職比率の目標数値を一律30%と定めるような、いわゆる女性登用クォータ制(数字割り当て)の意義について語っている。
「30%という数字は、ひとつの分水嶺になるのをご存知ですか。グループの中で、あるカテゴリーの人が30%を超えると、ステレオタイプに振る舞わなくなります。つまりその割合が30%以下の場合、女性たちは、例えば、とても攻撃的であったり、逆に従順であったりと、ステレオタイプに行動しがちで、リーダーシップを発揮することはありません。しかし、30%を超えると人々は性別について語らなくなり、自由に振る舞うようになります」
30%が分岐嶺という話に、私はハッとした。もともと私はリンダ・グラットン氏の『ワーク・シフト』の大ファンで、特にそれが決して大上段から抽象的・一般的な未来の職業論を語るのでなく、彼女の2人の息子たちの未来を、母親の視点から描き、思いをはせるという切り口で語られ始めるところがたまらなく好きだ。自分の教育講演で大いに引用させてもらい、本を紹介したこともある。その彼女が語る「30%が分岐嶺となって、女性は少数派意識を持たなくなる」との話は、実感を持って浸み込んでいくようだった。マイノリティが「少数派意識」、つまり数としての劣位意識を持たなくなったとき、マイノリティは自分たちへ向けられる視線を意識しなくなり、自意識からも自由になる。「こうあるべき」と自らに課す姿、あるいはステレオタイプに自分の体をねじ込んで適応しようと努力しなくてよくなる。人の視線から自由になれば、自分たちの国籍や宗教やジェンダーについて語らなくなる、語らなくてよくなるのだ。
そしてリンダ・グラットン氏はこうも語る。「日本の組織構造は、まるでクルミの殻のようです。堅く、美しく閉じられていて、開けることはほぼ不可能です」。そして、じつは日本は何をすべきかを「もう、皆知っている」。「若い女性たちの声を聞き、女性役員登用の目標値を設けたり、女性たちがネットワークを形成するのを奨励したり……もう既にスタートし始めている、一連の取り組みを加速させることです。」「とにかく、やるしかないのです。始めるしかないのです」。

政府が今回、女性登用クォータを30%から7%へと下げたのは、「諦めたから」ではないと信じたい。現状を十分に認識した上で現実的な路線に軌道修正したのは、着実に前へ進むためなのだと。折しも、新スローガン「一億総活躍社会実現」の登場によって示された社会像に、現代の働く女性たちからは「『産め、働け、育てろ、介護しろ』と、全てを女に押し付け、同時実現せよと命令しているとようにしか聞こえない」との猛反発も起きている。(参考記事:「『仕事・育児を両立』した女性に限って、なぜ、50歳で介護離職するのか?」http://president.jp/articles/-/16821)日本では女性の労働参加率が低かったがゆえに、どこか「女性の労働力」は神話的なレベルで全ての社会問題を解決する魔法の呪文だとでも思われているのではないか。「女性のパワー」は無尽蔵でも、万能でもない。女だって男と同じ、人間である。
冒頭の女性課長が口にした「労働者の生産性向上」は、女性だけに向けられた言葉ではなく、男性も女性も老いも若きも、全ての生産人口に共通の課題なのだということを改めて認識したい。
フリーライター/コラムニスト。1973年京都生まれ、神奈川育ち。乙女座B型。執筆歴15年。分野は教育・子育て、グローバル政治経済、デザインその他の雑食性。 Webメディア、新聞雑誌、テレビ・ラジオなどにて執筆・出演多数、政府広報誌や行政白書にも参加する。好物は美味いものと美しいもの、刺さる言葉の数々。悩みは加齢に伴うオッサン化問題。
