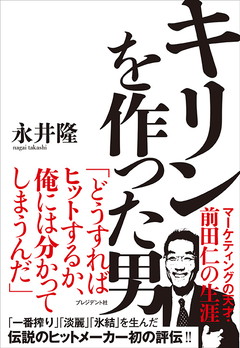抵抗勢力から現場の人間を守る
もっとも、社内には抵抗勢力があった。
「キリンはビールの会社だ。缶チューハイを、わざわざキリンが販売する必要はない。子会社にやらせておくべきだ」
といった意見が根強かったのだ。
伝統企業が新しい事業を始めるときに、抵抗勢力が生まれるのはやむを得ない。「前田さんは僕から見ればオタク」と、前田を師と仰ぐ湖池屋社長の佐藤章(キリンビバレッジ元社長)は指摘する。だが、商品開発ではオタクでも、社内のパワーゲームにおいて前田は抵抗勢力に対して、たじろぐことはなかった。持ち前の突破力で相手を封じ込んでしまう。
「前田さんは自分が正しいと判断したことを、断固やり遂げるリーダーでした。何より、反対派から僕ら現場の人間を守ってくれました」。そう鬼頭は述懐する。
ある意味、強引な手法でも、前田は新商品の企画を通して、ヒットさせていた
鬼頭が作ったサンプルを前田がプレゼンして、本社の経営会議でウオッカベースの缶チューハイは認められる。
鬼頭は前田に、メインとなるレモンとグレープスルーツだけではなく、梅や洋梨のサンプルもプレゼン用に送っていた。これは、「いずれフレーバーを広げていきます」という、鬼頭から前田へのメッセージでもあった。
神秘性を生んだ商品名の変更
前田のプレゼン成功により、私的な開発プロジェクトは正式なプロジェクトに昇格した。本社にキリン・シーグラムの和田をリーダーとする開発チームが組織される。
メンバーは清涼飲料メーカーのキリンビバレッジの社員、キリンの若手2人が加わる混成チームだった。従来のキリンビール社員だけの純血チームではなかったのは特徴だった。
「氷結」では果汁に一般的な濃縮還元ではなく、ストレート果汁を敢えて採用する。これはビバレッジ社員の提案だった。ストレート果汁は、扱いが難しくコストはかさむ反面、水で希釈しないため風味に優れ、商品コンセプトだった「微妙な甘さ」を実現できた。
なお、現在の氷結は、濃縮還元を使っている。「濃縮還元の技術が進歩して、ストレート果汁と味の遜色がないため」(キリン)と説明する。
鬼頭は御殿場蒸留所内の研究所で、チーフブレンダーらと氷結の技術チームを組み、開発を技術面から支える。
「氷結」は缶も特徴的だった。ベースカラーはブルーメタリック。しかも開缶するとダイヤ形状の凹凸ができる特殊なアルミ缶を採用する。これは東洋製罐が開発したが、ライバル社の製品にはない新しい試みだった。商品名は「氷結果汁」に決まる。
こうして01年7月に発売された氷結果汁は、たちまち好評を博す。
ところがだ、消費者団体から「商品名が紛らわしく、ジュースと混同する」とクレームが入り、キリンは翌02年4月から「氷結」に変更した。
「氷結となったことで、ネーミングに神秘性が生まれた。これもヒットの要因だ」(ライバル社)という指摘もあった。
天然果汁の調達が容易になった02年には売り上げを伸ばし、「スーパーチューハイ」を超えて缶チューハイNO.1ブランドとなる。最後発からの大ヒットだった。
ウオッカベースの缶チューハイが、女性をはじめ新規ユーザーを取り込んでいき、市場は膨らんでいった。ビール系飲料の市場が縮小していくのとは裏腹に、缶チューハイ市場そのものを拡大させていく。
前田は部門の責任者として、多様性のあるチームを作り上げ、商品をヒットさせた。