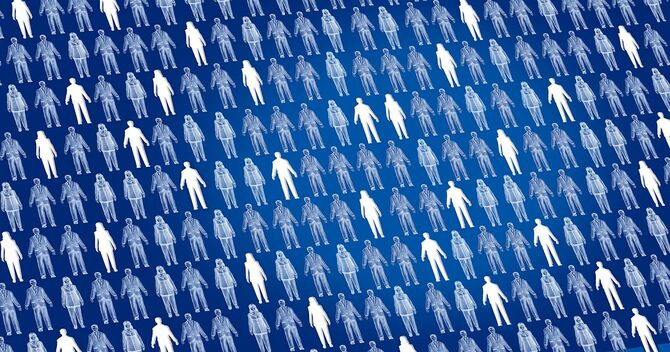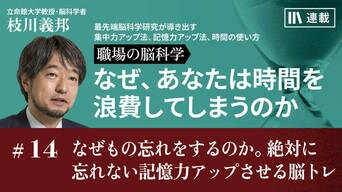解雇紛争の手段で異なる補償金額
厚生労働省労働条件部会(12月6日)に、労働政策研究・研修機構が作成した解雇の金銭解決の現状についての綿密な資料が提出された。これによれば、労働審判・あっせんでは、500万円以上の金銭補償額が全体の12%に過ぎないのに対して、民事裁判での解雇無効判決後の和解金では32%を占めており、3倍近い差が生じている。
とくに雇用者1万人以上の大企業については、労働審判などでは平均した補償金が4.2月分の賃金に対して、民事裁判では20.4月分と、より大きな差がある。これは、紛争解決までの期間が、前者は1年以内が56%に対して後者は20%に過ぎず、逆に2年以上が2%に対して29%と長期化していることに。
これらの結果から、仮に、欧州主要国で普及している解雇の金銭補償ルールが日本でも定められれば、現在は短期間で決着のつく労働委員会のあっせんや労働審判に依存している、主として中小企業の労働者も、長期になりがちな民事裁判のプロセスを踏まずに、相応の金銭補償を受け取れる可能性が大きい。
他方で、この欧州方式のルールが採用されれば、現在、わずかの補償金で労働者を容易に解雇できる中小企業の経営者にとって、補償金の下限を定められることは大きな負担増となる。逆に言えば、組合の支援などで長期間の裁判に耐え、多額の和解金を獲得できる可能性のある一部の労働者側にとっては、その金額に上限を課せられることに不満が生じる。
日本の企業別に分断された労働市場では、欧米のような労使間の階級対立よりも、企業間や労働者間に利害対立が存在することが、必要な労働市場の改革を阻んでいる大きな障壁となっている。
こうしたなかで、現在、厚労省の審議会で提案されている金銭解決方式は、本来の欧州方式とは異なり、金銭補償の申立は、企業には認められず、労働者側からだけしかできない非対称的なものである。これでは、せっかく解雇の金銭解決ルールが設定されたとしても、長期の裁判が可能な労働者は、あえてそれを使わずに、従来通りの職場復帰の請求を行い、青天井の和解金を請求することが有利となる現状に大きな変化はない。解雇の金銭解決は、労使双方にとって同一の原則に基づく、グローバルスタンダードの方式でなければ労働者間の公平性は達成できない。