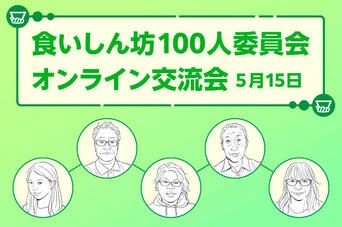働く時間を7時間程度に短縮した
次に着手した実験は「働き方」だった。パンの種類を絞って具材を入れないことにしたことで、手間をすでにだいぶカットできていた。さらに働く時間を短縮するため、グラッガーのように冷蔵庫を活用することにした。
なぜ冷蔵庫を使うと、働く時間を短くできるのか。冷蔵庫を使わなければ、パン生地を仕込んだ後に発酵が進むため、遅くとも4、5時間後には焼かなくてはならない。日本の多くの「こだわり」パン屋でやっているようにその日のうちに焼こうとすれば、仕込み始めから窯入れ、焼き上がりまでに7時間ほどかかる。
つまり午前8時にパンを焼き上げるためには、午前1時に作業を始めなくてはならないのだ。1回の窯入れで焼けるパンの量には限界があるため、2、3回窯入れしようとすると……寝られなくなる。
しかし冷蔵庫を使えば、途中で発酵をある程度止めておける。さらに冷蔵庫から出してすぐに焼けるため、何時に起きても、窯の着火から2時間ぐらいでパンを焼くことができるのだ。
「グラッガーでは、大して味が変わらない作業にはこうやって手抜きをしていたんです。パンは単純なもの。だから素材さえしっかりしていればおいしくなる」
こうして、働く時間を朝4時から11時までの7時間程度に短縮した。以前の半分だ。スタッフ10人程度で回していた店の規模も、ぐっと小さくした。店は1店舗に減らし、店を開くのは木、金、土の週3日の午後だけ。スタッフも基本的には自分と芙美さんの2人だけにした。
「ネット販売」と「リレー販売」で売れ残りをなくす
最後に田村さんが取り組んだのが、「パンを捨てないようにする売り方」だった。パンの種類を少なくして具材も入れないようにしたことで、パンは日持ちするようになった。問題は、どうやって商売として成り立たせるか、だ。
「パンを捨てたくないから焼かないようにする、というのは違うと思ったんです。そうすると商売にならないし、心をこめて作ったパンだから可能な範囲で多くの人に食べてもらいたい。作ったパンは捨てないし、仕事は楽で、わりと儲かる。そこを目指さないと、そもそもこんなパン屋稼業、やる人がいなくなっちゃうと思ったんです」
そこで考えたのが、予約を取って定期購入してもらうネット販売だ。店を閉める平日の2日間に定期購入分のパンを焼き、予約してくれた客へパンを発送する。
「パンって、暑い夏は売れなかったりして季節で売れ行きが変わるし、天気の影響も大きい。でも定期購入ならぶれが出ないので、収入の土台になります。僕が焼くカンパーニュみたいなパン、みんなが好きなわけじゃないです。100人のうち1人ぐらいでしょうか。だから販売する先を全国に広げた方がいいんです。形崩れしなくて日持ちするこんな堅いパンだから、発送もしやすいんですよ」
定期購入を始めると、ドリアンのパンは少しずつ評判を呼び、その送り先は北海道から沖縄まで約160に広がった。
店で販売するパンも売れ残らないように、「リレー販売方式」を編み出した。焼きたてはまず、厨房の横のテーブルに置く。パンの隣には、代金を入れる箱。無人のセルフ販売だ。そして広島市中心部にある店でパンが売れ残った時には、地元野菜の移動販売業者やハム店に託す。
「いろんなところで、ちょっとずつちょっとずつ売っていって、なんとか売り切れる感じですね」と田村さんは笑う。
朝日新聞 社会部記者
1979年、広島市生まれ。沖縄ルーツの転勤族で、これまで暮らした都市は10以上。2002年、朝日新聞社入社。長崎総局、西部報道センターなどを経て2010年から東京本社社会部。著書に『ルポ コールセンター』、取材班の出版物に『孤族の国』(ともに朝日新聞出版)がある。
藤田さつき(ふじた・さつき)
朝日新聞 オピニオン編集部記者
1976年、東京都生まれ。2000年、朝日新聞社入社。奈良総局、大阪社会部、東京本社文化くらし報道部などを経て、2018年からオピニオン編集部。近年は、消費社会や家族のあり方などを取材。取材班の出版物に『平成家族』(朝日新聞出版)など。