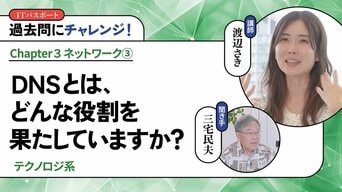戦争に積極的に参加してこなかった歴史がある
第5代のモンロー大統領はこの方針を受け継いで、有名な「モンロー教書」を発表しました。この教書では、ヨーロッパ諸国はアメリカに対して干渉するべきではないと同時に、アメリカはヨーロッパ諸国に干渉するべきではない、と表明しました。
第一次世界大戦でも、アメリカは前半まで不参加を貫き、後半になってやっと参戦しました。そして戦後、ウィルソン大統領は国際連盟創設を提案し、アメリカがその後も大陸情勢に関わり続けようとしましたが、議会がこれに反対した結果、非干渉主義に戻ることとなりました。同様に、第二次世界大戦の際、ヨーロッパとアジアで戦争が激化しても「不参加を保つべき」との声が根強く残り、真珠湾攻撃を受けてようやく参戦に転じました。
なぜアメリカは大陸に関わらないといけないのか?
戦後も「アメリカは孤立状態に戻るべき」との意見が少なからずありましたが、アメリカは国際連合やNATOを通じて大陸政治に積極的に関わる方針に転換して、今日に至ります。それでも2016年と2024年にドナルド・トランプ氏が、「自国第一主義」を掲げ、世界から米軍を引き上げようと訴えて大統領に当選したことからわかる通り、非干渉主義は今日でもアメリカが取ってもおかしくない外交姿勢なのです。
では、非干渉主義は今日でも妥当なのでしょうか? トランプ氏の訴えるように、海外から手を引いて、本土防衛だけに集中した方がアメリカにとって良いのでしょうか? 実は、地政学的にいえば非干渉主義は理に適っていません。古典地政学者のマハン、マッキンダー、スパイクマンは、全員揃って非干渉主義を否定しました。
そして、海洋国家は大陸に積極的に関わることを議論の大前提としました。この3人は、海洋国家のイギリスとアメリカの出身です。その上で、「母国の安全を保つためには、非干渉主義を否定し、ユーラシア大陸情勢への関与が必要だ」と訴えたのです。
では、一体なぜ海洋国家は大陸に関与しなければならないのでしょうか? これが、いよいよ地政学で最も重要な考え方である、「海洋勢力と大陸勢力の戦い」に繋がります。