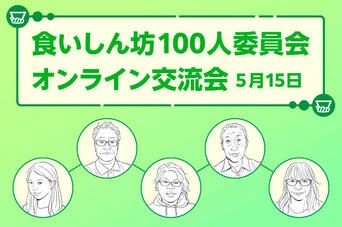音声教材の宣伝で、「最初は一言もわからなくても、シャワーのように音声を浴びていれば、ある日突然わかるようになる」といった謳い文句を目にすることがあります。
しかし、まったく理解できないものを延々と聞き流すよりも、5分間、集中して1フレーズでも2フレーズでも覚えたほうが、はるかに実力につながります。ただ受動的に聞き流すだけでは、あまり効果はないでしょう。
早く上達するには、学習者の能動性が欠かせません。私の経験上、「ある程度は理解できるが、わからないところもある。そこを確認しながらアクティブに聴く」というのが、最も学習効果の上がりやすい学び方なのです。
このように「自分が簡単に理解できるラインよりも少し高く、努力すれば理解できるくらいのレベル」を、言語学者のスティーヴン・クラッシェンは「Comprehensive input(理解可能なインプット)」と呼びました。
それくらいのインプットができる教材を選ぶと、着実な上達を実感しながらモチベーションを維持し、学び続けることができます。
物語や会話文が載っている教材、言語学習系のYouTubeチャンネルやPodcastチャンネルは無数にありますが、「初見(初聴)で80~90%くらい理解できるもの」であれば、今の自分に適していると言えます。
10~20%分だけ頑張ればいいというのが、意外とハードルが低くて驚かれたでしょうか。しかし、この10~20%の差分を埋める道のりが、着実な上達の道のりとなるのです。これに慣れてきたら少し難易度を上げて、60~70%理解できる教材を選んで挑戦してみると、スムーズに進められると思います。
「大筋はわかるけれども、ところどころわからない単語や文法がある」くらいならば、投げ出したくなることはないはずです。「よし、ちょっとだけ頑張って、全部理解できるようになってみるか」と思えるでしょう。
「苦手」を克服しようとしない
言語を学ぶ過程では、きっと誰もが苦手なことにぶつかるものだと思います。複数の言語を学んでいると、言語によって難しいポイントが違うと気付かされることもしょっちゅうです。
たとえばロシア語は文法が難解ですし、中国語とタイ語には「声調」と呼ばれる独特な発音体系があり、なかなか体得できません。
このように私も言語ごとに苦手とする部分はあるのですが、すぐに何が何でも克服しようと頑張ったことはありません。
文法や文字、発音が難しいと感じたら、とりあえず文法そのもの、文字そのもの、発音そのものには注力せずに、いったん脇に置く。そんなふうに苦手なところは何となくラフに捉えておいて、フレーズや単語にたくさん触れることを通じて、徐々に体得していけばいいか、くらいの気楽な感じです。
おそらくこれが、今までさまざまな言語を学び続けてこられた理由のひとつなのでしょう。