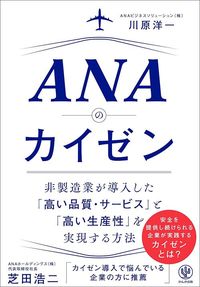※本稿は、川原洋一『ANAのカイゼン』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
「まずは現状分析」あいまいな問題を数値で具体化する
ANAグループオペレーション部門は、2016年からカイゼンを導入しており、
・部署内の年間業務時間を「1万4600時間削減」
・CAの年間業務時間を「2万1000時間削減」
・成田空港の航空機のエンジン保存にかかるコストを半年間で「500万円削減」
・お客様からのクレームに対する一次対応の所要時間を「61%削減」
などたくさんの成果を上げています。
非製造業であるANAでどのようにカイゼンを進めているのか、実際に行った事例をご紹介して具体的に解説しましょう。基本的に、カイゼンは「現状分析」→「真因追求」→「解決」→「定着」の順に進めていきます。チームを組んで進めるような大規模なカイゼン活動などは特に、この4つのステップで進めることがとても大切になってきます。
現状分析の段階では、問題となっている事柄の背景から実態調査、課題の特定までを行います。
まずは今目の前にある問題について、その実態を調査します。現状分析をする際に重要なのは、現状を数値やデータに落とし込むこと。そして、比較対象となる「標準」を設定することです。
単に「効率が悪い」「使いづらい」などの主観的な体感だけで課題を設定してしまうと、出てくる解決法も抽象的なものになってしまいます。また、客観的な数値を出したときに、その数値が異常な値なのか、それとも正常な値なのかは、「標準」がなければ比較できません。

コロナ禍後に増えたヒヤリハットの件数を半分に
2020年からしばらくの間、コロナ禍によって航空業界は大打撃を受けました。これはCAの育成にも影響しました。フライトの減少に伴ってCAが機内で経験を積む機会も減少したのです。
また、感染防止対策や衛生管理などそれまでにはなかった業務が増えたことによって、コロナ禍以前とはCAの業務手順にも変更が生じました。
やがてコロナ禍が落ちつき、人の移動が復活してからはフライトも増加しました。ところが機内におけるカートや手荷物の取り扱いで、経験不足による軽微なヒヤリハットが生じ始めたのです。
「一つの重大事故や災害が起こる背後には29件の軽微な事故や災害があり、その背景には300件の無傷害の事故や災害(ヒヤリハット)がある」という有名な法則があります。
この法則を提唱したのは、アメリカの損害保険会社に所属していたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒという人物です。
ヒヤリハット自体は事故ではありませんが、重大な事故の前兆であると私たちは考えています。ですから、ヒヤリハットの段階で手を打つため、CAが所属する客室センターは、この問題をカイゼンを使って解決しようと考えました。
客室センターは「現状分析」に取り組み、「今、どのような状況なのか」を可視化することにより、問題を浮き彫りにしていきました。今回のケースでは、あるべき姿としてヒヤリハットの件数を前年同時期の半分の値としました。
「課題の特定」ヒヤリハットを5Wで分析
続いて、カイゼン活動で解決すべき課題の特定に移ります。ここでは、さまざまな角度から「なぜその事象が起きているのか?」を追求していきます。これには、5Wが役に立ちます。「When:いつ」「Where:どこで」「Who:誰が」「What:何を」「Why:なぜ」という、あの5Wです。
ヒヤリハットの事例を5Wで分析してみます。まず「When:いつヒヤリハットが起きているのか」については、時間帯や曜日、旅客数に関係するかどうか、「Where:どこで起きているのか」については、路線や空港による違いはあるのか、空港のスポット(駐機場)による違いはあるのか、機種による違いはあるのか、という視点で分析しました。
そうすると、お客様にご提供する飲みものやカートに関連するヒヤリハット、相互確認の際の報告が漏れていることによるヒヤリハットなどが起きていることが見えてきました。これが「What:何が起きているのか」にあたります。
また「Who:誰によって起きているのか」については、若年層と中堅以上で分けました。その結果、路線や空港、スポットによる違いはないことが見えてきました。一方で、中堅よりも若年層のCAによるヒヤリハットが多発していることなどが分かってきました。
そして最後は「Why:なぜ」です。それはなぜなのかを考えます。ここまで見えてくると安心して手を緩めがちなのですが、まだまだ課題の特定は終わっていません。さらにカイゼンによって解決すべき課題を特定していきます。

「真因追求」本当の原因は何か
特定の方法にはさまざまな方法がありますが、客室センターでは「インパクト」「緊急度」「頻度」などの項目を挙げ、それぞれの項目について点数で評価するという方法をとりました。点数を合計すれば、最も優先して解決すべきものがわかる仕組みです。
その結果、最も優先して解決するべき課題は、若年層のCAによるカートの操作ミスであることが見えてきました。
ここまでで、現状分析がいかに重要なのかがおわかりいただけると思います。単に「ヒヤリハットが増えているから何か対策をしなければ」というあいまいな状態で解決策を考えても、意味がないのです。
現状分析によってカイゼンで解決する課題が決まったら、次は「真因追求」です。
「まだ課題を分析するのか」という声が聞こえてきそうですが、カイゼンにおいては、現状分析と真因追求がとても重要なのです。ここがしっかりとできれば、解決策は自ずと見えてきます。
真因とは、真の原因や本当の原因のこと。「その課題を引き起こすことになった根本の原因」と言い換えていいでしょう。
「なぜなぜ分析」を重ねる
エアコンのフィルターが詰まったら、フィルターを掃除しますね。フィルターを掃除すれば詰まりは取れますが、時間が経つとまたフィルターが詰まるという現象が再発します。単に表面的な原因を取り除いただけでは、根本的な解決には至らないのです。

フィルターが詰まりを起こす根本的な原因が明らかになれば、再発しない対策を立てることができるわけです。そこで、真因を追求するために、現状分析で見つけた問題を具体化して「なぜ?」を繰り返します。「フィルターが詰まったのはなぜ?」と問いかけ、出てきた答えに対してさらに「なぜ?」を重ねていきます。
これは「なぜなぜ分析」と呼ばれている手法で、トヨタ自動車の問題解決の考え方から生まれました。今では世界的に活用されています。
↓
A.掃除をせずに放置していたから
↓
Q.掃除をせずに放置していたのはなぜ?
↓
A.担当者や掃除の頻度が決まっていないから
↓
Q.担当者や掃除の頻度が決まっていないのはなぜ?
↓
A.社内に明確なルールがないから
↓
Q.社内に明確なルールがないのはなぜ?
↓
A.議題として誰も提案してこなかったから
このように「なぜなぜ分析」を重ねていくことで真因が見えてきます。真因追求は問題が入り組んでいて複雑なときに有効です。なお、シンプルな問題で5Sなどですぐに解決できるものであれば、真因追求のプロセスを省くこともあります。
突き止められた操作ミスの真因
先ほどのCAの事例では、カートの操作ミスをする事例は若年層のCAが起こしていることがわかりました。そこで、なぜ若年層のCAがカートの操作ミスをするのかを「なぜなぜ分析」を使って追求してみました。

そうすると、トレーニングと実機での環境が異なるため実際の現場でのカートの重さがわからず、操作ミスにつながることが見えてきました。さらに真因追求を進めていくと、「近くに練習できる場所がないから練習できない」という真因が見えてきたのです。
ANAグループは、ABB(ANA Blue Base)という訓練施設を持っています。ここでは運航乗務員(パイロット)、客室乗務員(CA)、整備士、グランドハンドリングスタッフ、グランドスタッフなどが業務に必要な訓練を受けています。CAもここでしっかり訓練を受けているものの、現場配属後に、日々経験を積むことができる場所が近くにあるといいという声が出されたのです。
「カート操作を誤る」という事象を見ただけでは、「近くに練習できる場所がない」ことが原因だとは、なかなか思い至りません。しかし何度も「なぜ?」を繰り返すことによって、想像もつかなかったような真因にたどり着くことができます。現状分析から真因追求がしっかり進められれば、解決策の立案に苦労することはありません。
課題解決に苦労しているという企業は、この現状分析と真因追求に着目してカイゼンを進めてみてください。