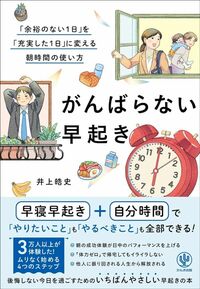※本稿は、井上皓史『がんばらない早起き 「余裕のない1日」を「充実した1日」に変える朝時間の使い方』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
朝やることを「曜日ごとに変える」は間違い
朝に「自分時間」ができたら、やりたいことがたくさんあるという人もいると思います。
散歩もしたいし、英語学習もしたい。そこで、月・水・金は散歩をして、火・木は英語学習をするというように、曜日によって時間割の内容を変えようと考える人もいるかもしれません。
しかし、これはおすすめしません。続かなくなる恐れがあるからです。少なくとも平日は「毎日同じ」と考えましょう。(※本記事では月~金曜日を仕事のある日=平日として考えます)
たとえば、月・水・金は散歩、火曜日と木曜日英語学習、土日はフリーと決めたとします。
もしも火曜日の朝に早起きができなかった場合、「次の日にやればいいや」と考えるでしょう。ところが、水曜日は散歩の日なので、結局その日は英語学習の時間はとれず、木曜日に持ち越されます。木曜日はもともと英語学習をやると決めた日ですが、遅れたぶんを取り戻すには時間が足りず、また次の曜日に持ち越しになり……こうしてどんどん持ち越しがたまってしまうことになります。
だったら決められた予定のない土日で取り返せばいいじゃないかと思うかもしれませんが、本来自由に使えたはずの時間を持ち越したタスクの消化に充てるのは、気持ち的にも相当な負担になります。
こうなってしまうと、結局英語学習をやるのが億劫になってきて、週に1回もやらなくなるということになりかねません。
日によって内容を変えること自体が間違いなのです。
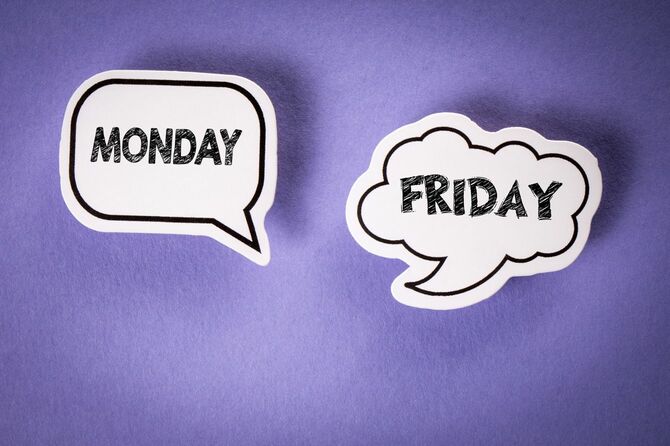
平日の朝は毎日同じことをやる
繰り返しになりますが、「平日の朝は毎日同じ」がポイント。とくに朝が苦手な人や初めて早起きに挑戦するという人は、習慣化のためにも、この基本は押さえておきましょう。
5分や10分という短時間でもいいので、毎日のルーティンに組み込んで、やらない日をつくらないようにします。
そのかわり、休日の朝はフリーにして忙しい平日の朝にはできないことに時間を使うのもいいですね。
私は毎朝やることがすごく多いのですが、5分や10分という短い単位で時間割を組んで「毎日やる」という姿勢でこなしています。
まずは欲張らず、シンプルに「毎日同じことをやる」ことを優先しましょう。曜日によって内容を変えたり、イレギュラーな日は認めないのがコツです。
やりたいことがたくさんある人は、ルーティンが完全に習慣化され、軌道にのってきてから、メニューを増やしたり、変更したりと、カスタマイズしていきましょう。
できない日があっても一喜一憂しない
ただ、ときには朝起きられなかったり、家族行事や会社行事によって自分のルーティーンが崩れることもあります。
もちろん毎日続けられることがいちばん理想ですが、気負いすぎて辛くなってしまうようでは意味がありません。できない日があっても一喜一憂する必要はないのです。
事前にできる対策としては、ルーティンをもう少し大きな単位で考えるという方法があります。
「今月は家族の予定が詰まっているな」「梅雨だから毎日外でランニングは難しそうだな」と思ったら、1週間や1カ月という「全体像」をつくっておいて、その中で帳尻をあわせていくというスタンスで考えることをおすすめします。

ルーティンの組み立て方3ステップ
組み立て方を考えてみましょう。大きく3つのステップがあります。
①目的を決める
「ランニング」や「英語学習」、「読書」などの目的を決めます。
②月単位の時間を決める
目的が決まったら、月単位でどれくらいやりたいのか、理想の目標値を決めます。
たとえば「月60km走る」「英語を月30時間勉強する」「本を月5冊読む」などです。
③1日単位に落とし込む
1カ月の目標値が決まったら、それを1日単位の数字に落とし込みます。
「月60km走る」なら、1日にすると2kmです。自分の今の体力をふまえながら、2km走るために必要な時間を15分と考えます。
「英語学習を月30時間やる」なら、1日あたり1時間。「本を月に5冊読む」なら、1冊を読むのに3時間かかるとして、月に15時間が必要です。これを1日あたりに置き換えて、1日30分と割り出します。
このように、まずは月単位で確保したい時間を決めてから、1日単位の時間に落とし込んでいきます。
1カ月単位で目標値を考えておくと、毎日「できた/できなかった」で一喜一憂する必要がなくなります。
もし15分のランニングができない日があったとしても、週末にランニングの時間を設けるなどして、別の日でリカバリーすればいいのです。このようにしながら全体として目標が達成されれば、落ち込むこともありません。
複数のやりたいことをセットにする
さらにいえば、「自分時間」は、趣味や資格勉強などの「目的系」と掃除や料理などの「生活系」をセットにして考えることをおすすめします。
朝の「自分時間」が1時間なら、目的系30分、生活系30分などとします。もちろん、15分単位で区切るなど、もっと細分化してもいいです。
複数のやりたいことをセットにしておけば、もしどちらかひとつ(どれかひとつ)しかできなかったとしても「最低限これだけはやれた」とポジティブに考えることができるからです。
たとえば前日に飲み会があって、いつもより寝る時間が30分遅くなってしまったとします。睡眠時間は削らないのが基本なので、起床時間も30分遅れることになります。すると、朝の「自分時間」はいつもより半分の時間しか確保できないことになります。
このようなとき、私なら「目的系」をカットして、30分の自分時間は「生活系」に充てます。生活の土台となるのは「生活系」のほうだからです。
ランニングや読書ができなくても、身の回りを整頓したり、きちんとした食事がとれていれば、気持ちが安定します。
ルーティンどおりの時間が確保できなかったときも、その日自分が「ごきげん」でいられるように、あらかじめ選択肢と優先順位を考えておくというのも1つのアイデアです。