※本稿は、和田秀樹『50代うつよけレッスン』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
自己愛の満たされ方には3種ある
50代以降の人生では、自己愛が大切です。
「自己愛」というのは「自分が大事である」という心理全般のことですが、自己心理学の始祖であるハインツ・コフート(1913~1981)は、人の自己愛の満たされ方には3つの種類があると言いました。
一つは、人から褒めてもらうとか認めてもらうことによって自己愛を充たす「鏡自己対象転移」です。主に自分に注目してくれる親や養育者、つまり「鏡」のように自分を見てくれる存在が、その人の野心を育てます。
二つ目は、理想の対象を通して自己愛を充たす「理想化自己対象転移」です。
「偉い先生に診てもらっているから、自分は大丈夫」というように、自分が理想とする対象者に自己愛が支えられると転移が生じ、「自分はこうなりたい」という道標ができるのです。
そして「鏡」でも「理想」でも満たされない自己愛を支えてくれるのが、3つ目の「双子自己対象」です。
たとえば、誰かに褒められても、それは真意ではないと感じたり、理想対象のそばにいても、その相手にひがんでしまったり、自分のマイナス部分が気になってしまったりすることがあります。それは、「鏡」も「理想」も所詮、自分とは違う人間だと感じてしまうからです。
そもそも人間には、「他人と同じでありたい」とか「この人と同じ人間と思いたい」という根源的な欲求があるとコフートは述べました。人には、何でも話せてお互いを理解し合えると感じ、「この人は自分と同じ人間だ」と心から実感できる相手が必要なのです。それが「双子自己対象」です。
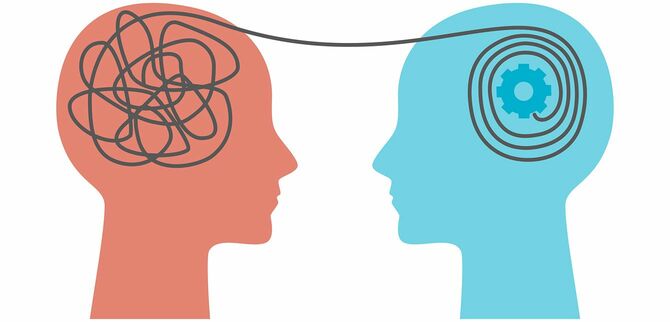
共感と同情の違いでわかる本当の仲間
「双子自己対象」をより具体的に述べると、気の置けない親友や、趣味を共有する仲間、自分と同じような立場に立っている人、同じような価値観を持っている人など、「この人と自分は同じ人間だ」と感じられる相手のことです。特にコフートは、「共感を覚える仲間がいるかどうか」が重要だと言っています。
「共感」と「同情」は似ているようで、実は極めて異なります。
同情も共感も、相手の感情を自分ごとのように追体験することですが、「同情」という表現は、相手が悲しみや苦しみなどのネガティブな感情を抱えているときに使います。
そして、どちらかといえば相手より心理的に上の立場に立ち、相手を「かわいそうに」と労ってあげる感覚です。ですから、失業したときや失恋したときなど相手が困窮しているときには同情しますが、相手が昇進したときや素敵な恋人ができたときには同情するとは言いません。
一方、「共感」はもう少し広い意味で用います。
相手が辛い目に遭ったときは一緒に悲しみ、相手が理不尽な思いをしたときには一緒に怒って、その思いを共有します。それだけではなく、相手に喜ばしいことが起きたときに一緒に喜ぶのが共感です。本当に仲のいい友だちの場合は、たとえば相手が出世したり、恋人ができたりすると、こちらまで嬉しくなります。
50代以降の人間関係は量よりも質
ですから、共感というのは、同情よりハイレベルな感情と言えます。
辛い目に遭った人の話を同情しながら聞くのはそれほど難しくはありませんし、それほど仲のいい相手でなくてもできます。
でも、相手が幸せになったときに相手と同じように喜ぶのはそれほど簡単ではないし、本当に仲が良い相手でなければできません。仲が良いと思っていた相手に、出世した話をしたらひがまれたとか、恋人ができたら嫉妬されたということもあり得ます。
それゆえ、お互いに共感の感情を持てる相手というのは、とても貴重なのです。
こういう存在を一人でも二人でもいいから、持つことが大事です。友人でもいいし、パートナーでも、同じ趣味を持つ仲間でもいいのですが、それが真に豊かな人間関係につながっていきます。
年齢を重ねた人にとって大事なことは、人間関係の量よりも質なのです。
人間関係の基準はここに
また、人間関係も、40代後半くらいから60代にかけて大きく変わっていきます。
一般的に、40代後半くらいまでは会社のなかでも出世競争があり、同期に負けて悔しい思いを感じたり、劣等感を抱いたり、卑屈になったりする人もいるかもしれませんが、50代半ばを過ぎると出世競争も一段落して、不思議なことに、出世している同期を心から応援できるようになる人も少なくありません。
たとえば、50代半ばで同期が専務になったら、「おまえは同期のホープだ。俺たちの分まで頑張ってくれよ!」と素直に言えるようになるなど、相手が自分の競争相手ではなくなって、利害関係が絡むこともなくなると、純粋に同期を応援したい気持ちが芽生えてくることがあります。

他人と比較することなしに社会のなかで生きていくのはほぼ不可能ですし、人間的な成長に人との競争や自己研鑽は欠かせませんが、もう50歳を過ぎたら、もっと気楽に考えてもいいでしょう。
会社や社会の基準ではなく、自分の心の基準で生きていけばいいのです。
定年後のザンネンな人の特徴
そして、自分が楽しめるもので共感を覚える仲間を見つけるのも、一つの生き方です。
肩書きや会社の力を気にせずに生きられるようになるのは、60代以降です。
60代までの人生では、会社組織の肩書きにとらわれた生き方をしている人も多いでしょう。「この人はあの大企業の部長なのか。大したものだ」「小さな会社の課長なら、自分のほうが上だ」などと、肩書きや会社名で他人と自分を比べて物ごとを捉える人も少なくありません。
でも、退職したらみんな一緒です。
仮に会社内で出世競争に勝ってきた人でも、役職定年を迎えた後は会社に残れなくなって系列の子会社へ出向する人も多くなります。ましてや定年退職後には、会社の肩書きはなくなるわけです。退職してから何年も経っているのに「○○会社の元部長です」なんて自己紹介していたら、ただのイタい人になってしまいます。
それは医者でも同じです。どんなに有名な大学の医学部教授になれたとしても、定年を迎えたら、その座はなくなってしまいます。名誉教授の名刺を見せる人がいますが、これもまたザンネンな感じがついついしてしまいます。
「他人の目の奴隷になるな」というアドラーの教え
退職後に何者でもない一人の人間になったとき、自分に残るものは何か。
50代以降はそこから始まる後半生を、楽しみながら味わい尽くせばいいのです。
コフートと同じように、他者との「共感」を重視したのが、『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)で一躍有名になった精神科医アルフレッド・アドラー(1870~1937)です。

コフートが人間の弱さを肯定して、不安を感じている相手に寄り添おうとしたのに対し、人間の本質的な強さを信じたアドラーは、相手に困難を克服する力を与える「勇気づけ」を行いました。
このアドラーは、「仲間」についても興味深い説を唱えています。
アドラーは、私たちは「共同体感覚」の世界にいる限り、他人から嫌われる心配をしなくてもいいのだと主張したのです。
共同体感覚というのは日本では誤解されやすい言葉ですが、同調圧力の強いムラ社会に同調していく、という意味ではありません。むしろ、周りに合わせなければいけないとか、周りに迷惑をかけてはいけないというのは、アドラーによると「他人の目の奴隷になっている」ことになります。
共同体の真の条件とは
そうではなくて、このなかにいる自分も他人も同じ人間なのだから、言いたいことを言っても排除されることはないという安心感を持てるのが共同体感覚だと言うのです。
この共同体感覚を持っている人とは、自分のことは何でも受け入れてもらえるという安心感があり、お互いにどんなことを言っても糾弾されない人間関係があります。
つまり、周囲が「仲間」なのだと感じられることが共同体の条件なのです。
大勢の人からどう言われようと、どう見られようと自分は自分だし、それを受け入れてくれる仲間が一人でもいるなら、それはあなたの共同体なのです。
40代後半くらいから、人は出世や競争という概念から徐々に自由になっていきます。
そんな時期だからこそ、そろそろ損得勘定での人間関係からは卒業して、本当に仲間だと思える人を探したいものです。

いちばん信じられるものは何か
アドラーは、共同体感覚を高めるためには、ありのままの自分を受け入れ、他人を信頼し、仲間に対して何らかの貢献をしようとすることが大事だと述べています。
ですから、「こんな自分には、どうせ仲間も友だちもできない」などと決めつけるのではなく、他人を信じて自分を受け入れてもらえる場所や仲間を探してみることです。行動する前から「どうせ仲間なんてできない」と決めつけていたら、何もできません。
また、損得勘定による人間関係で「この人の言うことを聞いていたら出世できる」とか「この人と付き合っていると人脈ができるはず」などと計算をする人もいますが、人間の計算ほどうまくいかないものはありません。
それよりも、純粋に「この人が好きだから付き合う」「面白いから一緒にいる」というほうがいいのです。なぜなら「この人と付き合っていたら、後でいいことがある」かどうかは誰にもわからないけれど、自分が今「この人と一緒にいると楽しい」のは確かなことだからです。
つまり、いちばん信じられるものは「今」なのです。

