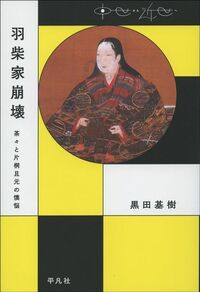※本稿は、黒田基樹『羽柴家崩壊 茶々と片桐且元の懊悩』(平凡社)の一部を再編集したものです。
江戸幕府の臣下とは違う“特別扱い”を受けた豊臣秀頼
関ヶ原合戦後、羽柴家は事実上、一大名のような存在になったが、さまざまな点から特別扱いを認められ続けた。茶々としては、秀頼が政権主宰者になることはできなくても、前政権の後継者として、一大名以上の存在であり続けることに、力点を置いていたのではないかと思われる。
しかし徳川家康は、そのような羽柴家の曖昧な位置を、これ以上は認めることはしないとして、方広寺鐘銘問題の解決のかたちをとって、豊臣家家老の片桐且元を通じて、一大名としての立場になることを要求してきたのであった。ここで茶々と且元の立場は、明確に分かれることになった。振り返れば、この時点で、茶々と且元の関係は決裂するしかなかったといえるかもしれない。

羽柴家を支え続けた家老・片桐且元もついに茶々と決裂
且元としてみれば、この家康からの要請を蹴ることは、江戸幕府との開戦にいたらざるを得ず、それは羽柴家の滅亡をもたらすものとしか考えられなかったのであろう。10代の時から秀吉に仕え、羽柴家を支えてきた且元にとって、どのような形態であれ、羽柴家の存続こそが最優先であったと思われる。しかも且元の父は、茶々の父浅井長政の家臣であり、且元自身も、早くからその長女である茶々の存在は承知していただろう。そのように因縁深い茶々から、羽柴家への二心を疑われ、結局は処罰されるにいたったことは、何とも残念であったに違いない。
そこで且元排除の急先鋒であったのは、秀頼近臣筆頭の大野治長や、親類衆筆頭の織田有楽・頼長父子であった。且元は、羽柴家中のなかで二番目に大きい所領高を有し、大坂城の城門番所7カ所のうち、弟貞隆とともに6カ所を管轄し、さらには羽柴家の財政・外交すべてを取り仕切る存在であった。あまりにもその権力は、他の家臣に比して隔絶しすぎたものになっていた。そうしたところに、他の家臣らの不満も生じていたことは容易に推測され、それを改変しようとして動いたのが、治長・有楽であったとみることもできる。そうであれば、且元による羽柴家の家政運営において、まったく問題がなかったわけではなかったのかもしれない。
対して、茶々はどうであったろうか。家康からの要請を蹴ることが、羽柴家の滅亡につながりかねないことをどこまで認識していたであろうか。且元がそれらの条件を取り次いできたことに不快を示し、且元の二心を疑ったとはいえ、最後は、且元の生命を保証し、片桐家の存続も図ろうとしたことを踏まえれば、茶々が、且元を決定的に排除しようと思わなかったことは間違いない。それはとりわけ関ヶ原合戦後から、羽柴家を一身に支えてくれた功績への感謝に他なるまい。
茶々は叔父に当たる信長の弟・織田有楽に影響されたか
しかし、茶々の政治判断の背景に、織田有楽や大野治長らの思惑に左右された面があったことは否定できないように思われる。茶々が且元との関係を修復しようしていた一方で、織田有楽・頼長父子や大野治長は、且元の排除を既定路線とし、さらには江戸幕府との開戦への道を辿っていたのであった。茶々はそうした重臣たちが敷いた路線から、どれだけ自由に判断を示すことができたといえるであろうか。そもそも政治経験に乏しかった茶々が、それらをはねのけて、独自の判断を押し通すことなど無理であったに違いない。
ここにあらためて、関ヶ原合戦後、茶々が且元に対して「自分にはしっかりとした親もおらず、相談できる家臣もいない」といっていた言葉が思い起こされる。関ヶ原合戦後の羽柴家は、且元を除いて、政治能力のある家臣はほとんど一人もいない状態になっていた。そして、且元が退去した後は、且元排除に動いた織田有楽・頼長父子と大野治長の両者が、羽柴家の家政を取り仕切ることになる。しかしその両者にしても、政治経験は乏しく、そのため江戸幕府と充分な交渉を行えるほどの政治能力は認めがたい。
この羽柴家の場合も、充分な政治能力のある家臣がいなければ、大名家の存続は遂げられない、ということの一例といえよう。ましてや主人の茶々・秀頼にしてから、充分な政治経験を有していなかったのである。政権や大名家を存続させるにあたっては、主人にはいかに高度な政治能力が必要であったのか、そこではいかに有能な家臣の存在が必要であったのかということを、あらためて考えさせられる。
大坂夏の陣後、茶々・秀頼・且元が迎えた悲劇的な最期
最後に、茶々・秀頼・且元のその後の動向について、ごくごく簡単にながめておくことにしよう。
且元が羽柴家を去った後は、織田有楽と大野治長が大坂方の総帥となって、幕府との交戦におよぶものとなった。そこでの作戦は、当然ながら籠城戦であった。10月12日、大坂方の軍勢は、幕府の堺奉行が管轄していた和泉国堺を攻め、これを占領した。ここに大坂冬の陣が開幕することになる。

これを聞いた且元は、翌日、すぐに茨木城から軍勢を派遣したものの、迎え撃ちにあう羽目になった。さらには、茨木城を攻撃されるような情勢になった。そのため且元は15日、京都所司代の板倉勝重に救援を要請、これをうけて幕府方の軍勢が救援に駆けつけてくることになった。こうして早くも且元は、幕府方として、大坂方と対戦するにいたっている。
片桐且元は仕えていた大坂城の茶々たちを包囲する
23日に、家康が京都二条城に到着すると、幕府方の大坂への進軍が本格的に開始されることになり、25日、在京の軍勢が先鋒となって、大坂に進軍することになった。そのなかには且元の姿もあった。さらに且元は、大坂方への経済封鎖を図り、大坂城近辺の絵図を提出するなど、幕府方に最大限の協力姿勢をとっている。幕府方からの信用を得るためであろう。そして11月5日になると、且元は家康から、大坂城の包囲を命じられることになる。
同月10日に秀忠が伏見城に到着すると、同月15日に家康と秀忠はそれぞれ出陣して、大坂に向けて進軍を開始、家康は大和路を進んで住吉に着陣、秀忠は河内口を通って平野に着陣する。そうして幕府方は順次、大坂城包囲のため布陣していった。
両軍が開戦したのは26日のことで、幕府方は大坂城外に構築されていた大坂方の砦を順次攻略していった。そして最大の合戦となったのが、「真田丸」での攻防であった。ここで幕府方は大きな被害を出し、そのため戦況は膠着状態に陥る。そしてこの日、家康は茶臼山に、秀忠は岡山に着陣し、それぞれを本陣とした。
もっとも、真田丸以外の砦はすべて攻略されていたから、大坂方はほぼ惣構えの内側に押し込まれた状態になっていた。しかし、幕府方も惣構えを突破することができず、戦況は膠着化した。そのため両軍の間で和睦交渉がすすめられていった。幕府方の交渉関係者が、「茶々は対応が遅い」と観測していたのは、このときのことになる。和睦交渉は紆余曲折を経ながらも20日に合意が成立、21日に起請文が交換されて、停戦和睦が成立する。そしてその日のうちから、和睦条件であった、大坂城の惣堀の埋め立てが開始されることになる。

和睦によって大坂城の外堀を埋め、難攻不落の城が丸裸に
これをうけて家康は、25日に茶臼山を引き払って二条城に戻り、且元もこれに続いて退陣し、26日晩に京都に家康を訪れている。なお且元は、この冬の陣終結にともなって、家康から1万石の加増をうけて、あわせて4万石を領知することになっている。いうまでもなく、この合戦における功績によるものであろう。
幕府方軍勢による大坂城の堀の埋め立て作業は、年が明けて慶長20年(元和元年)正月末頃には完了をみて、それにともなって幕府方軍勢は順次、退陣していった。そうして大坂城は、本丸のみが残された、事実上の裸城になった。ひと頃までは、それら堀の埋め立ては幕府方の策略とみられていたが、現在では、史料をもとに、そもそもの和睦条件であったことが確認されている。
冬の陣後、大坂城の浪士たちが織田有楽と対立し追い出した
ところが、もう一つの条件であった、牢人の召し放ちについては、進展しなかった。あろうことか在城衆は、幕府方軍勢が引き揚げると、すぐさま堀の掘り返しや建物の再建を始めた。さらに武具を用意して、明らかに再戦の動きがすすめられていった。そうした状況をうけて、大坂方の最高首脳の一人となっていた織田有楽が、大坂城から退去した。有楽は先の和睦締結を担った一人であった。条件の不履行は、ただちに再戦につながることになる。
在城衆のなかには再戦を推進する勢力が大きく、有楽との間に激しい路線対立が生じていて、有楽はいわば、それに敗れて退去せざるをえなくなったのであろう。有楽退去の後は、大野治長が大坂方の唯一の総帥になったが、彼も先の和睦締結を担った人物であり、彼もその後に再戦推進勢力から暗殺されかけるという始末であった。もはや大坂方では、それらの勢力をまったく制御することができなくなっていたことがわかる。もちろん茶々と秀頼に、その能力がなかったためであった。
ついに大坂城落城、助命かなわず茶々と秀頼は切腹させられた
家康は4月1日に、大坂城攻めのための陣触れを発し、ここに再び幕府は大坂城を攻めることになった。且元はこの時、駿府で与えられていた屋敷に居たが、幕府軍の上洛に従って、その後は秀忠軍に従軍した。合戦は4月27日、大坂方の先制攻撃によって始まった。大坂夏の陣の開戦である。本格的な交戦は、同月29日の樫井合戦から始まり、幕府方軍勢は大坂方を破りながら進軍していった。5月6日に道明寺合戦と八尾・若江合戦で激戦が展開されたものの、勝利した幕府方軍勢は、さらに大坂城に迫った。
そして翌7日、最後の合戦となる天王寺合戦が展開された。よく知られているように、真田信繁が家康本陣に三度まで突入したものの、反撃をうけて戦死にいたる合戦である。大坂方は敗北、幕府方軍勢は大坂城に攻め寄せていった。
大坂城では火の手が上がり、やがて天守にまで及んだ。茶々・秀頼らは天守下の山里曲輪のなかの土蔵に避難した。8日朝までにその土蔵も焼けたらしく、その焼け残りに隠れていたところを且元が見つけたという。それから幕府方と茶々・秀頼の助命交渉が行われたが、叶わず、ついにその日の昼に、茶々・秀頼らは自害して果て、羽柴家は滅亡を遂げた。茶々は47歳、秀頼は23歳であった。

茶々には「羽柴家を滅亡させてもいい」という覚悟があったか
最期を迎えるに際して、茶々は何を思っていたのかは、もちろんわからない。しかし、一大名の立場になるくらいなら、自害し、羽柴家を滅亡させてもよい、という考えまで持っていたのか、私には疑問に思える。自害にいたったのは、幕府方が助命を認めなかったためであり、幕府がそう判断したのは、大坂城が落城するまで、大坂方が徹底抗戦したためであった。徹底抗戦した相手を助命する作法は存在していなかったのである。
すでに状況は、かつて家康の息子・秀忠が将軍に任官した際、秀頼の上洛を拒否した段階とは異なっていた。このことは茶々も認識していたであろう。大坂冬の陣の和睦で、大坂城が裸城になることを容認したのも、何よりも羽柴家の存続を図ったからのことであったに違いない。そうであれば、その後、なし崩し的に再戦にいたってしまったのは、そうした動きに対して的確な政治判断を下すことができなかったためのように思われる。かつて茶々は且元に、自分にはきちんとした家臣がいないことを訴えていた。その結果としかいいようがない。
羽柴家の“最後の家老”だった片桐且元も20日後に死去
さて合戦後、且元は大和国の所領に戻ったが、その後、京都三条にある屋敷に移って、養生した。且元は前年から「咳病」を患っていたらしく、その養生のためとみられる。しかし5月28日、同地で死去した。享年60であった。その死は、かつての主人の茶々・秀頼の死去から遅れることわずか20日であった。
且元が死去したのが、茶々・秀頼の死去から20日後であったところに、何やら因縁のようなものを感じざるをえない。実際にも且元の死去については、実は自害であったという見解もみられているが、真相はもちろん不明である。しかし前年から病気であり、しかも年齢も60歳であったことからすると、病死とみるのが自然であろう。それが茶々・秀頼の死から20日後のことであることをみると、何らかの関係を思わざるを得ない。茶々・秀頼が自害し、羽柴家が滅亡してしまったことへの気落ちによるものであったのかもしれない。
且元は、早くから秀吉に仕えていただけでなく、秀頼が羽柴家当主になって以来、その重臣として、さらには唯一の家老として、茶々・秀頼を家長とする羽柴家を支え続けてきた。
しかし最後は、江戸幕府との関係の在り方をめぐって決裂にいたり、且元は羽柴家の滅亡を見届けることになった。且元の人生は、羽柴家とともにあったといって過言ではない。そのことからすると、羽柴家の滅亡により、自身の人生の終わりを感じたことであろう。羽柴家の滅亡後、わずか20日で人生を終えることができたことは、且元にとって満足なことであったかもしれない。