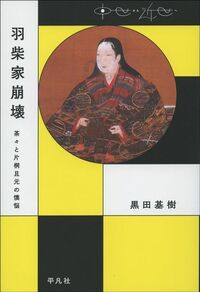※本稿は、黒田基樹『羽柴家崩壊 茶々と片桐且元の懊悩』(平凡社)の一部を再編集したものです。

「気鬱」の病で医者にかかっていた33歳の茶々
家康が、将軍任官を見据えて、後陽成天皇の行幸を迎えるための新たな屋形を、京都に造営することの計画が明らかになったのは、伏見城に移ってから2カ月後の慶長6年(1601)5月のことであった。その直後といっていい6月10日、茶々は医師曲直瀬玄朔の診療をうけている(『玄朔道三配剤録』)。これを編集した『医学天正記』にみえる記載を掲げよう。
この年、茶々は33歳であったから、「御年三十余」というのは合っている。症状は、「気鬱」「不食」「眩暈」であった。気鬱により、食事できず、さらに眩暈がしていた、ということらしい。この症状に対して曲直瀬玄朔は、「快気湯」と生薬の「木香」を飲ませたことがみえている。
これによってこのとき、茶々はいわゆる鬱病に罹っていたことがうかがわれる。ただし、ここには病状だけが記されているにすぎないので、どうしてそのような状態になったのかは、もちろん不明である。しかし茶々は、羽柴家当主秀頼の後見役として、事実上の羽柴家の女主人であったことからすると、やはりその原因は、羽柴家を取り巻く政治情勢によるものと考えるのが妥当と思われる。
家康は伏見城を拠点に移し、将軍任官を狙っていた
そのようにみた場合、何よりも思い当たることは、家康との関係の変化となろう。3月、家康は大坂城から伏見城に移って以後、伏見城を「天下の政庁」とし、あわせて諸大名の屋敷も大坂から伏見に移転させた。このことは、諸大名が忠節を示す対象が秀頼ではなく、家康になったことを意味していた。またそれとともに、家康によって、秀頼の居城と領知が確定された。これにより羽柴家は、政権から明確に分離され、その領国支配によってのみ存立を遂げることになったから、そうした家の存立の在り方からみれば、事実上、一個の大名と変わらない存在に位置づけられることになった。
そのうえで家康は、将軍任官を意図するようになっていた。これは明らかに、羽柴政権を解消し、自身を主宰者とする新たな政権樹立のためであった。すでに家康は、諸大名に対して主人として存在し、朝廷との関係や諸外国との関係を執り行い、事実上の「天下人」として存在していた。将軍任官は、家康を名目的にも「天下人」とする装置であり、これにより、名実ともに「天下人」としての地位を確立させるためのものであることは、誰の目にも明らかであったに違いない。
茶々は秀頼の関白任官を狙っていたが、羽柴政権は解体に
茶々が気鬱になったのは、このように羽柴政権の解体が進められている情勢をうけてのことであった、とみていいのではなかろうか。茶々の意向はおそらく、先に触れた伊達政宗も認識していたように、秀頼が成人した暁には、関白に任官され、「天下人」の地位を譲られることであったに違いない。
そのためそれまでの間、秀頼は次期「天下人」としての体裁を維持し続ける必要がある、ということであったと思われる。その場合、秀頼の居城と領知が確定されてしまったことは、いわゆる羽柴政権の財政から完全に切り離されたことを意味したから、大きな痛手と認識しただろう。
いずれにせよ、家康の伏見城移転から急激に進められた、羽柴政権解体の動向に、茶々は、秀頼の将来、羽柴家存続の在り方について、大いに気を揉むようになったのではなかろうか。

羽柴家のトップとして「政治的決定が遅い」と書かれた茶々
ところでもう一つ、茶々から豊臣家家老・片桐且元に宛てた文書からうかがわれることについて触れたい。それは茶々の対応の遅さである。茶々は前年から、且元の領知を増やしてもらいたいと家康に申し入れしようとしていたらしいが、「何かと申し候てうちすぎ候」と、いろいろ考えてしまうことなどがあって、結局は実現していなかった。今回になってようやく、家康に申し入れを行ったようであるが、且元から送られてきた返事への返事、すなわちこの消息を出すことについても、「心あしくておそく成り申候」と、気配りが悪くて遅くなってしまった、と述べている。
これらのことをみると、茶々はどうも、物事に迅速に対応できるような性格ではなかったように思われるのである。このことに関しては、後のことではあるが、思い起こされる話がある。『駿府記』慶長19年(1614)12月25日条に、大坂冬の陣での徳川方と羽柴方との和睦交渉がすすめられているなか、家康が交渉に関わっていた側近の後藤庄三郎(光次)に、交渉の進展状況を尋ねたところ、後藤光次は、使者からの報告として、「城中悉く秀頼御母(茶々)儀の命を受け、今又女の儀たるにより万事急がざる成る故、返事延引の由」と述べている。
政治経験がなかったのにいきなり政治に関わることに
大坂城内はすべて茶々が仕切っており、しかも女性であるから、何ごとにつけても急ぐことができないので、大坂方からの返事が遅れている、というのである。
ここにも、茶々の対応の遅さがみえている。しかし、これが茶々の性格なのか、あるいは後藤光次の使者がいうように女性であったからなのか、判断はできない。とはいえ、このことで茶々を責めることはできないであろう。茶々はそもそも政治経験がないのであるから。秀吉生前において、茶々が政治に関わることはありえなかった。死後においても、「五大老・五奉行」の執政体制や、その崩壊後の家康の単独執政になっても、茶々が政治に携わる必要はなかった。
ところが慶長6年3月、家康が伏見城に移り、羽柴家が単独で存在しなければならなくなったことによって、事情が変わった。羽柴家として、外部の政治勢力との間で、さまざまな問題について、政治折衝を行わなければならなくなったのである。羽柴家当主の秀頼はまだ9歳でしかなかったから、当然ながら独自に判断はできない。また秀吉後家であった北政所も、すでに関ヶ原合戦前に大坂城を出ていたから、茶々が羽柴家の女主人として、いろんな問題について判断を下さざるをえない状況が生まれてしまっていた。
家康と折衝する重圧が茶々を気鬱の病にしたのか
且元の身上引き立てを要請する書状を、家康に出したことがみえるが、こうしたことはそれまでまったく必要なかったことであったろう。しかも家康は、かつては茶々に出仕する側にあった人物である。それが事実上の「天下人」として、羽柴家の存在をも左右する人物になっていた。そうした家康に、政治的な要請を行うこと自体、政治経験のなかった茶々にとっては、どれほど大変なことであったか、と思うのである。
羽柴家が事実上、単独で存立しなければならない状況に置かれた直後、茶々は「気鬱」になっていたが、そうした政治への対応が、茶々の気分を悪化させたのではなかったか、と思われる。そうしたなかでは、羽柴家の古参家臣であり、秀頼の家老であった片桐且元を頼りとする以外なかったに違いない。そのような状況を踏まえると、本文書にみられる「秀頼の親代わりに」という茶々の言葉は、心底からの発言であったように思われる。
慶長8年(1603)5月1日、茶々は再び、医師曲直瀬玄朔の診療をうけている(『玄朔道三配剤録』)。先の場合と同じく、『医学天正記』の記載を掲げよう。
11歳になった秀頼は内大臣になるが、家康がついに将軍に
このときの茶々の症状も、2年前と同じく「気鬱」であり、さらには胸がつかえて痛みがあり、まったく食事を摂ることができず、時には頭痛もした、というものであった。茶々は2年前に次いで、再び「気鬱」に罹っていたことが知られる。
この直前の4月20日、秀頼は内大臣に昇任していた(『時慶卿記』)。いうまでもなく、これも家康の取り計らいによる。わずか11歳での内大臣への就任であり、かつ昇任したのであるから、本来ならば喜ぶべきものであろう。ところが、その8日前の2月12日に、家康は征夷大将軍に任官、さらに内大臣から右大臣に昇任していた。これによって、家康を主宰者とする新たな徳川政権(江戸幕府)が、名実ともに誕生するにいたっていた。
そもそもその直前まで、先に触れたように、秀頼は関白に就任するのではないかと噂されていたことからすると、関白への任官ではなく、内大臣であったことに、ひどくがっかりしたことは充分に推測できる。とはいえ関白は、名目的には天皇の後見役であるから、いかに羽柴家の当主であるとはいえ、11歳の少年の任官は難しいように思われる。むしろ11歳にして、家康の次の地位である内大臣に任官しているところに、羽柴家がいまだ「豊臣関白家」としての格式を維持していたと評価することが可能である。
既に公家衆は家康が武家のトップだと認めていた
しかし茶々は、どう思ったのであろうか。前年の慶長7年(1602)2月、家康が源氏長者に就任するという動きがあった。これについて家康は、今年は時期が悪いとして、辞退したのであったが、源氏長者就任は、いうまでもなく将軍任官に等しい行為であった。家康の辞退の背景に何があったのかはわからないが、いまだ島津忠恒との和睦が成立していない状況であったことからすると、「天下一統」が遂げられていなかったためかもしれない。
そして同年12月に、薩摩の島津忠恒が家康に出仕し、列島すべての大名が家康に服属することになると、その直後に、家康もしくは秀忠が将軍に、秀頼が関白に任官するとの噂がでてくることになる。公家衆たちは、島津服属により、徳川家が将軍に任官することの障害は完全に除かれたと考えたらしい。このことはすでに、公家衆は徳川家の将軍任官を当然のことと認識していたことをうかがわせる。問題になっていたのは、単にその時期だけのことのように思われる。

茶々は秀頼が関白になれなかったことに衝撃を受けたか
むしろ注目すべきは、公家衆たちが、わずか10歳前後であった秀頼が、関白に任官することがありうると考えていたことだ。
そうすると関白の地位が、武家の場合においては、もはや天皇の後見役というような名目にとらわれるものではなくなっていたことがうかがわれる。武家と公家とでは、同じ関白という地位にあったとしても、その役割はまったく異なるものとなっていた、ということであろう。であるからこそ、わずか10歳前後の秀頼であったにもかかわらず、「豊臣関白家」の格式にあることをもって、関白の任官が可能とみられていたのであろう。
そうするとやはり、茶々にとっては、秀頼が関白ではなく、内大臣に任官したことに大きな落胆を感じたのであろうと思われる。それが再びの「気鬱」となったのかもしれない。その直前に、茶々が家康と何らかの交渉などを行っていたのかどうかまではわからないが、なれない政治交渉に携わっているなかで、大きな落胆があり、気分を激しく悪化させたとすれば、納得できるように思われる。