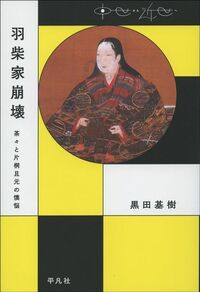※本稿は、黒田基樹『羽柴家崩壊 茶々と片桐且元の懊悩』(平凡社)の一部を再編集したものです。

2カ月ぶりに政権トップの座に返り咲いた家康
慶長5年(1600)9月15日、美濃関ヶ原において、羽柴政権を二分しての、空前の大合戦となった、いわゆる関ヶ原合戦が行われた。合戦の結果、「大老」筆頭の徳川家康を総帥とする江戸方が勝利し、「大老」毛利輝元を総帥にした大坂方は敗北した。大坂方の戦場での大将であった「大老」宇喜多秀家、さらに大坂方の首謀者であった奉行石田三成らは逃亡(三成は21日に捕縛、次いで処刑される)、もう一人の首謀者の奉行大谷吉継は戦死するなど、大坂方の大敗であった。
勝利した徳川家康は、大坂城に向けて進軍、17日に石田三成の本拠近江国佐和山城を攻略し、その日に江戸方大名の福島正則・黒田長政に命じて、大坂城の毛利輝元に、輝元に対して疎略にしない意向にあることを伝えさせている。輝元は大坂方総帥として、大坂城西の丸に在城していた。
西の丸には、その直前まで、政権執政にして「天下人」の地位にあった家康が在城していたのであり、石田三成・大谷吉継の挙兵に呼応した毛利勢が、家康留守居衆を追放して、同城を占拠していたものであった。ここで家康が輝元に対して、疎略にしない意向を示しているのは、輝元を穏便に西の丸から退去させるためであった。
まずは西軍大将・毛利輝元を追い出し大坂城西の丸へ
これをうけた輝元は19日、福島正則・黒田長政に宛てて、家康宿老の井伊直政・本多忠勝から領国安堵の起請文を出されたことについて感謝を示し、22日付けで、福島・黒田両名宛の起請文、井伊直政・本多忠勝宛の起請文、そして江戸方大名の池田照政(のち輝政)と井伊直政・本多忠勝宛の起請文を作成し、家康からの領国安堵を謝するとともに、大坂城西の丸を家康に明け渡すことを誓約した。
そして25日付けで、江戸方大名の池田照政・福島正則・黒田長政・浅野幸長・藤堂高虎は連署して、輝元に対して、井伊・本多の起請文の内容(輝元への領国安堵)は偽りではないこと、輝元が家康に対して別儀なければ馳走すること、家康は輝元に対して疎略にしないこと、について起請文を作成した。
このような、江戸方大名の有力者である池田・福島・黒田・浅野・藤堂の仲介によって、輝元は、家康からの領国安堵の意向をうけて、家康への忠節を誓い、在城していた大坂城西の丸から退去することになる。そして27日に、家康は大坂城に戻り、本丸において羽柴家当主秀頼に対面し、以後、家康は再び西の丸に在城するとともに、さらに嫡子秀忠が二の丸に在城することになった。家康は、ほぼ2カ月ぶりに政権執政の立場に返り咲いたことになる。
二の丸に息子・秀忠を駐在させ徳川家による統治を始める
合戦が、理論的には政権内部の権力闘争であったとしても、江戸方の総帥であった徳川家康が勝利したことは、その後の政権の性格に、少なからぬ変化をもたらすことになった。家康が、秀頼に対面した後、大坂城西の丸に復帰したことは、石田・大谷挙兵以前に戻ったにすぎないともいえる。

しかし、その立場の在り方は、それまでと比べると大きく異なるものになっていた。西の丸だけでなく、二の丸に家康嫡子の秀忠が在城したのである。いうまでもなく大坂城は、羽柴家の本拠であり、城内に在城できるのは、羽柴家の家族に限られていた。家康が西の丸に在城してからは、政権執政が在城するものとなったが、新たにその嫡子の秀忠が在城するようになったことは、政権運営は徳川家によって行われることを示すものとなった。
秀吉死後の政権の執政体制は、いわゆる「五大老・五奉行」であったが、すでに「五大老」のうち、(前田利家の嫡男)前田利長は家康に屈服しており、ここに石田・大谷に味方した毛利輝元も家康に屈服、宇喜多秀家は没落した。残る上杉景勝も、この時はまだ交戦状態にあったが、やがて家康に屈服してくることになる。
「五奉行」のうちでは、すでに石田三成・浅野長政は失脚していたうえ、三成は挙兵により政治復帰したものの、この合戦で没落、石田・大谷に味方した残る三奉行のうち、長束正家は9月30日に自害し、増田長盛は領知を没収され、高野山に幽閉となり、前田玄以のみが赦されたにすぎなかった。
家康・秀忠は合戦後「羽柴姓」を使わなくなった
秀吉死後の執政体制の「五大老・五奉行」制は完全に崩壊し、執政は「大老」筆頭の徳川家康のみが担うことになった。そしてその政治は、実際には家康の嫡子秀忠をはじめ、その一門・宿老たちがあたっていくことになる。諸大名との取次も、それまでは「五奉行」をはじめとする羽柴家直臣が担っていたのであるが、合戦後は、井伊直政・本多忠勝・本多正信など、家康の宿老が担うようになっていった。これは完全に、政権運営は徳川家によって執り行われたことを示している。
そのことを象徴する出来事といえるのが、家康・秀忠父子が、合戦後は羽柴名字を称さなくなったことであろう。それまで家康は「羽柴江戸内大臣」、秀忠は「羽柴江戸中納言」、秀忠の庶兄の秀康も「羽柴結城宰相」というように、いずれも羽柴名字を称していた。羽柴名字は、政権主宰者の秀吉・秀次・秀頼といった羽柴家当主の名字であり、秀吉はそれを、旧織田家臣や旧戦国大名など服属してきた有力大名に対して、公家成の身分(従五位下・侍従以上の官職)とともに与えて、羽柴家の「御一家」として、政権内の政治秩序のなかに位置づけていたのである。
政権代理人の「大老」ではなく政権主宰者という立場を取る
羽柴政権のもとでは、各地の有力大名はすべて羽柴名字を称する公家成大名とされて、政権はそれらの大名を統合する体裁がとられていたのである。いわゆる「五大老」の有力大名も、もちろんすべて羽柴名字を称していた。ところが合戦を契機に、「大老」筆頭であり、政権執政であり、諸大名中もっとも政治的地位が高かった徳川家康と、その子秀忠・秀康は、羽柴名字を廃し、本来の徳川名字あるいは松平名字を称するようになったのである。このことが持つ外見的な意味合いは大きいといわねばならない。
それまで家康は、羽柴家の「御一家」の一員として、政権執政の立場にあったという体裁がとられていたのであったが、以後は「御一家」を名目にするのではなく、合戦勝利者として、政権執政にあたることを意味するものとなったからである。

関ヶ原で負けた大名の領地を独断で取り上げ味方に与えた
そのうえで10月にはいると、いまだ一部地域においては戦時体制が継続されていたものの、家康は、合戦で敵方になった大名たちの領知の没収・削減と、味方した大名への領知の加増転封を行った。そこで対象になったのはすべての大名であり、羽柴家の唯一の一門衆であった小早川秀秋をはじめ、羽柴家譜代の有力大名の福島正則・池田照政(輝政)・浅野幸長・加藤清正・黒田長政らにもわたっていた。
この領知宛行について、茶々・秀頼の関与はまったくなく、すべて家康の独断によるものであった。理屈的には、政権運営は家康に任されているので、そこに茶々・秀頼の意向が入る余地はなかったのである。
こうした家康による諸大名への領知宛行は、石田・大谷が挙兵する以前になる、慶長5年2月の森忠政への信濃川中島領の宛行や、長岡(のちに細川)忠興への豊後杵築領の宛行などがみられていた。石田らは、こうした家康の行為に強く反発して、挙兵に及んだのであった。そうした石田らに勝利した家康にとって、戦後その路線を踏襲するのは至極当然のことであったろう。
石田三成の旧領は徳川四天王の井伊直政に与えた
しかし、それだけではなかった。家康は、自身の一門や宿老にも、敵方からの没収地や味方大名の転封後の地の宛行を行った。福島正則が安芸・備後2カ国に転じたあとの尾張国には、四男松平忠吉を入れ、改易された石田三成領には宿老井伊直政を入れる、といった具合である。そうして尾張国までの東海道・中山道筋は、徳川家の一門・譜代大名で固められることになり、しかも、それら家康取り立ての大名たちは、それまでの羽柴政権下における大名と同列に位置づけられることになった。
それまでの諸大名にとって、合戦後は、家康は主人に相当する立場になり、松平秀康や松平忠吉らその一門衆は、自身より上位者になり、そして宿老で領国大名になった井伊直政や本多忠勝らは、自身とまったく対等の大名として存在するようになったのである。もっともこの時の領知宛行において、家康は宛行状を出していない。このことから、この領知宛行は、家康が完全に「天下人」の地位についたわけでないことを意味するととらえられている。
征夷大将軍になる2年前、家康は大名たちの主君になっていた
いってみれば、この時の家康による領知宛行は正式のものではなく、秀頼の「代行」としてのものであり、そのためこれによって家康と諸大名との間に、ただちに主従関係が成立したわけではない、ということであろう。しかしその一方で、長岡(細川)忠興の場合にみられるように、大名たちにとって、領知を与えてくれたのは家康である、という認識がもたらされていた。決して秀頼からのものとは認識されなかった。
合戦の結果、家康が諸大名に対する領知宛行権を掌握したのは、確かなことと考えられる。そうして慶長7年(1602)からは、家康による領知宛行状もみられるようになっていくことになる。