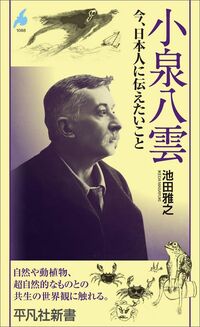※本稿は、池田雅之『小泉八雲 今、日本人に伝えたいこと』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。書籍とは文章の順番などが異なります。
ラフカディオ・ハーンの共同製作者だった妻
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、1850~1904年)の日本時代における創作と取材には、セツ(1868~1932年)の協力と同行が欠かせないものでした。二人の生活のひとこまを『思い出の記』から紹介したいと思います。

セツの『思い出の記』は、八雲とセツとの仲むつまじい夫婦関係を知るだけでなく、八雲の最高傑作といわれている『怪談』誕生の秘話を知るうえで、きわめて貴重な作品といえます。
『思い出の記』は、八雲の没後、セツが、八雲の信頼していた友人、三成重敬に請われるまま語ったものですが、三成が速記し、編集し直したものです。三成がセツを上手に導いて、一つの「文学作品」にまで仕上げた名品といってよいでしょう。三成の編集ぶりも見事だと思いますが、何よりもセツの語り手としてのすばらしさを、見落とすわけにはいきません。
セツの『思い出の記』には、八雲とセツの『怪談』完成の秘話といってよい創作現場の生なましさがつぶさに語られています。その一節を引用してみます。
(八雲は)怪談は大層好きでありまして、「怪談の書物は私の宝です」と言っていました。私は古本屋をそれからそれへと大分探しました。(中略)私が昔話をヘルンに致します時には、いつも始めにその話の筋を大体申します。面白いとなると、その筋を書いて置きます。それから委しく話せと申します。それから幾度となく話させます。
私が本を見ながら話しますと「本を見る、いけません。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければ、いけません」と申します故、自分の物にしてしまっていなければなりませんから、夢にまで見るようになって参りました。
このセツの語りからは、『怪談』は助手という立場を超えて、八雲とセツの共同作業によって誕生したことがはっきりとうかがい知ることができます。さらにいえば、『怪談』だけでなく、八雲の日本時代の13冊にも及ぶ著作の誕生の背景には、セツの助力があったことが分かります。
「私に学歴がないから」と詫びた妻セツに…
もう一つ、逸することのできない八雲とセツの心あたたまるエピソードを取り上げたいと思います。東京時代の出来事だと思いますが、セツが八雲から万葉(集)についての質問を受けたことがありました。セツはうまく答えられず、「程度の高い女学校を卒業しなかった事、および、自由に英語を話す事のできないのを残念に思う」と答え、自分の浅学を八雲に詫びたことがありました。
すると、八雲は即座に自分の著作の数々を示し、「これだけの書物は誰の骨折でできましたか」と問い返したといいます。セツのこれまでの労をねぎらう言葉でした。
没落士族の娘で、庶民の気持ちが分かっていた
このやり取りは、二人の互いの思いやりの気持ちをよく表しており、とても感動的です。セツは武士階級から一転して一庶民の身分となった女性でした。それゆえ、庶民の心をよく理解していました。八雲の創作には、高度な文学的知識ではなく、このセツの庶民性を必要としていたのです。

八雲の取り上げる文学的主題は、『怪談』もそうですが、名もなき庶民の哀歓、悲しみや喜びの声といったものでした。八雲は自分の文学世界は、「『八百屋、飴屋、僧侶、神主、占師、巡礼、農夫、漁師』たちの世界である」とセツに語っていました。そして、自分の文学世界は、インテリや大学教師たちが住む世界ではない、と主張していました。
八雲のアメリカと日本での30余年にわたる作家活動は、一貫して、『怪談』、『日本の面影』などで自分の内面を密やかに語りながらも、名もなき庶民の心や魂を語り継いでいったことにあったのではないかと、私は考えています。

『怪談』の「耳なし芳一」が読み継がれている
八雲が私たち日本人に愛されているのは、なぜでしょうか。彼の文学世界が私たち庶民の悲しみや喜びをローアングルから共感をこめて描いているからでしょうか。八雲の著書『日本の面影』や『怪談』のなかに、私たち庶民の一人ひとりの生活ぶりや、あたたかな人情の交流を認めることができます。
日本の近代文学の主流は、インテリの文学といってよいですが、八雲文学は名もなき庶民を中心に描く庶民のための文学といえます。八雲は私たちから遠い存在ではなく、私たちの身近にいる作家だと思われるのです。これは私自身、八雲の作品を翻訳して感じる親近感です。
しかし、一方で心配なのは、現代の私たちは、130年前の八雲の『怪談』や『日本の面影』で描いている日本人の心根を、理解できるのかどうか、という疑問です。つまり、彼の作品は昔の日本人のもっていた微妙な感性や情緒、人への思いやりの心を表現している文学だからです。

130年前の八雲文学を本当に理解できているか
たとえば、『怪談』の「青柳ものがたり」などは、八雲と日本人が共有していたはずの、命あるものへの慈しみの心を表現した名作といえます。
あるいは『骨董』の「和解」は、男女の死を超えての霊的な再会などをテーマにしています。人間の裏切りと残忍さのなかに、愛の永遠性という一条の光が見え隠れする不思議な作品です。この二作とも、西洋流の善悪の二元論で、むごい話だと切り捨てることはできないでしょう。
しかし、日本人のものごとの受け止め方は、むしろこうした情感の「あわい」中に、一種の「あいまいさ」のなかに、ものごとの本質が潜んでいるのではないか、と考えるのではないでしょうか。こうした日本人が従来もっていた、微妙なものごとを感知する情緒や感性は、今日の私たちにも引き継がれていると信じたいですが、現実はどうでしょうか。
惜しくも2024年8月に亡くなられた、私の尊敬する松岡正剛は、『神仏たちの秘密』(春秋社)で、八雲の日本理解の方法を大変評価なさっていました。しかし、松岡は、今日の日本人が、日本文化の本質に迫る八雲の作品を、本当に味わうことができるのかについては、危惧の念を抱いていたようです。八雲がおよそ130年前に描いた日本人の「かそけきもの」、「そこはかとないもの」への美意識をすでに失っているのではないか、と指摘しているのです。
はたして、私たちは八雲文学をとおして、日本文化のこうした微妙な美の本質を理解できるのかどうか。失われた日本人の美意識を取り戻す意味でも、八雲文学の理解はこれからの日本人の重要な試金石となるのではないでしょうか。
文学研究者が八雲に魅了されたきっかけ
ここで私が八雲文学に魅了されるようになった経緯を簡単に記しておきたいと思います。私は大学では英文学を学んだのですが、文化的背景の違いからかよく理解できなかったし、あまり楽しむこともできなかったのです。
ちょうどその頃、英語の原文で八雲の『日本の面影』や『怪談』を読んでみたのですが、これが私の感性にぴったりとなじむものを感じたのでした。八雲の日本時代の作品は、英語で書かれた「日本文学」だなと思いました。
その後、八雲の翻訳をしたり、論文のようなものを書くようになりましたが、私が八雲入門として、昔から親しんでいたのが、田部隆次の『小泉八雲』でした。今回、NHK連続ドラマ小説で、八雲の妻セツを主人公とする「ばけばけ」が、2025年9月29日から放映される予定にちなんで、新装改訂版として中公文庫から最近出版されましたが、私はその解説「名も無き庶民の心を語り継ぐ」を担当しました。
田部隆次は八雲の直弟子で、この本は八雲の評伝としては、今日でも古びていない、読みごたえのある八雲案内書といえますが、私にとっては八雲と妻セツの関係を知るうえで、とても参考になったテキストでした。私はこの田部の『小泉八雲』に収録されたセツの「思い出」を読み感動し、すっかり八雲とセツファンになったのを憶えています。