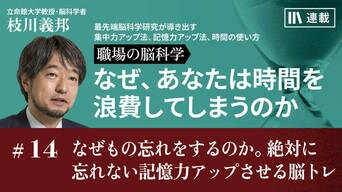家康の重臣による秀忠評
関ヶ原に遅参したのは、中山道を進んだ秀忠の軍勢が、途中で上田城(長野県上田市)の真田昌幸を攻めたところ、昌幸らに翻弄され、時間を空費したのが原因だった。このときの秀忠を「軽い気持ちで上田を攻めた」「若気の至り」などと評する向きもあるが、当たっていない。上田城の攻撃は「小山の評定によって策定された既定の作戦であって、秀忠の個人的な功名心などに発するものではなかった」からである(笠谷和比古『論争 関ヶ原合戦』新潮選書)。
とはいえ、遅参の影響は大きかった。家康は関ヶ原合戦に勝ったといっても、戦場に徳川軍の主力がいなかったため、それは豊臣系武将の働きによる勝利で、彼らの領土を大幅に加増するほかなくなった。結果として、西国の8割が豊臣系大名の領土となるなど、徳川にとっては不安定な状況が生まれてしまった。
だから、開戦から6日たって、大津にいる家康にようやく追いついた秀忠に対し、家康は面会を拒否した。また、家康は秀忠を嗣子と決めていたものの、『寛政重修諸家譜』巻七〇七によると、家康は大久保忠隣、井伊直政、榊原康政、本多忠勝、平岩親吉、本多正信を呼んで、だれを嗣子にすべきか、あらためて尋ねたという。
正信は次男の結城秀康、直政は四男の松平忠吉、忠隣が秀忠を推し、その忠隣は「乱を治め、敵に勝は、武勇を先とすといえども、天下を平治し給はんとならば、文徳にあらずしては基業をたもち給はん事かたし」と説いたとされる。すなわち、乱世において敵に勝つには武勇が優先されるけれど、天下を治めるためには、文武が兼備でなければいけない、という理屈である。
文武のバランスが◎
二次的な史料なので創作の可能性はあるが、少なくとも家康は秀忠を、このように評価したということではないだろうか。凡庸だ、鈍感だ、というのではなく、文武のバランスがとれていた、という評価である。
それでも、関ヶ原に遅参した経験は、秀忠に大きな影をおよぼしていたようだ。そこで負のイメージがついたという意識があればこそ、文武の「武」に弱点があるとは思われたくなかったのだろう。慶長19年(1614)、大坂冬の陣の際には、遅れてはならぬという決死の覚悟が見てとれる。
家康は10月11日に駿府城(静岡県静岡市)を発って23日に上洛した。一方、秀忠が6万の軍勢を率いて江戸を発ったのは23日。自分が着く前に戦いがはじまってしまっては大変だ、という思いが強かったようで、猛スピードで進軍している。
たとえば29日には、掛川(静岡県掛川市)から吉田(愛知県豊橋市)まで、およそ70キロを1日で進軍したという。その間、家康はたびたび「大軍行程ヲ急ニセバ、兵馬疲労セン。緩ニ来ラレルベシ」、すなわち、大軍が急いで進軍すれば、兵も馬も疲労してしまうので、ゆっくり進むように、とたしなめたが、秀忠は最後まで急行軍を続け、11月11日に京都に着いている。