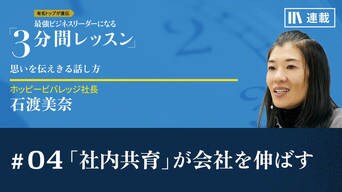収集家がヒューストンの自然科学博物館に数年単位で貸与していたところ、捜査当局が展示品を押収。エジプトへと返還された。マンハッタン地方検事長は、木棺の価値は100億ドル(約1億3000万円)を超えると推定している。
米ニュースメディアのアクシオスによると、同地の観光業と経済のさらなる活性化に貢献するとして、関係者らは返還を歓迎している模様だ。
美術品の略奪に関し、博物館や美術館側の責任が問われた例は、これだけではない。
英アート・ニュースペーパーは昨年12月、米メトロポリタン美術館がナチスによって盗まれた美術品を所蔵しており、発覚前に売り抜けようとした疑惑があると報じている。
英文化相は「危険な道である」と警告
このように返還が成立し、取り組みの成果として華々しく取り上げられている事例は、欧米諸国に点在する盗品の全体数からすれば氷山の一角にすぎない。
一部の返還を認めれば、やがてアメリカやヨーロッパに所蔵されている美術品や文化財の多くを手放さざるを得なくなるとの懸念する向きもある。
例えばロゼッタストーンが火種となっている大英博物館では、ほかにギリシャのパルテノン神殿から盗み出されたとされる大理石の彫刻が議論の焦点となっている。
英BBCによるとイギリスのミシェル・ドネラン文化相(当時)は、彫像は「私たちが手入れを行ってきたわが国の資産である」と述べ、返還要請に反発。返還を行ったならば「収拾のつかない事態を引き起こす」こととなり、「危険な道である」と警告した。
ドネラン氏が懸念するのは、一部の重要美術品の返還が契機となり、イギリスじゅうの文化財が流出する事態だ。大英博物館の収蔵品を含め、イギリスには植民地時代に属国から持ち出した文化財が多く保管されている。
アフリカで文化財の買い取りによる奪還を進めるある実業家は2018年、ニューヨーク・タイムズ紙に対し、「(返還の正当性を認めた)マクロンはパンドラの箱を開いた」と指摘している。
だからといって略奪品を展示し続けることを正当化できるわけではないが、博物館側としては所蔵庫が空になるような事態に至らないか、警戒せざるを得ない実情がある。
「文化財の保護につながった」という理屈は通るのか
返還反対派を支えるひとつの論理として、先進国の優れた環境で文化財を保管することで、貴重な文化財の保護につながるとの主張がある。アメリカの伝統あるライフスタイル誌のタウン&カントリーは、カンボジアの文化財の事例をもとにこのロジックを説明している。