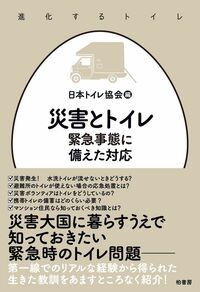外部との連携、協力には支援を受ける体制が大事
水や食料などは、外部から自主的な支援が届くことも期待できる。しかしトイレに関してはどうだろう。阪神・淡路大震災では自治体や民間から多くの仮設トイレの支援があったが、そもそも民間の自主的な支援に頼ることは心許ない限りだ。
神戸に駆けつけた岐阜県など東海地域の汲み取り事業者は、「1959年の伊勢湾台風の時に神戸市からバキューム車が駆けつけてくれた、そのときのお返しだ」と筆者に語ってくれた。地震に対してほとんど対策がなかったところを救われたのだが、このような関係に依存するだけでは心許ない。
国は、大きな災害が起きたら被災地からの要請を待たないで必要な物資を緊急輸送する「プッシュ型支援」を行うようになっている。その品目のなかに「携帯トイレ、簡易トイレ」「トイレットペーパー」が入っているが、待っていて避難所に仮設トイレが届けられるというわけではない。
必要な仮設トイレを調達し、配置するのは市町村の仕事である。その調達や運搬には民間との協力が不可欠で、特に支援を受ける体制、仕組みも用意しておかなければならない。
たとえばトイレに関する支援がきたとき、それらの物資をどこで受け取ってどう分配するのか、仮設トイレはどこに置くのか、さらに事態が収束したときに片付けはどうするのか等も考えておかなければならない。
【参考資料・文献】
・日本トイレ協会/神戸国際トイレットピアの会『阪神大震災にともなうトイレに関する支援のための調査報告書』日本トイレ協会、1995年
・日本トイレ協会/神戸国際トイレットピアの会監修、日経大阪PR企画出版部編『阪神大震災トイレパニック 神戸市環境局・ボランティアの奮戦記』日経大阪PR、1996年
・山本耕平『まちづくりにはトイレが大事』北斗出版、1996年