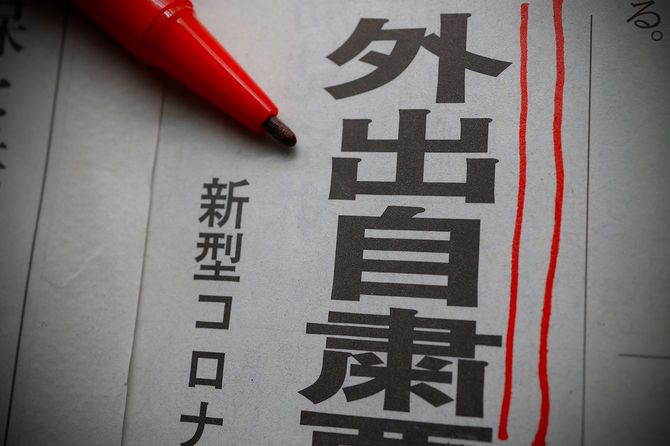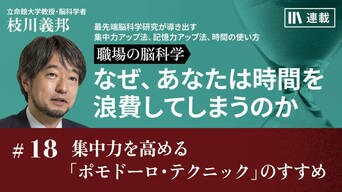ロックダウンは科学的に「有効」なのか
まず、考えておきたいのはシラクサ原則の(3)と(5)、つまりロックダウンは人権を制限してまで断行しなければならないほどに、感染症の制圧という目的達成に本当に必要な手段で、科学的根拠に基づいているのかどうか、というところだ。
短期的に見れば、ロックダウンのようなソーシャルディスタンスの手法で新型コロナの流行を一時的に抑え込むことはできる。
これは事実だが、ただし「短期的に」であって、ロックダウンを永久に続けることはできない。
つまり、一時的なロックダウンによって、感染者数のピークをなだらかにしたり、そのピークを二つの感染増の山に分割して長引かせたりしているだけで、長期的に合計を見れば感染者の総数には大差ないとの推計もある。
そして、厳しい見方をすれば、感染者数がピークになったとき、医療資源が逼迫して助けられる命が失われるのは、その国の医療体制の不備、つまり人災であって、新型コロナそのもののウイルス毒性とは別問題だともいえる。
この点で、ロックダウンの「有効性」は過剰な期待にならないよう割り引いて考えなければならないし、文化や医療制度の違う国々の間で安易に国際比較することはできない。
感染拡大の原因は“気の緩み”という議論の危うさ
お願いと自粛と忖度によるロックダウンもどきを1年以上にわたって断続的に行ってきた日本社会において、ロックダウンと法律について議論する傾向が出てきたことは好ましい変化だ。
国家や自治体からのお願いや指導とその自発的な受け入れや世間を忖度した自粛では、どこまでソーシャルディスタンスを徹底すべきか、どこまで公的に補償すべきなのか、開始と解除のタイミングを誰が判断するのか、どこ(誰)に責任があるのか、があいまいな無責任システムになってしまう。
明確な法の枠組みがあって、その明文ルールに従って社会が回ることは、権力者による恣意的な命令を許さないことにつながり、法治主義や立憲主義の基本だ。
これは、先に紹介したシラクサ原則の(1)と相通ずる。
だが、ロックダウンと法律についての議論の実際は、そういう方向ではないように見える。
新型コロナが繰り返す波のようになったのは、人々の気の緩みに原因があり、人々がソーシャルディスタンスを守らないことが感染症を拡大させている、だから法律で罰則を付けることで人々を従わせる必要がある、という上から目線の議論の声が大きい。
こうした発想は、ロックダウンの有効性に関する誤解に基づいている。