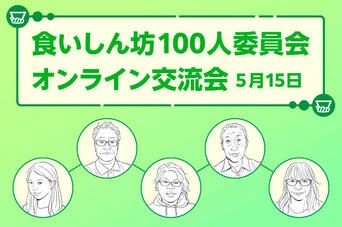政府基金は無駄遣いの温床になってきた
政府が新設した「宇宙戦略基金」が動き出す。
スタートアップ(新興企業)、企業、大学の技術開発や研究に補助金などを出し、10年間で総額1兆円規模の支援をするというものだ。
全体をとりまとめる内閣府が、4月末に支援対象22テーマを発表した。費用を100%補助するものや、一企業に500億円を超える支援をする場合もある。
「これまでにない思い切った支援」と宇宙業界は歓迎するが、内容を見ていくと支援企業の選定方法や責任の所在がはっきりせず、支援金が悪用されたり国への依存が強まったりする懸念もある。
内閣府の発表によると、第一弾として、文部科学省が1500億円、経済産業省1260億円、総務省240億円の計3000億円を出し、「宇宙輸送」「衛星」「探査」の3分野22テーマの技術開発や研究を支援する。
基金は宇宙航空研究開発機構(JAXA)に設置。JAXAが基金の運用、支援先の選定、技術支援、全体のマネジメントなどを担う。7月からJAXAが公募を始め、今年度内に支援先を選定する予定だ。
政府基金は2000年代に入ってから各省庁が競うように設立した。政府予算のように1年ごとに計上する必要がなく、複数年分をまとめて計上して使えるなど自由度が高いためだ。一方で国会などの監視の目が届かず、無駄遣いの温床になる問題が起きている。
3000億円が3倍に膨れ上がる「宇宙予算バブル」
政府は4月22日に、基金の一部事業を廃止し、約5400億円を国庫に返納すると決めた。
内閣府が、宇宙戦略基金の支援策を公表したのは、その4日後。逆風の中でも新設できた背景には、宇宙を取り巻く環境が大きく変化していることがある。
安全保障、防災、地球観測、通信など、世界で宇宙開発や利用がさかんになり、市場規模も拡大している。担い手も、国から民間へと移っている。
「1年ごとの予算に縛られたり、JAXAが企画・設計して大手メーカーに仕事を発注したりする硬直したやり方では、世界との競争に勝てない。予算も少なすぎる」――。政治家、宇宙業界、政府などからそんな声が巻き起こった。
米国は、米航空宇宙局(NASA)や国防総省などの政府機関が、スタートアップなどに資金を提供して、技術開発や研究を推進している。日本も宇宙基金を作り、そうしたやり方を目指そうとしている。
宇宙基金を足すと、今年度の宇宙予算は約8900億円になる。宇宙予算は、3年前から少しずつ増えてきたが、長年にわたって約3000億円台の横ばいが続いた。今年度は一気に拡大し、まさに宇宙予算バブルのような状況だ。