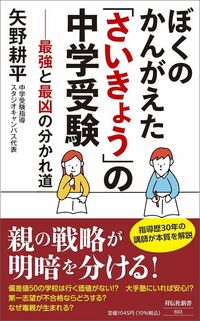カンニングに手を染めるわが子にショック
Q 小学校四年生の息子がおります。大変恥ずかしい話を打ち明けるのですが、どうやら息子は隣の席の子の答案をカンニングして得点をごまかしているようです。このような姿勢では中学受験自体あきらめたほうがよいのでしょうか。
A こんにちは。わが子がカンニングしているなんて聞いたらショックを受けるその気持ちはよく分かります。
さて、わが子が「不正行為」を働いたら保護者はどうすべきかについて私見を語ります。実はこの手のご報告やご相談は案外よく寄せられる類のものです。中学受験勉強における「不正行為」は幾つかに分類できます。
① テスト中などに隣席の子の答案を覗き見る、つまりカンニング行為を働く。
② 宿題に追われるあまり、解答を丸写しして提出する。
③ 先生の解説を聞いた後に自分の誤答をすばやく消しゴムで消して、正解を記す。
この中で一番「根が深い」場合が多いのはどれだと思われますか?
①でも②でもなく、実は③だとわたしは考えています。どうしてでしょうか?
わたしはよく塾生たちに口を酸っぱくして言うことがあります。それは「塾は間違えにくる場である」ということです。このたとえ話をすると子どもたちはすぐにその真意を理解してくれます。
「では、六年生のみんなにこれから小学校一年生用の漢字確認テストをする。もちろん全員が満点だ。このテストを実施することでみんなの成績は上がると思う?」
当然、全員がかぶりを振ります。それはそうですよね。
なぜ、学力が向上するのか? それは、「分からないことを知って、それができるようになる(定着する)」からなのですね。
わたしが言わんとすることはもうご理解いただいたでしょう。
そうです。③の「不正行為」を働く子は、自らの分からないところから目を背けてしまっているのです。現実逃避と言い換えてもよいでしょう。保護者がその形跡を発見したならば、間違えることを恐れない、いや、むしろ正々堂々と間違えることが成績向上の第一歩だということを言い聞かせてほしいと考えています。
それでは、①と②についてです。両者ともに「根が浅い」場合が多いといえます。
②についてですが、これは宿題に追われているという「焦燥感」からついやってしまうことがほとんどです。ですから、この場合は宿題を日々計画的に取り組むスケジュール作成が必要不可欠です。そのやり方についてはこれまで再三述べてきました。再度それらを見返してほしいと思います。
最後に、今回のお悩みの①についてです。