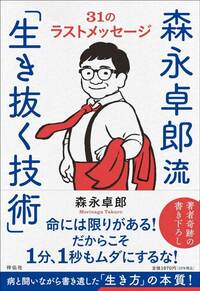ガン公表後に殺到した2000通のメールとお届けモノの中身
私は誰とでもオープンに付き合うようにしているが、もちろん、無制限に付き合うわけではない。たとえば、ガンの発覚後、私のところには2000件を超えるアドバイスのメールがきた。
私はそうしたメールに1回だけは返信をしたが、さらにメールのやり取りを続けたいとか、直接話をしたいという人が結構たくさんいる。
そういう人に対して私は、「ギャラを負担してくれるなら、やり取りを継続する」と伝えている。料金は、メールが1回1万円で最低10回分セット、直接の会話は1分あたり4000円で最低30分からだ。高いと思われるかもしれないが、毎月100万円以上の医療費を投じて延命し、生み出した時間を提供するのだから、私は高いとは思っていない。
ただし、この条件を示した途端に99%の人が、その後の連絡を自主的に絶ってくる。
「森永さんの命を救うためだったら何でもします」
そういった彼らの言い分が真っ赤なウソであることがすぐに判明してしまったということである。
奇怪なモノも…奇跡の水、キノコ、植物の種、農薬から作った新薬
誰かに何かしてもらったとき、その人にお返しをしようとすると人生を縛られてしまう。「借り」は必ずしも本人ではなく誰かに返せばよい。そうするだけで人生はラクになる。
人間はひとりでは生きられないから、あらゆる場面で人の助けを借りることになる。
問題は、その借りをどのように返すか、だ。多くの人が、助けてくれた人に借りを返そうと行動するのだが、そうすると人生が縛られてしまう。
年賀状を考えると、わかりやすいかもしれない。家に届いた年賀状すべてに返信をすると、次の年は、より多くの年賀状が来るようになる。それにすべて返信をすると、翌年は、さらに年賀状の数が増えて、やがて身動きが取れなくなってしまうのだ。
年賀状ならまだしも、これがお中元とかお歳暮だと、必要な費用がどんどん増えて、生活を脅かすことになりかねない。
私のガン罹患が明らかになったあと、私のところにはお見舞いや、治療のアドバイスのメールが殺到した。前述したようにその数は軽く2000通を超えた。私は原則として、1回だけはお礼のメールを出したが、2回目以降は一切返信しなかった。そんなことをしたら、どんどんメールが増えて、その対応だけで時間がなくなってしまうからだ。
もっと困ったのは、いろいろなものを送ってくれる人がたくさんいたことだ。なかでも、送り主が「ガンの治療に役立つ」と信じているものが、山のように届けられた。
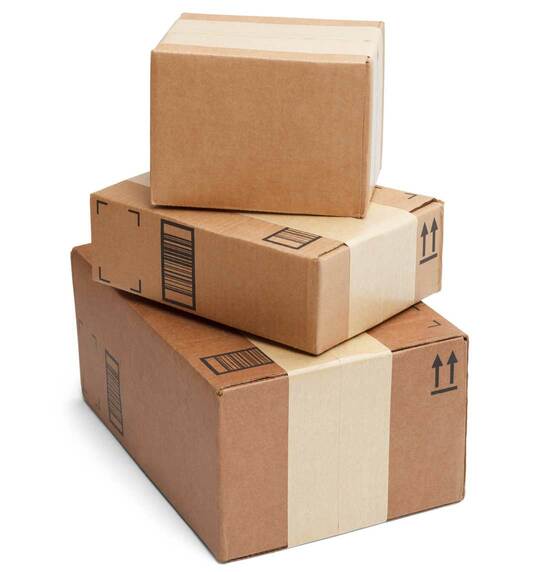
健康になる奇跡の水、重曹とビタミンC、ニンニク、サプリメント、キノコ、海藻、キチン・キトサン、植物のタネなど、種類はさまざまだ。なかには得体の知れない液体をボトルに詰めたものとか、農薬から独自に作った新薬などというものまであった。
もちろん、得体の知れない液体を飲むわけにはいかない。正直に言うと、私は送られてきたものを口にすることはなかった。
見ず知らずの人から送られたものを体のなかに入れるのが怖かったし、効果を確信することもできなかったからだ。
感謝の気持ちの表し方は人それぞれでいい
それどころか、お礼のメールもほとんど出さなかった。もし出したら、同じものが継続的に送られてきて収拾がつかなくなることが目に見えていたからだ。
ただ、私のところに連絡をくれたり、ものを送ってくる人の大部分は、善意にもとづいて行動している。その気持ちに関しては、もちろん感謝の気持ちを持ってはいるのだが、それを直接返す必要はないと私は考えている。
たとえば、ガンの治療に役立つ食品とかサプリに関しては、それを分類整理して、世間ではこんなことが信じられている、ということを書籍や雑誌記事で公表した。つまり、個人に還元するのではなく社会に還元したのだ。
そうした「借りは誰かに返す」という行動は、仕事をするうえでも、とても重要だ。私はこれまで多くの人の手を借りて、仕事を続けてきた。
ただ、直接お返しはしていない。もしお返しをすることを優先すると、私はその人の仲間になる、あるいは派閥に入ってしまうことになるからだ。
孤独に耐えられる人生を築くことが重要になる
私の仕事の信条は、「誰とも共闘しない」ということだ。仲間に巻き込まれたり、仲間を巻き込んだり、仲間外れを作らないためである。借りを本人に返すという原則は、そうした私の生き方を壊してしまうのだ。
もちろん、もうひとつの生き方があることを私は否定しない。親切にしてくれた人にていねいにお礼をして、仲間の輪を広げていく。その仲間と一緒にコミュニティを作って支え合う。
かつての日本はそうだったし、いまでも田舎には、そのようなコミュニティが色濃く残っている。ただし、そうしたコミュニティが「窮屈」だということも事実だ。
田舎に移住した友人の話を聞くと、村祭りで神楽を踊れるようになって、初めて正式な村のメンバーとして認められるという。ただ、そのためには10年近い年月をかけ、近隣住民との絆を深めていかなければならない。
イノシシがワナにかかったり、シカが交通事故に遭うと住民総出で解体して、肉を分かち合う。私が知人の家を訪ねると、誰にも言っていないにもかかわらず、近隣住民が一升瓶やツマミを持って集まってきて、朝まで宴会になる。
それが、貧しいなかでも豊かな暮らしをするためのひとつの方法であることは事実なのだが、私のような一匹オオカミを自認する生き方とは相容れない。「自由」と「自由を実現するための時間」が奪われてしまうからだ。
おそらく、これからは「クリエイティビティ」を問われる時代がやってくる。定型的な仕事は、AIやロボットがやるようになり、人間に残された仕事はクリエイティビティを問われる“アート”に限られていくからだ。
自分だけの世界を作るアーティストは、孤独にならざるを得ない。だから、社会に支えられていることへの感謝の気持ちを持ちながらも、孤独に耐えられる人生を築いていくことが、これからは重要になるのではないだろうか。
●「借り」は必ずしも当事者ではなく、誰かに返せばよい
●感謝の気持ちの表し方は人それぞれでいい
●助けてもらった人にお返しをすると、不必要なつながりが生じてしまう
●コミュニティには「支え合い」と「窮屈」という相反する側面がある
●アーティストとして生きるためには、孤独に耐えられる人生を築くのが重要