※本稿は、吉田裕子『[新版]大人の語彙力が使える順できちんと身につく本』(かんき出版)の一部を再編集したものです。

話し言葉と書き言葉は語彙の水準が違う
面と向かって「厳寒の候、○○さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」と言われたら、驚きますね。しかしこうした表現は、文書や手紙の書き出しには当たり前に使われます。話し言葉と書き言葉は、語彙の水準が違うのです。
本記事では、とくに書き言葉でよく用いる表現をいくつか紹介します。ぜひ参考になさってください。
「ご自愛ください」
自身の健康を気づかうこと
例文 時節柄くれぐれもご自愛ください。
拝啓なら敬具、前略なら草々をセットで使うというように、手紙を書くにあたっては、さまざまなしきたりがあります。時候の挨拶ではじめ、相手の体調を案じる言葉でしめくくるというのも、一つのしきたりです。
そうしたしきたりを守って手紙を書くのは、なかなか骨の折れること。ただ、「顔の見えない相手のことを思いやり、慎重に、心をこめて書く」という、手紙の精神を日常的なメールにも取り入れることで、他の人とは一味違う、上品な文章に仕上げることができます。
たとえば、ビジネスメールであれば、「いつもお世話になっております」ではじめ、「今後ともよろしくお願いいたします」と終わるのが一般的です。そこに、一工夫加えてみてはいかがでしょうか。幾度かやり取りをした、そのしめくくりとなるメールの末尾に、「どうぞご自愛ください」などとひと言添えるだけでも、印象は変わります。ビジネスライクになりがちなメールに、あたたかみが生まれるのです。
「ご自愛ください」というのは、自分自身の体を大切にすることを呼びかける表現です。
手紙でよく使用され、「何とぞご自愛専一になさってください」のような言い方もできます。「専一」は、「他のことを顧みず、そのことを最優先に」という意味の言葉です。
「お体に気をつけて」と伝えるなら、古風で奥ゆかしい言いまわしとして「おいといください」もあります。この「厭う」は、厭な状態を避けられるように、いたわり、気をつけるという動詞です。
寒い時季には、「お風邪など召されませんように」というフレーズもぴったりです。
目上の人への感謝の気持ちを伝える
「厚情」
親切な気持ち、あたたかい思いやり
例文 ご厚情を賜り、感謝の念にたえません。
目上の人から優しく、手厚く支えてもらったことに感謝する言葉です。「(ご)厚意」「(ご)温情」「(ご)高配」「(ご)厚誼」ともいいます。
異動や退職、閉店の挨拶文、あるいは、葬式における遺族の挨拶のような、それまでの長年の感謝を伝える、あらたまった場面で用いられることが多い表現です。「長年の(生前の)ご厚情に感謝申し上げます」のように使います。
日常的な会話の中でお礼を言う際は「あたたかいお言葉、痛み入ります」「いつも支えていただき、御礼申し上げます」のような言い方がなじみます。
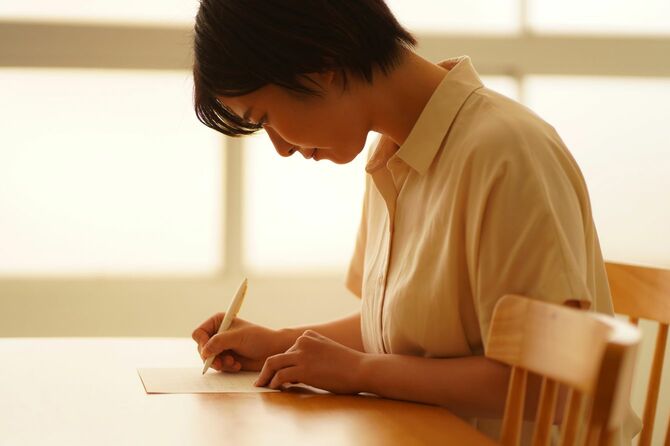
「平素」
普段、いつも
例文 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「普段」という言葉を、丁寧にした表現が「平素」です。
電話や日常的なメールであれば、「いつもお世話になっております」で十分ですが、あらたまった書面や謝罪の手紙などでは、右の例文のように、かたい表現を用いたほうがふさわしいでしょう。なお、例文にある「ご高配」は、相手の気づかいや心配りを敬った表現です。
「平素は」「平素より」と助詞をつけて使用することもあれば、「平素利用している製品」のように、そのまま副詞的に用いることもあります。
同じ意味の語に「平生(読み方に注意)があります。
強めの要求も優しい印象に
「万障お繰り合わせのうえ」
参加できるよう、都合をつけること
例文 ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、お運びください。
トイレに「汚すな!」という貼り紙をすると、わざと汚そうとする厄介な人たちがいるそうです。高圧的・直接的に注意するよりも、「きれいにお使いいただき、ありがとうございます」といった貼り紙をしたほうが、効果的なのだといいます。
主張の内容自体はもっともであったとしても、言い方次第では反発を招きます。たとえば、重要な会議で、全員に集まってもらわなくてはならない場合でも、「絶対に来るように!」という言い方では、角が立ちかねません。しかし一方で、来てもらわなければ困るという趣旨も伝えなくてはなりません。
そんなときに使えるのが今回のフレーズです。
「万障」とは、万の障り。「障り」は、差し障り、障害のことですから、「万障」で「参加するにあたって差し障りとなるあらゆる事情」という意味です。それを「お繰り合わせ」するというのは、調整して都合をつけるということです。したがって、内容としては「どんなことがあっても、必ず都合をつけて参加せよ」ということで、かなり強めに要求していることになります。
ただ、「万障お繰り合わせのうえ」という言葉が、あまり日常的でない、格式ばった言葉である分、感情的な反発を招きにくいのです。
口頭では「お忙しいかと存じますが、ご調整を賜りますよう、どうかよろしくお願いいたします」のように案内したほうが伝わりやすいでしょう。
なお、誘われた側が「ぜひ行きます」「必ず参加します」ということを伝えるときによく使われるのが、「万難を排してまいります」という言い方です。どんな困難も取り除いて必ず、という強い決意を表しています。
大人の謝罪では「ごめんなさい」を使わない
「寛恕」
心が広く、過ちを許すこと
例文 不行き届きな点もあるかと存じますが、どうかご寛恕くださいませ。
謝るとき、小さな子どもは「ごめんなさい」と言います。
この言葉を漢字変換してみると、「御免なさい」です。「御免」+「なさい(~しなさって)」ですから、実は赦免(=許すこと)を相手に要求している言葉なのです。「許してよ~」と言っているわけですから、あまり反省している感じがしません。そのため、大人の謝罪にはあまり使われないのです。
この「ごめんなさい」というフレーズをかたい言葉にあらためているのが、この「ご寛恕ください」です。寛大な相手の人柄を見込んで、寛容に、恕してくれるよう頼んでいるのです。なお、「恕」は『論語』のキーワードの一つで、「思いやり」や「相手に同情する姿勢」を意味しています。
したがって、相手の寛容さや思いやりに甘えようとしており、言っていることは結局、「ごめんなさい」と同じようなものなのですが、格式ばった表現である分、真摯に反省して詫びる態度をにじませることが可能です。会話でよく聞く「ご容赦ください」も同じ発想ですが、「ご寛恕ください」は、これを一段階あらたまった表現にした、書き言葉向きのフレーズであるといえるでしょう。
さらに一段階あらたまった表現で、口頭ではほぼ通じそうにないのが「ご海容ください」です。「海のように広い心でお許しください」と頼んでいるわけですね。相手の優しさを立ててから謝ることで、どうにか許してもらおうとしているのです。
また、和語の表現としては、見逃してもらうよう頼む「お目こぼしください」があります。
このように丁寧な書き言葉は特にビジネスシーンなどで役立ちます。上手に使いこなすことができれば、語彙力のある知的な大人の印象を与えることができるでしょう。

![『[新版]大人の語彙力が使える順できちんと身につく本』(かんき出版)。12万部のベストセラー『大人の語彙力が使える順できちんと身につく本』を時代に合わせてアップデートし、より読みやすくなるよう再編集](/mwimgs/4/6/200/img_46eb26697cdb36ac5477e15281c780e7290641.jpg)