※本記事の情報は取材時のものです。

「障害のある子」だけ預かる里親になったワケ
閑静な住宅街の一角にある、二階建ての一軒家。可憐な花に彩られた玄関周り、あたたかな雰囲気が漂う「坂本」と表札がかかるこの家には、「坂本」と異なる姓を持つ子どもが5人暮らしている。ここ「坂本ファミリーホーム」は、何らかの事情で親と暮らせない子どもが、里親に育まれながら成長していく場所だ。
※「ファミリーホーム」とは2009年に創設された制度で、養育者の住居で5〜6人の里子を育てる、里親を大きくしたようなもの
私にとっては3年ぶり、そしておそらく6回目となる来訪だった。里親の坂本洋子さん(67歳)が、明るい笑顔で迎えてくれる。リビングには家族旅行の集合写真や、それぞれの子の七五三や卒業式などの写真、子どもたちの作品が壁に飾られ、足を踏み入れただけで、愛情に満ち溢れた、あたたかな雰囲気を肌で感じた。
小柄ながら、いつもパワフルな“みんなのお母さん”である坂本さんは40年前から「養育里親」として、19人の里子を育て、今はかつての里子であり、自ら「養育里親」となった歩くん(29歳)と共に、里子たちの養育にあたっている。
今や全国にさまざまな里親がいるが、坂本さんは30年ほど前からあえて、障害などハンデを持つ子どもだけを里子に迎えるという、養育里親の中でも稀有な里親となっている。現に坂本家の里子たちは皆、聴覚障害や知的障害、緘黙、自閉症スペクトラムなど、何らかの障害を持っている。
無論、初めから「障害のある子だけ」を預かっていたわけではない。坂本さんにこう決意させたのには、初めて預かった里子、純平くん(仮名)の存在があった。
不妊治療の後、里親へ
坂本さんは、世間体や体面を非常に気にする厳しい両親の下に育ち、最初は、福祉系大学への進学を親に反対されたことで断念し、短大へ進んだという。親が反対したのは、有名大学でなければ、大学名を周囲に聞かれたときに恥ずかしいという理由だったそうだ。しかし、その後、1年間、念願の福祉関係の学校に通い、子どもの社会福祉を専攻した。もともと坂本さんは子どもが好きで、障害のある子に寄り添いたいという思いを10代から抱いていたのだという。
23歳で、教育系の職場で働く夫と結婚。婚姻時に、「もし、子どもが授からなかったら、里子を育てよう」と夫婦間で決めていた。
「私、昔からどんな子とも仲良くなれる自信があったの。なかなか妊娠しなくて不妊治療もしたけれど、自分の子どもを持てないと分かったら、里親にあっさり切り替えられた。これは、神様が私に里親をやりなさいと言っているんだなと。与えられた宿命というか、背中を押されているとはっきりとわかったの」(坂本さん、以下同)
夫婦で居住地である東京都の窓口に出向き、里親希望を伝えたところ、「養子縁組里親」か「養育里親」の選択が必要ということで、坂本さんは迷わず、「養育里親」を選んだ。
「家に跡取りが必要なわけでもなく、縁組をする気もなかったので、養育里親で行こうと即決。養子縁組里親は、なかなか子どもが来なくて、1年以上待つこともあると聞いたので、それなら早く子どもを預かってあげたいと思ったの。本当の親と暮らせるなら、それが一番だから、それまで大事に預かろうって。住居や経済力などさまざまな面での調査があったり、夫婦で講習を受けたりして、ようやく、里親として認められたの」
3歳の男の子は、担当の保母さんにしがみついていた
1985年、坂本さんが27歳の時だった。
2カ月後に児童相談所の担当者から、乳児院にいる3歳の男児はどうかと打診があり、夫婦で乳児院に面会に行った。
「お母さんが養育できなかった子とだけ、聞きました。初対面では、担当の保母さんにしがみついて、私たちには寄ってこなくて。子どもって、違う環境に置かれるってわかるんですよね。なかなか距離が詰められず、何回も通いました。それが、だんだん近寄ってくれるようになり、家にも何回かお泊まりをして、児相もこれなら大丈夫と判断したタイミングで、最初の里子を迎えました。その日のこと、今でもとてもよく覚えています」
3歳の男の子の手をひき、その身体を抱いた時、ワッと実感が湧いて、重い責任に押しつぶされそうになった。
「私、本当に最後まで、この子を育てられるのかという不安が実感として押し寄せました。初めての育児で突然、3歳の子と一緒に暮らすわけですから」
だが、初めての育児に待っていたのは、子どもと暮らす楽しさだった。公園で一緒に遊び、天気がいい日にはお弁当を作って川原に行った。どれも、全てが楽しかった。
乳児院での経験しかない純平くんは、よく坂本さんを驚かせたという。
「鯉のぼりをえらく怖がるものだから、なぜ? と聞くと『あんなところにいたら、あの鯉、お空の天井にぶつかっちゃうよ』と言ったり、バスのアナウンスが流れると不思議そうにスピーカーを見て『あんな狭いところに、人が入ってるんだね』と言ったりね。社会経験がとても少なかったので、彼にとっては全てが新鮮に映ったみたいです。そして、そうやって彼の言うことが、私にはものすごく新鮮だった。本当に、全てが面白かったんです」
乳児院と社会のギャップが「問題行動」に…
もちろん初めての育児が全て順調に進んだわけではない。純平くんには、問題行動もかなりあった。
「人の家に遊びに行ったら、勝手に冷蔵庫を開けるし、欲しいものがあれば持って帰って来ちゃう。初対面の人のバッグを開けちゃうなんてこともしょっちゅうで。あるものを取り合って、自分のものにする乳児院の世界から、なかなか抜け出せない。でも、当たり前ですよね。それが、生まれ落ちた時からの環境なんだもの。私たちにはあり得ないことが、彼らにとっては普通のことだった。だから、ちゃんとしなければいけないとそのあたりは何度も厳しく教えました」
乳児院に限らず、児童養護施設で育つ子は、家庭で育つ同世代の子と比べて、経験が圧倒的に足りないという指摘がある。また、乳児院では、子供の「愛着」を形成することも簡単ではない。「愛着」とは、養育者と赤ちゃんの間に築かれる絆のようなもの。例えばハイハイをした赤ちゃんが急に不安になっても、母親のあたたかな膝を思い出せば、不安を鎮め、大きな混乱をきたすことはない。愛着があれば世界を広げることができ、安定した対人関係を築いていくことができるといわれる。
一方、虐待などで愛着をもらえなかった子どもはさまざまな問題行動を引き起こす傾向があり、それは「愛着障害」と呼ばれる。他人のバッグを勝手に開けたり、他人の靴下を履いて帰ってきたりする行為は、人との距離がわからないという愛着障害が引き起こす行動とも言える。それにより対人関係に支障をきたす、衝動を抑えるストッパーを持たないなど、愛着を獲得できなかった子どもは、その後の人生でも生きづらさを抱えて生きていくことになるのだ。
「この子は里子と言いましょう」が招いた悲劇
純平くんにも、その要素がなかったとは言い難い。それでも坂本夫妻は精一杯の愛情と時間を注ぎ、純平くんの「妹が欲しい」という願いにも応え、3歳下の友紀ちゃん(仮名)を里子に迎えて、一家4人、幸せな日々を過ごしていた。
「いろんなイベントをやったり、森に出かけたり、旅行に行ったりね。純平も友紀も自分だけのお父さんとお母さんがいる生活は、幸せだったと思うし、私たちもそれがつづくことを望んでいた」
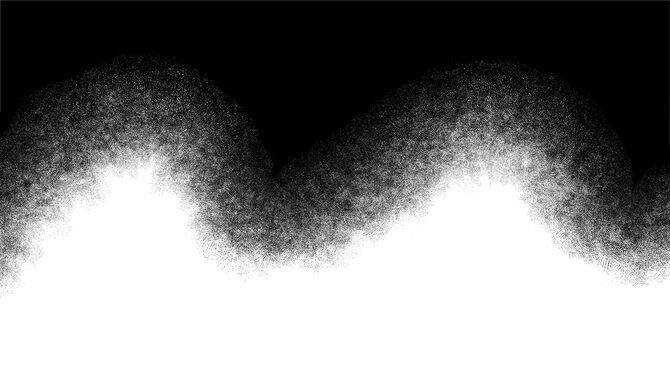
しかし、一歩家の外に出ると、そのような和やかな世界はなかった。純平くんには多動の傾向もあり、幼稚園の頃から「変な子」と言われ周囲から浮いていた。それでも友達と遊んでから帰宅するなど、交友関係を広げていた純平くんだったが、進学した小学校で、担任が坂本さんに提案したことが、坂本家を窮地に追い込むことになる。
「この子は里子だと言って周囲からの理解を深めることで、みなさんに協力していただきましょう」
学校の先生がそんなに親身に考えてくれるなら……と従い行ったカミングアウトが致命的だったと坂本さんは語る。
「そこから、親たちからの差別、区別が一斉に始まってすごかった。直接会ったときには『あなた、偉いわね。立派なことなさって』と言っておきながら、裏では全然違うようなことを言っているのを聞く。人間って、表と裏でこんなに違うんだということを、このときに、私は初めて知ったんです」
「うちの娘があんたの子と何かあったらどうすんの?」
それからは、学校で純平くんと同級生が「遊ぼう」と約束して来ても、必ず、親から断りの電話が入るようになった。遊ぶのを楽しみに帰宅した小学生の男の子にとって、それはどれほどつらいことだったか。近所に住む専門職の母親が、突然電話をしてきて「うちの娘に近づかせないで。うちの娘があんたの子と将来、何かあったらどうすんの?」と言われたこともある。当時小学2年生のかわいい息子へのあまりの言葉に坂本さんは、言葉を失った。
そこで、坂本さんは学校にも親にも、里親制度のことを説明し続けた。このままじゃいけないと思ったのだ。純平くんたちは、社会で育て、守っていかなければいけない子供なのだと。
「純平と妹、この子たちを守れるのは私しかいないと思って。世の中の人に、里親制度を正しく受け止めてもらおうと話し続けました。子供のせいじゃないのに、差別はおかしいだろうと。だけど当時、里親なんて本当に珍しかったからか、誰一人、聞く耳を持つ人はいなかった」
最後の夜に純平くんが言ったこと
純平くんは次第に、学校へ行けなくなっていった。児相に状況を改善するためのアドバイスを求めたが、児相の結論は、純平くんを坂本家から引き上げることだった。引き上げられた里子は、そのあと一時保護所で過ごし、児童養護施設へ再入所することになる。
「やっとやっと、人生で初めて、みんなと同じ家庭を得たのに。子どもの立場からすれば、こんなに残酷なことはない。彼は、最後まで『この家にずっといたい』と言い続けていました。わたしもふくめ、みんな『子どものために』と話し合い判断するけれど、子ども本人の意思が尊重されることは多くなく、大人に振り回されてしまう」
家族で過ごす最後の夜、4人で外食をした後に車で家へ向かっていると、純平くんが「ぼくの学校を通って」と、父にお願いしたという。学校に着くと「お父さん、ゆっくり走って」と。
「あたりを見渡すと、校庭も校舎も真っ暗で。周囲には住宅が並び、その窓から煌々とした明かりが漏れ出している。それを見て、ああ、絶対に子どもを取り上げられない、家庭の光がこれだけあるのにって……。何で私たちは、離れなきゃいけないんだろうって。悔しくて、悔しくて」
学校を通り過ぎて、純平くんは静かにこう言った。
「お父さん、お母さん、ありがとう」
坂本さんは帰宅後、純平くんに1本のぶどうの木とその枝を描いた紙を見せて話をした。
「この枝はお父さんとお母さん、これは妹の友紀ちゃんで、これはあなたね。どこへ行こうと、みんな、この葡萄の木のように繋がっているんだからね」
翌朝、純平くんはその絵を持って、坂本家を出た。
「今振り返っても、気の毒すぎた。彼は小さいのに全部わかって受け入れて、御礼まで言って出て行って……。友紀も大好きなお兄ちゃんが急に連れられていっただけでなく、自分もそうなるかもと不安そうでした」
それからも、純平くんは時々、施設を抜け出してはこっそり坂本家にやってきて、一言の手紙が置いてあるなど、小さい目印をつけていったので、そのたびに「純平が来ていたのかな?」と坂本さんたちは話したという。夏休みの長期外出では坂本さんたちと旅行にも行った。そして中学卒業と同時に、純平くんは施設を出た。当時、施設の子たちは中卒で働く人も多く、今のように、その先の支援などはほとんど整えられていなかった。
「最後に純平が来たときは、お給料で買ったって発泡スチロールの箱いっぱいの魚介を持ってきてくれて。私が魚介を好きと知っていたので『お母さん、食べろ』って置いて行ってね……」
あまりにも短かった17年の命
その夏、里子たちとの海外旅行から帰ってきた坂本家のFAXには、溢れんばかりの大量の紙が渦巻いていた。何事かと手繰り寄せたFAXには、信じられないことが書かれていた。
「純平くんがバイク事故で、亡くなりました」
17歳で、帰らぬ人となった純平くん。あまりにも短い人生だった。生前、純平くんが坂本さんに書いた手紙に、こんなことが書かれていたという。
「もう生きるのを、やめようかと思ったけど、この家があるから、生きることに決めたんだ」
純平くんの死は、坂本さんにとって受け入れ難いことだった。
「彼の人生に、生まれてきていいことってあったの? 幸せなことは、あったの? って。親がない子どもっていうのは、こんな残酷なことになるんだって」
ただただ、悔しく、涙が止まらなかった。初めての大事な里子、かけがえのない子だった。
「魚を置いて行って、すぐに電話もくれたんだよ、『お母さん、食べたか?』って。今置いて出て行ったばっかりなのに、そんなに早く食べられるわけないでしょう? って笑ったよね。優しい子でした」
思えば、今でも涙が込み上げる。純平、あなたは私に会ってよかったの? 人生で幸せと思えたときはあった? それを知ることもできないまま、純平くんは星になった。
(後編へつづく)
