※本稿は、このテーマをより深く理解するために性にまつわる具体的な生物学的記述が含まれています。宮﨑浩一、西岡真由美『男性の性暴力被害』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

男性への性加害でも「性的快感」が暴力の手段となる
「性」を手段にした暴力を受けると、身体にも心にも深い傷がつくことがあります。性的なことは、明確な輪郭があって目に見えることばかりではないので、ある意味非常に曖昧でもあります。それは、性的な事柄というのは個人の感覚によって性的であるかどうかが決まるからです。だから、人がどう言おうとも、自分が性的に不快だと感じることは、勝手にされてよいものではありません。その性的な感覚を侵害する行為が性暴力であり、その結果として男性に特徴的な問題を生じさせることがあります。
性的な感覚の一つとして、性的快感があります。好きな人とのスキンシップで満たされながら感じることもありますが、この性的快感も暴力の手段として使われます。
性的快感は親密な関係で大切に育まれて感じるものと、反射的に身体が反応して感じるものとに分けて考えられます。暴力の手段として使われる性的快感は、反射的な身体の反応を利用していると言うことができます。この反射的な快感が生じる部分が生殖器の、特に陰茎(ペニス)亀頭部や陰核(クリトリス)です。
性行為を望んでいなくても生殖器の一部は反応する
ヒトは同じ細胞から精子を作る個体であるオスと、卵子を作る個体であるメスとに分化していきます。たくさんの神経組織が集まっている性器の、特に陰茎や陰核は刺激を受けることで反応し、快感が起きるように作られています。このような身体的な反射で起きる快感は、相手との関係性やその行為を望んでいたかどうかといった意思とは関係なく起きます。そのため、とても不快で嫌悪を感じている状況でも、起き得ることです。
こういった身体反応は性暴力被害の最中でも起きることがあります。反応してしまったという罪悪感や恥辱感については、そのような感覚を起こさせている加害者に責任を帰する必要があります。私たちは、殴られたときに感じる痛みについて、痛みを感じた自分の責任だと思うことはないと思います。他人が自分を殴ったから痛いのであって、勝手に痛みを感じているのではありません。
同じように、性的快感も、暴力の手段として使われたとき、加害者が自分の性器に刺激を与えたから感じているのであって、それを望んでいたわけでも、喜んでいるわけでもありません。
加害者は加害行為の責任を被害者にも負わせようとする
快感の場合、本来喜ばしい感覚であるはずですから、性暴力被害の最中にその感覚が起きることは、非常に矛盾したものです。この矛盾を作り出すことで、加害者はその加害行為の責任の一端を被害者に押し付けようとしているのです。また、そのような感覚を引き起こすことで、被害者の身体の自由を奪うことに加えて、感覚をも支配しようとしていると言えます。
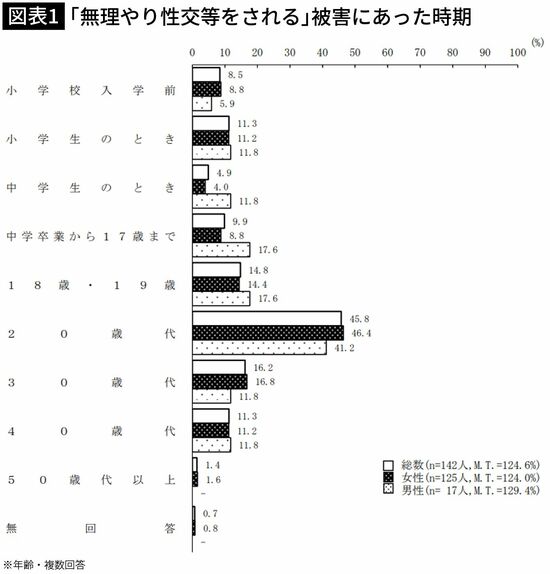
性別にかかわらず性的快感が被害の最中に起きることはありますが、ペニスを持っている人にとっては、それが別の意味を帯びてきます。それは、性的快感を抱いていることが他人から分かりやすいという点と、ペニスが持つ性的能動性という点の二つにあります。ここに、男性の性暴力被害の特殊性が表れてきます。
ペニスが持つ性的能動性ゆえ「本人が望んだ」と思われる
男性外性器は、刺激を受けると勃起や射精が起きます。これは他者から見ても分かりやすい変化のため、そのときに性的快感を抱いていることが簡単に他人にも伝わってしまいます。よく性教育の本では、勃起を起こす理由として性的な刺激が与えられると……と書かれていることが多いため、勃起をしたということに、本人の意思が介在しているように思われるかもしれません。
確かに、エロティックな視覚情報や想像も性的刺激として勃起を引き起こしますが、そのような本人の意識的な関与がなくても、陰茎の触覚が刺激され、それが適度な感覚刺激であるならば、反射的に勃起を引き起こすことがあります。
つまり、性暴力被害の最中に「触られたくない」「気持ち悪い」「怖い」「悲しい」「痛い」といったさまざまな不快な感覚や感情があり、全く望まない状況であると認識していても、性的快感が生まれる可能性があるということです。
実際、男性や男児に対する性暴力において、勃起や射精へと至らせる行為は珍しいことではないと、これまでの研究で明らかになっています。先ほど触れたように、性的快感を暴力の手段として使うことで、加害者は被害を受けた人の感覚をも従属させた気分になれます。
女性ももちろん性的快感を被害の最中に抱いていることがありますが、男性に特徴的なのは、その感覚を勃起や射精という生理的な現象によって簡単に知られてしまうという点にあります。そのときに加害者は「本当は気持ちいいんだろう」「身体は正直だ」などと、あたかも本人がそれを楽しんでいたり望んでいたりしたかのような言動をとることがありますが、これも巧妙な加害者の策略です。
男性が「挿入させられる」という被害は想像されない
そこに被害者も自ら積極的に関与しているかのように思わせて、性を利用した暴力であること、自分の加害行為を隠そうとしているのです。なお、現行法でも勃起や射精が起きたことが、同意を示しているとは考えられていません。
異性間の関係が想定されている性交では、挿入する側として男性が想定されており、挿入される側として女性が想定されています。このことが二つ目の特徴です。この男女間の性関係において、性的能動性は常に男性のペニスに還元されます。
つまり、勃起しているなら、それは挿入したいのだ、射精をしたいのだ、という短絡的な論理です。これは、男性の身体に起きている生理的な仕組みや、感覚、感情、認識といった複雑な関係を度外視して、男性の性をすべてペニスに還元する見方です。
また、「挿入させられる」という被害の形態は想像されません。自らの勃起したペニスを入れたのだから、それは本人がしたかったのだろうという結論になってしまいます。そうすると、男性はペニスを持っているから被害者にはならないということになってしまいます。
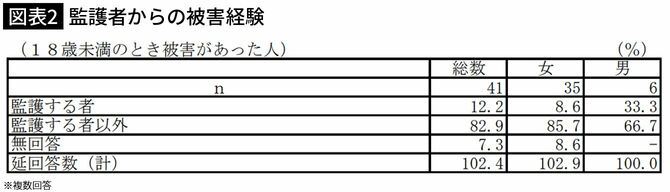
身体反応を利用するから、性暴力は人の統合性を侵害する
繰り返しになりますが、勃起は生理現象であって、本人の意思に反していても反応することがあります。そして、その反応を起こさせているのは、加害者であって被害者ではありません。通常、快感や安心感といった好ましい感情は、その出来事と感覚が一致しています。暑い日に水を飲んだときの美味しく感じる爽やかな感覚、疲れて眠るときのベッドの気持ちよさといった具合に、状況は感覚と一致して経験されることが多いです。
性暴力が人の統合性を侵害し、支配するというのは、この点からも言えます。不快な状況、逃れられない状況において加害者は被害者の身体反応を利用して、快楽を生じさせています。快楽ならばいくらあってもよいと思うかもしれませんが、それは出来事の評価と一致している場合に限ります。
男性のレイプ神話には、「男は性暴力被害に遭わない」という誤った考えがあります。これは、ペニスに男性性を象徴させて、挿入できる(そして、挿入される穴はない)能動的な存在として男性一般を見なすことで作られています。あえて問題化しなければ気づけないほどに、男性の性はペニスに還元されています。このような象徴性は現実に流布されています。
「自分は求めていたのか」という被害者の混乱
これほど一般的とも言える考え方は、男性被害者も持っています。勃起し、射精したということは、この状態は私が求めていたものだったからかと混乱が生じることがあります。
外性器の勃起や射精は、反射的な反応です。しかし、その反応についての説明は基本的に性的快感と結びついて理解されています。実際、望んでいない状況であったり、恐怖など不快な感情を抱いていたりするときでも、射精に至る過程で少なからず性的な快感は生じます。そのために、加害者の行為によってもたらされる被害状況の内的な経験と、身体反応から生じる感覚(これも内的な経験です)の間に断絶があります。これは加害行為の結末です。ですが、当事者がそのように考えることはなかなか難しいものです。
「男らしさ」の規範があるから、男性のレイプ神話が生まれた
男性性の混乱とは、「当該文化における規範的男性像と一致していないことや、被害者自身が抱くジェンダー・アイデンティティが不安定な状態を表現しているものである」と説明できます。
規範的男性像とは、いわゆる「男らしさ」のような、男性が期待されている振る舞いのことを言います。男性のレイプ神話は規範的男性像を表したものだということができます。男性は「肉体的に強い」「異性愛」「精神的に強い」「挿入されない」「ホモフォビア」「性的に能動」といったルールを表し、レイプ神話では男性の性暴力被害をそれに沿わない劣った男の事象として否定しようとします。
規範的男性像は、素朴な基準として一般に浸透しています。当たり前のこととして社会にあるということは、男性の被害者にも男性性のルールが染み付いているということです。それによって、個別的な性暴力被害体験と男性規範のルールとの間に矛盾が起きてしまいます。この矛盾状態では自分自身に起きたことが、本当に性暴力被害と言えるものなのか疑いを感じたり、自分の性的なアイデンティティが揺らいでしまったりすることがあります。このような状態を「男性性の混乱」と言います。
例えば、ある調査では一部の男性被害者は、被害体験中の自身の性的反応について混乱や嫌悪を表現していると述べ、異性愛男性が「もし本当に自分が受けていた性的暴行がそれほど不道徳なものなら、なぜ僕は射精したのか? 長い間、それを楽しんでいたに違いないと思っていて、だから、同性愛の傾向があるに違いないと思っていた。すごく長い間混乱していたんだ」と語ったことが例示されています。
「女の子が好きだったのに変わってしまった」という葛藤も
さらに、「自分は被害のせいで、バイセクシュアルなんじゃないかと思った」「混乱しているように感じる。たぶん、自分はあのことがあったからバイセクシュアルなんじゃないかと思う。今でもすごく女性に惹かれるけれど」と語っている被害者の例もあります。
日本においても、「女の子が好きな普通の男だったのに。あのことで自分は変わってしまった。自分からホモになりたくてなったんじゃない」という男性被害者の葛藤が記されています。
加害行為を男性が受けると、セクシュアリティや性行動に影響が及ぶと報告されており、この影響はジェンダー化された存在としての自己のセクシュアリティをどのように捉えるかという点や、性的なアイデンティティをどのように構成し維持するかという点と関連することが示唆されています。

