91歳で新雑誌を創刊
緑あふれる東京・広尾の一角に、日本赤十字看護大学のキャンパスがある。1890年に日本赤十字社病院で看護婦の養成が始まり、1945年の敗戦翌年には「日本赤十字女子専門学校」が設立された。さらに短大から4年制大学へと、130年余にわたり看護教育が受け継がれてきた。

そんな日本赤十字看護大学で今も名誉教授として活躍する川嶋みどりさん(92歳)は、まさに戦後の看護の歴史とともに歩んできた一人だ。看護界の重鎮として後進の教育に尽力し、昨年には91歳にして『オン・ナーシング』という新雑誌も創刊。今なお看護の在り方を追求し続けるフロントランナーである。
川嶋さんがかつて教員だったころは、学生からよく「なぜ、60年以上も看護師を続けてきたんですか?」と聞かれたそうだ。その度に、決まってこう答えていたという。
「それはね、看護大好きだから。このままではいけないっていう思いが強くって、もっとよくしていかなければと思っていたら、とうとう今日まで来ちゃったの……」
ずっと、勉強がしたかった
看護の道を選んだのは「もっと勉強がしたかったから」と、川嶋さんは子供時代を顧みる。
川嶋さんが生まれたのは1931年、満州事変の始まった年に。朝鮮京城(現在の韓国ソウル)で誕生した。銀行員だった父の転勤に伴って、幼少期~15歳になるまでは韓国、中国各地の小学校、女学校へと転々と転校を繰り返した。女学校の前半は、戦争の学徒動員で作業に明け暮れる日々だったという。
終戦を迎えた1945年、一家は引き揚げ船で父の故郷である島根県へ。仕事も食べ物もない中、両親は慣れない農業を始めたが、なかなかうまくはいかない。6人きょうだいの長女だった川嶋さんは苦労する両親の姿を目にして、どうしても進学の願いを口に出せなかった。そんなとき女学校の保健教諭から、学費もほとんどかからず資格を取得できる道があると聞き、同じ悩みを抱える友人と共に大喜びで受験したのが、日本赤十字女子専門学校(日赤女専)だった。
「寮生活は規則が厳しく、先輩への礼儀や言葉遣いをみっちり鍛えられました。食糧難でいつも空腹を抱えており、暖房もなかったので寒さが体にこたえました。そのような環境に耐えられないと半数が荷物をまとめて出ていったので、40人が入学して卒業まで残った同級生は26人。でも、私は勉強できるのがうれしくて。それに戦後すぐの女学校は封建的な学風で、自由な言論が許されず窮屈でした。そっちでの生活の方がつらかったので、赤十字での寮生活を私はあんまり苦には感じなかったの」
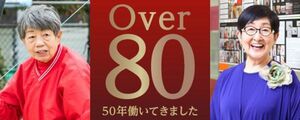
敗戦で物資が極度に不足していた当時、乏しい医療材料を工夫して使うしかない看護師たちの仕事は想像以上の過酷さだった。寮生活をする学生も朝5時半には起床、毎朝7時に病棟へ実習に行き、授業と実習を挟みながら一日8時間以上は学ぶ日々。2年生になり夜勤実習がスタートすると、夜勤は1週間ぶっ通し。人手不足から学生でも病棟を一人で任されるなど、学生気分ではいられない緊張感のある日々だった。
「学生気分ではいられない日々の中、私たち学生はすごく背伸びをしていたと思います。しんどいときには、とにかく看護婦は尊い仕事、専門職なのだと、常に自分に言い聞かせていました。でも、私の本音では“そうかな、本当にそうなのかな……?”という疑問もずっとあったんです。実感がなかったんですね。卒業式では答辞を読まされたときなどは、立派なことを書いていたけれど、心の底からそう思っていたわけではない気がします。私が本当に看護の力を知ったのは、トシエちゃんという女の子を看護したときでした」
原点となった少女との出会い
卒業後、日赤病院で小児病棟を志願した川嶋さんは、12人の子どもがいる部屋に配属された。トシエちゃんと出会ったのは、働き始めて9日目のこと。脊髄の悪性腫瘍で地方の病院から転院してくる9歳の少女がいると聞いていた。
玄関へ迎えに行くと、その子は赤ちゃんのようにおくるみにくるまって母親に抱かれていた。ストレッチャーに乗せて病室へ運び、寝間着に着替えさせようとおくるみを取ると、体はやせ細って、土気色の顔は皺だらけ、まるで老婆のように見えた。背中には大きな腫瘍があり、仰向けに寝かせることもできなかった。
「今にも死にそうな末期の状態で、トシエちゃんは『痛いよう』『だるいよう』と、かぼそい声でうめいていました。どうしていいかわからず、足をさすってあげたら、その感触が魚のうろこのようにザラザラと硬くなっていて……。驚いておそるおそる毛布をはがしたら、垢の層がびっしりと足をおおっていました。何ともいえない悪臭が鼻をつきましたね」
手術を求めて病院を転々としている間、お風呂に入ることも、身体を拭いてもらえることもなかったことが分かった。そこで、まず川嶋さんはトシエちゃんの身体をきれいにしようと決めた。
「新人でしたが、ベッドでの全身清拭は実習で幾度も経験していましたし、これならお手のものだと。すぐにお湯を汲みに行きました」
大匙2杯の卵粥
脈をとると、脈拍が極端に弱く、一度に全身の清拭を強行すれば症状が悪化することは予測できた。そこで初日は足だけを洗うと決め、ぬるい湯に片足ずつ浸して洗っていく。
両足を洗い終えると、石鹸箱ですくえるほどの垢が取れ、まるでソックスを脱がせたように本来の真っ白な足が見えてきた。毎日少しずつ、上半身へと向かって拭いていき、一週間目には背中の腫瘍のまわりもガーゼでそっと拭いた。
「翌朝、最後に顔を拭いて、すっかり全身がきれいになったトシエちゃんに『どう?』と聞くと、ほっぺをピンク色に染めてにっこりと笑い、『看護婦さん、おなかが空いた』と言ったんです。それまでブドウ糖の注射だけで食事もとれていなかったから、その言葉に驚くやら嬉しいやらで。私は配膳室へ飛んでいき、大匙2杯分の卵粥をつくりました。スプーンで口もとに差し出すと、『おいしい!』と言って食べてくれて。その日からトシエちゃんは見違えるように変わっていきました」
数えるのが難しいほど弱かった脈が、通常の強さに戻り、リズミカルに打つようになった。なぜ食欲まで出てきたのかと不思議に思い、医師や婦長に報告したが、そのときの返事は「あっ、そう」と素っ気ないもので答えは得られなかった。当時は看護学の参考書も手に入らず、調べることもできなかったが、トシエちゃんが明るくなったのは明らかで、皆とおしゃべりするほどに元気になった。それから3カ月余り、9歳の女の子らしく生きることができたのだ。
「あの経験が、私自身の目を見開かせてくれました。お湯に浸して絞ったタオルと石鹼で、一時的ではあっても彼女の生きる力を引き出せたのです。身体を少しずつ拭きマッサージすることで、全身の緊張をほぐせたのだと思います。あのとき、もしそのままにしていたら、トシエちゃんの命は数日で尽きていたことでしょう。人間の身体の中には自分で治る力が潜んでいる。自然治癒力を発揮できるように手助けするのが看護なのだと、肌で感じた体験でした」
後に翻訳されたナイチンゲールの『看護の覚え書』の中にも、こう書かれていた。
新人時代に経験したこの出来事が、今日まで看護に携わる礎になっていると、川嶋さんは顧みる。

共働きなんて「お気の毒ね」
看護師として奮闘するなか、さらなる人生の転機が訪れたのは26歳のとき。川嶋さんは、ともに生きる伴侶にめぐり会う。夫になった人は日赤女専時代の同級生の兄で、通産省の地質調査所の研究者だった。川嶋さんの仕事もよく理解してくれ、共働きの結婚生活がスタートした。
「あの頃は結婚したら、仕事を辞めるのが普通の時代。日赤は全寮制なので、結婚して寮を出るときは退職なんですよ。でも、私は看護の仕事が大好きだから、辞めたくなかったの」
両親は辞めるべきだと反対し、同僚には「共働きなんてお気の毒ね」と夫の甲斐性がないかのように見られることもあった。ほとんどが未婚者である職場なので、結婚当初は心ない言葉に傷つくこともしばしばあったが、家で「ちょっと聞いて! どう思う?」と話すと、夫は耳を傾けてくれた。
「夫はワンマンなところもあったけれど、私の仕事をいつも尊重してくれました。『女性の可能性を家事に埋没させてはダメだ。雑用は手の空いている方がすればいいから。そうしないと仕事との両立は長続きしないよ』『僕のお客さんが来ても、お茶を出しちゃいけない。自分でやるからいい』とまで言われて。私はそんな家庭に育っていないから、『そんなのお客さんに私が変に思われるじゃない!』と最初はかなり抵抗しましたけれど(笑)」
家事はそれぞれ得意なことを分担したうえで、できるだけ簡素化するためになるべく電化製品を取り入れて……といろいろ知恵を出し合った。やがて一人目の子を妊娠。産後8週間で職場へ復帰した。
産休明け、病棟から自分の名前が消えていて…
小児看護をライフワークにしたい。そう願っていた川嶋さんだが、産休明けにショックを受ける出来事があった。出勤すると小児病棟のスタッフ名簿から自分の名前が消えていたのだ。
その足で上司の元に行き、小児病棟で働き続けたいと懇願したが、配置転換を命じられたのは耳鼻咽喉科外来だった。
「夜勤のある病棟勤務は無理と判断されたのかなと。産休に入る前日まで夜勤もしていたのにと、悔しかったですね」
この出来事もあり、仕事と子育てを両立する大変さも実感していくなか、川嶋さんの胸中では「働き方改革」への意識が芽生えていく(後編へつづく)。
