※本稿は、永田希『再読だけが創造的な読書術である』(筑摩書房)の一部を再編集したものです。
本を読むのは億劫だし、文章を理解するのも困難だ
読書には二種類の困難があります。ひとつは、直感的なものです。本を手にとるのが億劫であったり、読み始めたり読み続けたりするのが億劫であったり、読み終えたくないと思ったり、誰とも解釈を共有できないかもしれないと感じる困難です。

読書にまつわる困難は、読み始めない自由、途中で読むのをやめる自由によってその都度は回避可能です。その自由を自覚し、読むのかどうか躊躇することを肯定することが肝心です。その躊躇に慣れることで、やがて読書に対する気負いや気まずさは薄れ、以前よりは読めるようになるものです。
問題はもうひとつのほうの困難、わたしが「複雑な困難」と呼んできたものです。パズルのように意図的に読み解きにくく書いてあったり、その文章を読むために求められる前提知識が際限なく求められたり、客観的な批判を保留して「信じる」ことを求められたりするような書物です。これもまた読まない自由を読者に許す困難ではありますが、単に繰り返し読むだけでは何度読み直しても腑に落ちない厄介さがあります。
再読すると、それまでに経験したことで感じ方も変わる
再読――つまり書物を繰り返し読むと、最初に読んだとき(あるいは何度目かに読み返したとき)と次に読むときのあいだに、ほかのことを読者が経験する時間がさしはさまれることになります。ほかの本を読んで知識を得たり考え方が変わるということでもいいでしょうし、体調が変わるだとか、住んでいる地域の季節が変わるだとか、学校や勤め先の環境が変わるということもあるでしょう。人間関係で新しい友人知人ができたり、あるいは関係が悪化したり、誰かを亡くしたりする経験もあります。
そういった経験がさしはさまれることで読者自身が変化して、それからかつて読んだ本を読み返すとき、人間の基本機能である「自分に都合の良いことだけを読み取る」が働いたとしても、かつてとは自分の状況が変化しているので、以前には気づかなかった部分に意識がつけられる可能性があります。
読書や再読を繰り返すうちに、自分の読み取れる内容が変化することにも繰り返し気づかされるようになります。読書に慣れ、再読に慣れるとは、書かれていることが変わっていないのに、読むたびに読みとられる内容が変化することを知るということでもあるのです。
読書を繰り返せば「読み取り困難な記述」にも慣れる
かつて読んで意味不明だった部分について、前よりもわかるような気がする場合にかぎらず、以前にわかったつもりになっていた部分がわからなくなってしまう場合もあります。
ここで自分の頭が悪くなったのだと考えるのは、ときには正しい場合もあるかもしれませんが、ひとつにはかつてわかったつもりになっていた部分について解像度が高まった結果として理解困難な部分に気づけるようになったのかもしれません。初読時に「簡単なこと」として読み飛ばしていた箇所について、より精確に近い読みかたができるようになったということです。
読書に対する躊躇が正当であることを自覚し、好きなときに好きなだけ好きな本を読めるようになるのには、そのタイミングをからだで覚えるまで読み捨てを繰り返す必要があります。そしてその自由を実感できるようになるまで読み捨てに慣れたとしても、読み取るのが困難な記述に直面することは珍しくありません。読書を繰り返すうちに、やがてこの読み取り困難な記述にも慣れてきます。どうせ困難なのだから今回は読み飛ばそうと決めるのも、今回は腰を据えて噛み締めてみようと決めるのもまた読者の自由です。
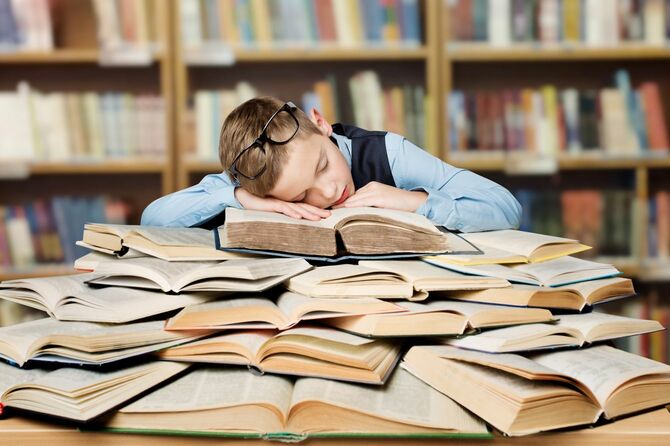
意味を理解するのに困難を感じる記述に出会ったときに、その意味を深く考えずに保留して先を読み進むこと、つまり読み飛ばすということと、意味を噛み締めてそれを解きほぐそうと試みることとのあいだには、二者択一ではないグラデーションがあります。どの程度その困難につきあい、どれくらいで困難に付き合うのを諦めるのか。読み取り困難な記述を含む本を読むことに慣れれば慣れるほど、このグラデーションは多様になっていきます。
難しいところはある程度読み飛ばして進めてもいい
繰り返し読むことを前提にした読書であれば、「この困難について考えるのはこれくらいにして、気が向いたらまた読もう」と腹をくくって、ある程度の「読み飛ばし」をすることができます。いつかまた読むリストのようなものをつくって、そこに書名を追加していくのもいいでしょう。どこにひっかかったのか、メモをしておくと再読の際の参考になります。これも面倒な作業なので、ある程度の慣れを得てからのほうがいいと思います。
読書に慣れること、読解困難な記述に慣れることの先には、その「奥」があります。再読するときまで検討を保留する、あるいは再読時に再検討することを残しておくという領域です。意識的に保留するだけではなく、読み解けていないことを自覚していないものもそこに残されていることに、再読時に気づかされることもあるでしょう。
かのプラトンが言った「語りかけるべき人々」とは?
読んでも読んでもそういった「残りの部分がある」と思わせてくれる本があります。汲めども尽きない泉のような、何度でも読める本は「古典」と呼ばれます。ひとは学びを得るためだけに読書をするわけではありませんが、たとえば読み返すたびに異なった教訓を与えてくれる本というのは確かに存在しているのです。
西洋哲学の祖プラトンが「語るべき人々に語り、黙すべき人々には口をつぐむ」言葉として指し示したかったのは、読者が「語るべき人々」になったときにその内容を「語り」、読者がまだ「黙すべき人々」でしかないときには「口をつぐむ」、そんな言葉のことなのかもしれません。

読者が「語るべき人々」であるタイミングになれば、そこに読まれる言葉は読者の心に刻み込まれるかもしれません。その記述が読者を「語るべき人々」として認める資格として、プラトンは「知恵」を要求します。
これは単なるバラバラの知識ではなく、読者に何かの資格を与えるような体系や経験を含むものです。プラトンの言う「魂」には独自の文脈がありますが、そのような知識と経験の体系をもち、しかるべき資格を得たときに言葉が書き込まれるもののことだ、とひとまずは言えるのかもしれません。
既読スルーした表現から再読時に感銘を受けることも
書かれた文章は、誰にでも読むことができます。ただしそこで使われている文字を読む知識や、そこで書かれていることを想像するための経験は必要になります。例えばマルグリット・デュラスの小説『アガタ』の「打ちひしがれたような優しさ」という文字列を見て「打ちひしがれる」という言葉の意味がわからないひとは「誰にでも読める」はずの文章を読むことができません。
そして言葉の定義を知り、その意味をわかったつもりになっていても、「打ちひしがれたような優しさ」の意味はすぐにはわかりません。誰にでも朗らかに優しさを振りまく幸福なひとには、あるいは逆に、誰にも優しくできないようなひとにも、なかなかわからない文章なのです。
それでも初読時に「打ちひしがれたような優しさ」の理解の困難さを無視して読み進めることはできます。少し時間をおいて、もしまた『アガタ』を読み返すことがあったとして、時間をおいているあいだに経験したことや知識を得ることによって、「打ちひしがれたような優しさ」に感銘を受けるようになるかもしれません。
本を手にとる億劫さ、読み始める億劫さに躊躇することに慣れ、また読解困難な記述に慣れて、初めてこの感銘を味わうことができます。
初読でわからなかったことに気がつくために再読が必要
しかしその感銘が、自分勝手な読み取りでしかないという可能性はまだ残っています。もちろん、自分勝手な読み取りをする自由もまた読者には許されています。しかし自分が本当にその記述にとって、プラトンが言う「語るべき人々」になっているのかを判断する方法はありません。
本は繰り返し読めるものなので、ひとたび感銘を受けたと思っていても、また読み返したときにもっと深い、あるいは別の感銘を受ける可能性が常に残されています。前に読んだ時にはわからなかったことに気がつくためには、それを繰り返し読む必要があるのです。そして、繰り返し読むことによって「慣れ」は深められていきます。

「読書に慣れる」というのはどういうことか
読書に慣れることで、繰り返し読むとそのたびに「さらに奥」を見せてくれる本が存在すると知ることになります。「読書に慣れる」ということそのものが、読書の深みを知るごとに深まっていきます。それは他人からは、知識や蘊蓄を増やしているだけに思われるかもしれないし、実際そうでしかないひともいるでしょう。
他人の目にどう映るかはさておいて、自分自身に「果たしてそれだけか」と問いかけたとき、それまでに読んできた文章の書き手たちが「読みとられないかもしれない」と思いつつ書き留めた言葉が自分に確かに響いてきた、自分が「語るべき人々」の資格を得て、言葉に「語り」かけられたと思えるかどうか。そしてその経験を繰り返してきたかということが、慣れを深めてきたかをはかる基準になります。
他人にほめてもらうために読解を深めるわけではない
披露することで他人を驚かせる知識量やマニアックな蘊蓄と違って、「慣れの深み」を味わっていることは他人には伝わりにくいものです。他人に認めてもらい評価されるための読書ではなく、またそのときどきに束の間を忘れるために楽しむ読書でもなく、誰かがわざわざ読みにくさを障壁にして書いた言葉を自分なりに受け止めてきたという積み重ね。それを誰かにわかってもらうためには、わざわざ読み取りにくく書かれていたものを台無しにするリスクをおかして、読みとりにくさも含めて開陳する必要があります。
しかもそのときには、相手が「語るべき人々」の資格を得ていることが条件になります。「わからないひとにはわからない」という当たり前の事実と、「話せばわかる」という希望とが衝突するのです。
より遅くより深く再読すると人生のパズルが解けていく
速く読むことも多く読むことも無意味ではありませんし、知識や蘊蓄を蒐集することにも意味がないわけではありません。しかし、より遅く読み、より深く読むこともまた大切なことなのです。知識は読書以外にももちろん役に立ちますが、ある種のパズルを解くヒントになったり、その知識を前提とした書物を読み解くのに必要になったり、自分とは異なった信念や考え方を持っているひとの言葉を噛み締めるために不可欠なものでもあるのです。
より速く、より多く読む「わかりやすい」読書は初読の機会を増やします。これに対して、より遅く、より深い読書は再読によって可能になるものです。まず読書に慣れ、つぎに再読に慣れることで、読み飛ばしたり読み捨てたりしてきた本からはより豊かな読書を得られるようになります。そして再読への慣れには、際限のない深みがあるのです。

