※本稿は、シャルル・ぺパン(著)永田千奈(翻訳)『フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者』(草思社)の一部を再編集したものです。
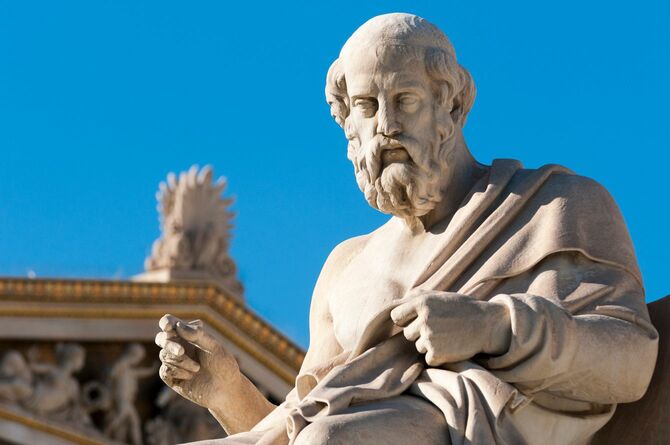
理想の天界を作り出したプラトン
プラトンは「イデア(=理想)の天界」を作り出した。プラトンによると私たちの住むこの世界は本当の世界ではない。「本当の世界」は別のところにある。私たちの頭上、「イデアの天界」には、理想が永遠の輝きを見せているが、地上にいるかぎり、このイデアを完全に自分のものとすることはできない。つまり、ルールは天上にあり、下界に生きる私たちはこのルールを多少なりとも意識しながら生きている。
プラトンの思想はまず、私たちがひとときを生きる「可感界(見たり触ったりできる具象)」と、永遠の命をもつイデアが生きている「可想界(頭のなかにしかない抽象概念)」を区別することから始まる。「可感界」において、人はそれぞれに異なる。大柄な人、小柄な人、臆病な者、勇敢な者、悪人も善人もいる。
だが、イデアの世界における人間の概念は一つしかない。こうあるべき人間というただ一つの理想的な人間像しか存在しないのだ。そして、この抽象的ながらも、明確な理想を基準とすることで、感覚的に生き、具体的なかたちで存在する人間、多様な人間を価値づけることができる。
プラトンは理想主義者
プラトンは天に理想を求める。プラトン哲学が理想主義と言われるのはこのためだ。ニーチェはプラトンを理想主義の創始者と位置づけた。ニーチェによれば、天と地を神と人の領分として区別するキリスト教は、プラトンの思想を借用したものなのである。
「可感界」は多種、多様、偶発性、相対性を特徴とする世界であり、非本質的な世界である。たとえば、それぞれに異なる台がある。応接間の低めのテーブル、背の高いテーブル、美しいテーブル、みすぼらしいテーブル、ナイトテーブル、手術台も広い意味ではテーブルだ。
一方、可想界では、一貫性、必然性、普遍性が価値となる。これこそがプラトンのいう本質的な世界であり、ここでいう概念は本質と言い換えられる。つまり、ここで問題なのはテーブルという概念であり、「物を載せられる平面に脚がついているもの」というテーブルの定義だ。テーブルとは何かを知るために、この世に存在する台状のものをすべて思い浮かべ、その詳細に目をこらす必要はない。ただ「上を見る」、つまり、矛盾するようではあるが、目を閉じ、可感界の煩雑さ、複雑さから遠ざかり、自身のなかに問いかけ、テーブルとは何かを考えてみるのだ。
人が本当に求めているのは真理
さて、次に問題になるのが可感界と可想界の関係だろう。私たちは具象にあふれる下界で、イデアの天界にある価値観に従って生きている。
では、どうやって、自分たちの行動が天界のルールに合致しているか判断すればよいのだろうか。私たちの行動を分析し、その問いに答えられるのは、永遠のイデアを眺めることができる哲学者だけだ。
二つの世界の関係については逆方向からも考えることができる。下界で生きる私たちを永遠のイデアに導く人はいるかということだ。
これについては、プラトンが『饗宴』のなかで答えている。誰よりも美しい肉体がほしいと思いつづけることで、人は美という概念、ついには真理という概念に向かう。
もちろん、経験豊かな哲学者による導きは必要だろう。ほしいのは美しい肉体ではなく、肉体の美しさであることに気づいたら、第一段階は完了だ。さらに、その美しさが均衡の真理にあると気づいたら第二段階も達成される。
つまり、人が本当に求めているのは、単なる個人的な身体の美しさではなく、真理なのだ。こうしていくつかの段階を経ることで、人間はイデアの天界に向かって昇っていく。
ただし、この考え方は民主的とは言えない。知恵の人に導かれ、一部のエリートだけが真理に到達できるとプラトンは考えていた。
ニーチェによると、キリスト教はこれを民主化し、誰でも天国に行けるとすることでプラトン主義を俗化させた。哲学者の役割を教会が担い、「人民のためのプラトン主義」をつくったのだとニーチェは説明している。
このイデアの天界という基本概念は、認識論、政治論、社会論、美学に至るまですべてのプラトン哲学を貫くものであり、この基本を理解することで彼の思想全体が見渡せる。
空を見上げる才能こそが哲学だという哲学の定義そのものがそこにかかわっているのだ。そして、空を見上げる賢者の純粋なまなざしに比べると、人の行為は価値が低いものとなる。

「肉体は死ぬべし」
「哲学とは死に方を学ぶことだ」という、モンテーニュが引いたプラトンの言葉は意外に思われるかもしれないが、こうして考えると腑に落ちる。「可感界」の生活は早々に終わらせるべきものであり、多様性のなかにある非本質的な肉体は死んでしかるべきなのだ。賢人は、永遠という視点からものごとを見なければいけない。
知識について、プラトンは実に独創的で驚くべき仮説を披露している。それによると、あらゆる知識は遠くの人生から突然湧き出てくる記憶であり、再認識であるというのだ。これが、プラトンが『メノン』で説明している「アナムネーシス(想起)」というものである。
「肉体は魂の墓場」
つまり、生まれる前、現在保有している肉体、空間的にも時間的にも限定された肉体に「劣化」する以前、人間はイデアの天界に暮らしており、死ぬとまた空に戻る。誕生するまで、人は永遠の真理という「産湯」に浸されていた。まるで突然光が射すように何かを理解するのは、誕生前に触れていた真理を「想起する」からなのだ。
よって、知ることは常に思い起こすことであり、記憶を呼び覚ますことなのだ。知識はアナムネーシスなのである。
こうして、プラトンは「明証(エビデンス)」を説明しようとする。私たちが「明証(エビデンスの語源はラテン語のvideo=見るである)」のなかに見ているのは、下界の肉体に閉じ込められる以前、天界にいた頃に慣れ親しんだ概念のほうなのだ。
よって、プラトンにとって死は悪ではない。狭く、重く、不器用な肉体という檻から解放され、永遠の真理に回帰することなのだ。
「哲学とは死に方を学ぶことだ」というのは、死によって肉体の限界から解放されるのを待つまでもなく、思考によって永遠のイデアに到達せよという意味である。ギリシャ語で肉体は〈soma〉だが、墓は〈sema〉である。プラトンにしてみれば、肉体は魂の墓場なのだろう。といってもこの肉体という墓は一時的なものでしかない。死は魂を肉体から解放してくれる。
哲学者を王に、という考え方
政治に関して言えば、プラトンは民主主義に対して非常に厳しい目を向けており、特に『国家』では民主主義への批判が顕著である。ただし、ここで彼が批判しているのは、当時誕生したばかりの古代ギリシャの民主制であり、ここでも「イデアの天界」の原理をあてはめたうえでの批判である。
彼によると、民主制は、人々が無自覚のまま権力を手にし、人民、正義、善などの本質についてイデアを仰ごうともせず、無知のまま政権を担うことを意味する。
つまり、情動の政治であって、理性の政治ではない。国を治める方法など学んだことのない人民たちが、これまで政権の座にあった貴族への憎悪を原動力として、不公平な政治を執り行なう危険がある。
だが、これまで高い地位にあった特権階級は不当な政治を甘受しようとはしないだろう。そこで、民主制はやがて独裁に陥る。
こうして、プラトンは『国家』で「哲学者を王にする」必要性を訴え、書簡集第七巻でも同様の主張をしている。正義や徳といったイデアに基づき都市を治めるため、為政者は天界のイデアを見ることができる人物であらねばならないというわけだ。天の法則によって導かれた者こそが国を導くことができるとプラトンは考えた。
「幻想を退け、真理をとらえよ」
次は芸術論である。プラトンは「都市から詩人を追放せよ」と言い放った。
『国家』第十巻で、彼は寝台を写実的に描いた絵とイデアの寝台とを比較している。寝台を描いた絵画は、現実の寝台よりもさらにイデアの寝台から遠いものであるという。現実の寝台には少なくとも機能がある。上で寝ることができる。「真理から一段階遠いもの」つまり、理想の寝台という概念から一段階遠いものということだ。真理ではないが、実用性はある。実用に耐える寝台を造らねばならない以上、職人もある程度は、寝台の本質に忠実であろうとするだろう。
だが、芸術家が寝台の絵を描く場合は違う。彼らは、一つの角度、一つの色彩に固定された特定の寝台を思うがままに描く。よって、芸術は、「真理から二段階遠いもの」となる。描かれた寝台は、寝台の本質から乖離しているうえに、実用性もない。芸術家は真理を尊重しないし、その作品には必然性もない。芸術家には、ある種の「気まぐれ」が許されており、彼らは傍若無人にふるまう権利、似非自由を謳歌する。
芸術とは幻想なのだ。これは寝台だと思い込ませることで、真理も実用性も考えず、見る人を楽しませるだけのものがプラトンにとっての芸術である。
実際のところ、プラトンは同時代の芸術家たち、だまし絵の技術を競うような画家たちに対して怒っていたのだ。そのうちの一人、ゼウクシス〔紀元前五世紀の画家〕は、岩の上に本物そっくりのブドウの絵を描いたところ、鳩が間違ってついばもうとしたと言われている。
少数派であった文学的な哲学者プラトン
だが、たとえ、プラトンの芸術批判が本気のものであり、その後連綿と続く哲学者による芸術批判の口火を切るものだったにしろ、プラトンは芸術、とりわけ詩について複雑な思いを抱いていた。若き日のプラトンは一時的とはいえ詩人になろうとし、厳密な意味での哲学的議論に加え、神話や画像、寓話などもしばしば引用している。要するに、プラトンは本当の意味での「作家」であり、プラトンのように文学的な哲学者は実は少数派なのである。
プラトンは、『ソピステス』のなかで、だまし絵的な芸術ではなく、複製の技術であるとしてエジプト芸術を擁護し、持論に含みをもたせている。少なくとも実物の比率を「忠実に再現」しようとしていると評価しているのだ。
均衡の真理を愛したプラトン
プラトンは忠実な再現を目指したエジプト芸術(人間の身体の各部位を最もシンプルな角度から再現して描いたパピルス画がその一例)を、均衡や黄金比のもつ本質的な美を無視し、ただ客を喜ばすことだけを考える模造の芸術であるギリシャ芸術と区別している。
民主制や芸術に対する厳しい批判、そしてその厳しさを多少とも緩和させる時においてさえ、プラトンにとって重要なのは真理への愛であり、永遠のイデアに対する忠誠心なのだ。
プラトンの創立した学校、アカデミアの正面には、「数学を学ばぬ者この門をくぐるべからず」とある。均衡の真理を愛する者しか入ってはならないという意味だ。均衡の真理こそ、数学が私たちに教えてくれるものであり、一時的な感情や意見、可感界の表面的な世界と距離を置くことを教えるものである。
数学がサイエンスの基本であるのは、他の分野に比べ、感覚でとらえた具体的な物体を抽象化し、幾何学、代数という絶対的に純粋な状態で考えることを可能にするからだ。
当時、プラトンの野望は失敗に終わった
プラトンは『ソクラテスの弁明』で師のソクラテスを賛美し、その教えを忠実に守ってきた。そして、真理に到達する手段として、「産婆術」を唱えるようになった。質問や後押し、時に皮肉を言うことで「胎内にある《精神》を引き出す技術」と言ってもいい。
偏見から魂を救い出し、すでに胎内に存在している「真理」の存在に気づかせる。つまり、「再認識」させるのだ。もちろん、簡単でないことは百も承知だ。
有名な「洞窟の寓話」は、人間が目に見えるものに囚われている様を示している。洞窟から一度も出たことがない人は目に見えるもの(実は小さな開口部から射し込む光によって洞窟の壁に映し出されている虚像にすぎない)を現実だと思い込む。
一方、哲学者は洞窟の外におり、遠くや天上の世界を眺め、見た目だけの幻影にはまどわされない。哲学者が洞窟に戻り、人間に真理を教えてやろうとしても、人はそれを信じようとしない。幻想の居心地の良さから離れたくないのだ。
芸術を批判したプラトン自身も、哲学的対話という新ジャンルで必ずしも成功を収めたわけではない。今でこそ、偉大なる古典哲学の祖とされているが、当時彼は人気を得ることを夢見、劇作家に嫉妬し、自身も対話という新ジャンルの文学の創立者になろうとしていたのである。だが、その野望は失敗に終わった。
劇場は常に人々を魅了しつづけ、詩人も人気があった。詩人が都市を追われることはなかった。一方でプラトンの対話は、彼の生きているあいだ、ごく一部の人にしか人気がなかった。
それでも、後年になって再評価され、アングロサクソン系の哲学者ホワイトヘッド〔1861~1947〕が西欧哲学はすべて「プラトンの対話の脚注」にすぎないと言うまでになったのである。
プラトンからのアドバイス
いつも他人に意見を求めて、決断できない。最後にしゃべった人の意見に同意してしまう、あなた。
正解を求め、解決策を手にしたいのに、様々な視点のあいだで迷ってばかりのあなた。
プラトンなら、もっと自分に自信をもてとシンプルなアドバイスをくれるだろう。だって、真理はあなたのなかにあるのだ。真理はあなたの外、つまりあなたがもっていないけれどほかの誰かがもっている知識のなかにあるわけではない。
『メノン』を思い出してほしい。『メノン』のなかでプラトンは、アナムネーシスを説明している。今、あなたは真理を探しているけれど、あなたはそう遠くない昔、真理のすぐそばで暮らしていたことがある。永遠のイデアの大きな浴槽のなかを漂っていたのだ。
こんな解釈はどうだろう。あなたのなか、あなたの奥底には自分でも気づかないものが眠っているのだ。
だからといって、他人の存在や他者との対話が何の役にも立たないというわけでもない。他者との交流は必要だが、プラトンはその付き合い方に条件をつける。
他者と語り合うのは、あくまでも自身と対話するためであり、あなたが真理にたどりつくためのヒントが他者の指摘から得られるかもしれないからだ。他者の言葉に真理や正解を求めて対話するわけではない。
他者を頼ろうとしないこと
まずは、他者が答えをもっていると思わぬこと、他者を頼ろうとしないことだとプラトンは助言するだろう。
プラトンとの対話において、ソクラテスが真理を明かすことはない。ソクラテスはただ先入観を取り除き、論点の矛盾に気づかせようとする。何かを明かすのではなく、何かから解き放つのだ。
自分を信じて、他者と会話し、明白な真理が現れる瞬間を待つ。それが「理解する」ということだ。
こうした確証は簡単に見つけられるものではない。確証がなければ、それは印象にすぎない。それこそがプラトンの闘いであった。
『ピレボス』に書かれているように最初に感じたことは、ただの反射的な反応にすぎない。確証は、あとになって、ある種のねぎらいとしてやってくる。そうなるともはや人は真理を見ずにはいられないのだ。
紀元前428(427?)~前348(347?)
古代ギリシャの哲学者、ソクラテスの弟子(ソクラテス自身は著作を残していない)、アカデミアと理想主義の創始者。

