※本稿は、シャルル・ぺパン(著)永田千奈(翻訳)『フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者』(草思社)の一部を再編集したものです。
徹底して疑っていたデカルト
デカルトは思考の実験を極めた人である。急進的な思想家としてあらゆる事象を問題にし、疑い、確固たる新たな土台の上に知を再構成しようとした。現在「デカルト主義」と呼ばれている頭でっかちな合理主義とは程遠い人なのだ。

リンゴの入った籠がある。ほとんどが腐っている。腐ったリンゴを排除しようとするなら、少しでも傷があるものをすべて排除しておかないと、すべてを捨てることになりかねない。傷のついたリンゴを一つでも見逃せば、あっという間にすべてがだめになる。デカルトならば、すべてのリンゴを一つずつ点検し、無傷のものしか籠には戻さない。たとえリンゴが少なくなろうが、合格するリンゴが一つもなくても、手加減しない。
デカルトの特徴はこの徹底にある。確実な土台となるものを特定するには、疑ってかかることが必要だった。だが、疑うこと自体が彼の哲学の目的ではない。この点は、徹底して疑うことだけを考えていたピュロン〔紀元前三六五頃~前二七五頃。古代ギリシャの哲学者〕など、古代の懐疑論者たちとは一線を画す。もちろん、たとえ疑うことが真理を極める「手段」や「方法」にすぎないとしても、デカルトは徹底的に疑う。
世界は本当に存在しているのか
世界は本当に存在しているのだろうか。夢のなかでは、存在しない世界をリアルに感じる。ということは、今こうしていることも夢なのではないだろうか。この肉体は、目の前のコップは、本当に存在するのだろうか。触ることができれば、それが存在する証拠になるだろうか。砂漠で喉が渇いたとき、人間はオアシスの幻影を見るという。触れることができても、この目で見たことでも、それが真実だという証拠にはならないのではないだろうか。砂漠で幻を見る人と今の自分にどれだけの違いがあるだろう。つまり、感覚は信用できない。デカルトは蠟を例に「錯覚」を説明する。
封蠟は硬くて冷たい(触覚)。うっすらとではあるがどちらかといえば良い匂いもする(嗅覚)。赤っぽい色(視覚)、食品ではないが、口に入れると不味いことがわかる(味覚)。だが、ここでデカルトは、この封蠟を火にくべ、感覚の「言う」ことなど頼りにならないことを示そうとする。火のなかに入れられた蠟を想像してほしい。すべてが変わる。さきほど五感で得た情報はもはや真理ではない。形状が変わる。蠟は熱くてやわらかい。もう触ることも難しい。匂いが変わる。色や形もさきほどとは違う。口に入れることもできない。では、蠟の本質とは何だったのか。
われ思う、ゆえにわれあり
真理を説明しようとすると、まず感覚がとらえたことはすべて排除しなければならない。必要なのは、思考、「《精神》による観察」である。何もかも疑ってなお残るのが思考であり、疑うという思考である。
となると、最も確実なものは、疑っている自分である。どんなにすべてを疑っても、自分は今、疑っているのだと考える自分がいる。それだけは確実だ。何もかも疑ったところで、疑っている自分だけは消えない。今、この存在が夢ではないのは、砂漠で渇きのあまり見えてくる幻影よりも現実味があるのは、考える自分があるからだ。
いや、砂漠で渇く人だって、確実なものが一つある。あのオアシスは幻影かもしれない。だが、彼が周囲のすべてを疑いはじめたとき、一つだけ確実に存在するのは、疑っている自分なのだ。デカルトの有名な言葉「われ思う、ゆえにわれあり」はこうして生まれた。
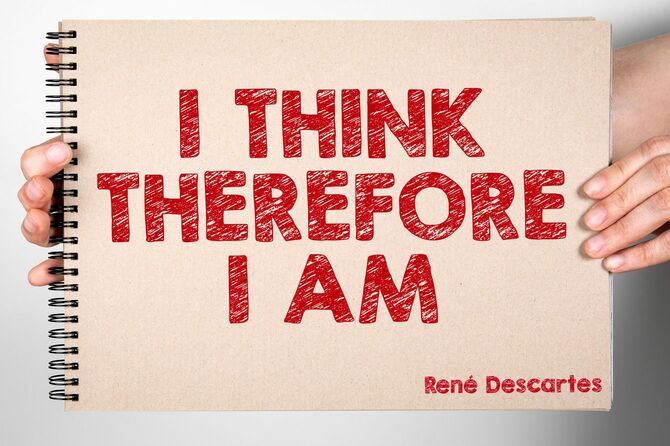
デカルトの徹底した合理性は、この「ゆえに」にある。というのも、多くの人は特に意識することなく、感覚を盲信しがちなのだ。
さらに言うと、この「ゆえに」が大事なのは、思考、そしてその先にある哲学というものが濃厚な実存体験であることを示しているからである。
いや、思考とは存在そのものだと言えるかもしれない。デカルトはキリスト教的な省察の長い伝統を引き継ぐと同時に、古代哲学における精神鍛錬の後継者でもある。省察にしろ、鍛錬にしろ、単なる神学的な思弁を超え、人が自分を鍛え、よりよく生きようとするトレーニングなのだ。デカルトは、現在「デカルト的」と言われているものとは少し違っており、ある意味ではのちの「実存主義」を先取りしている一面もある。
急進的な良識派・デカルト
デカルトの抱える矛盾は、彼の二冊の著書『省察』と『方法序説』の両極端な内容と、その対比によく表れている。まず、すべてを疑い、世界の存在さえ疑念を抱く、急進的な側面があり、もう片方には、現在「デカルト的」とされている慎重で、進歩的な良識ある側面もある。この二つの特性は混じり合うことも少なからずあるのだが、わかりやすくいうと、『省察』のほうが急進派で革命的なデカルト、『方法序説』のほうが慎重で、良識派、伝統を守るデカルトだ。デカルトにとって良識は「世の中で最も広く共有されているもの」であった。
四段階法で考える方法を説く
彼は、一六三七年に『方法序説』をラテン語ではなく、誰もが読めるようにフランス語で書いた。そして、よりよく考えるため、偏見の餌食にならないために四段階で考える方法を説いた。そのシンプルさは実に驚くばかりだ。彼によると良識をもつための思考ステップは四つある。
一つ目は、確実なことから出発すること。最初に出てきたものや表面的な事実に飛びついてはいけない。注意深く考え、慎重に検討したうえで確定した根拠が必要なのだ。つまり、ある程度時間をかけ、一度疑ってみたうえで、それでも確証が揺らがなかったことのみを真理とする。
二つ目は、問題を分解、分析して考えること。複雑な問題に直面したときは、まず複数の単純な問題に分解してみる。たとえばうまくいかなくなってしまった夫婦。実に複雑な問題だ。問題を理解するために、まずは、いくつもの要素に分解してみる。景気、相性の問題、経済的な問題、セックスの問題、将来への計画性などを個別に考えてみるのだ。
三つ目は総合する。分析し、複雑な関係にある個別の要素を見極めたあとで、もう一度全体を俯瞰し、本質をつかむ。夫婦の例に戻るなら、社会的な状況や経済的な問題が原因ではなく、むしろ相性の問題、つまりは二人の性格の不一致によるものだという結論になるかもしれない。
四つ目の作業は、ほかに考慮し忘れた要素がないか確認することだ。夫婦がうまくいかなくなったのは、予定より早く子供ができてしまったせいもあるのではないだろうか、など。
以上、四つの思考ステップを見るかぎり、特別に画期的な要素は感じられない。同様に、デカルトは数学の証明においても、常に二段階の作業が必要だとしている。最初は直観によって、命題が明白であるかを判断し、次に推理する。まずは自分を疑うのだ。現在、考え方の硬直した人が「デカルト的」と称される傾向があるが、こうして見ていくと、デカルトの印象もだいぶ違ってきたのではないだろうか。
デカルトは、なぜ神の存在を証明しようとしたのか
こんな良識あるデカルトが、なぜ、一方ではあれほどまで必死に神の存在を証明しようとしたのだろうか。生涯にわたり、人間の知性の限界を見定めた結果として(もちろん、間違いがないように、基本的な手順を踏み、時間をかけて真理だと証明できるか吟味したうえで限界を確定する)、限界を知らない存在があると示そうとしたのだろうか。
矛盾は単に表面的なものでしかない。デカルトは人間の知性の有限性から神に至ったのだ。より正確に言うなら、人間のなかには無限という概念として、神が存在するというのが彼の出発点だった。無神論者でも、少なくともこの点までは受け入れられるのではないだろうか。私たちは無限である。それは無限という抽象的な概念をもっているからだ。
一方でわれわれの思考は、自分たちがこの世の有限な存在であるという自覚から出発しているとデカルトは言う。われわれは、有限という概念を自分たちが知る有限のもの、自分たちの有限の知性に基づいて構築している。だから、人間が自分たちだけで考えるかぎり、無限という概念にはたどりつけない。よって、われわれのもつ無限という概念は、有限の存在を超えたものから与えられたものである。つまり、神は存在する。
存在論的証明と呼ばれる神の証明
これが「存在論的証明」と呼ばれるデカルトによる神の存在の証明であり、アンセルムス〔1033~1109。神学者、哲学者〕の影響を色濃く受けている。アンセルムス自身も著書『プロスロギオン』のなかで、神という概念から演繹法で神の存在を証明している。抽象的な思考の実験という意味で、デカルトは彼の後継者であり、有限な人間が無限という概念をもっているのはなぜか、という単純な発想から出発し、誰にでもわかる段階的な検証を経て、無限の存在である神が必然の存在であることを示そうとした。
もちろん、理性を重んじるデカルトの本質と信仰の折り合いはどうなるのかという問題は残る。『方法序説』であげた最初のステップは「確実なことから出発する」だった。数学的な真理も最初の明証を土台にしている。
だが、そもそも私たちはどうしてそれが明白な証拠だとわかるのだろう。デカルトならこう答える。神が人間に「生得観念」を授けた。そのおかげで私たちは第一確証を認識できるのだと。
だが、もし「生得観念」によって、段階を追い神の存在証明に達するのならば、神のおかげで神の存在を証明することになってしまう。これでは存在証明というより、仮説をもてあそんでいるだけではないだろうか。
想像は経験の組み合わせ
神の存在論的証明が説得力のあるものかどうかはともかく、無限と有限をめぐる弁証法的な考察は常に繰り返され、多くの人を惹きつけている。人の思考には限界があるが、無限という概念は存在する。思考に限界があっても、人間にはもう一つ限界を知らない力があるとデカルトは言う。どんな力だろう。
想像力のことではない。人はしばしば自分たちが無限の想像力をもち、純粋なファンタジーの世界をどこまでもつくりあげられると思っているが、それは誤りである。デカルトに言わせれば、想像というのは常に現実に存在するもの、自分で経験したことを組み合わせているだけなのだ。
ピンクの象を想像する。奇想天外な発想だ。だが、デカルトにしてみれば、ピンク色を見た経験と、ふつうの象を見た経験を組み合わせたものにすぎないということになる。想像力は無限ではない。既知のものを超える想像はありえない。
感性でもない。感覚によって得る情報は限定的なものだ。そもそも人間には、フクロウほどの視力もなければ、犬ほどの嗅覚もない。

人間にある有限の知性と無限の意欲
知性にも限界がある。無限の世界へと到達する力は、ただ一つ意志の力しかないとデカルトは結論する。確かに、私たちは今よりも多く、今よりも高くと求めつづける。無欲ではいられない。善でありたいという欲もある。つまり、神になりたいという欲が人間を神に近づける。
人間には二つの特性がある。有限の知性と無限の意欲だ。人間には有限(知性)と無限(意志・意欲)が共存している。デカルト主義とは、無限と有限の弁証法なのだ。
有限の知性と無限の意志というあらたな人間像からデカルトを考えると、彼の提唱する思考方法についても納得がいく。特に、自由な哲学という意味において、彼がとても独創的な哲学者であったこともおわかりいただけるだろう。
実際、もし神が人のなかに「生得観念」を授け、人間の多くが良識を得ているとすれば、なぜ私たちはこうもしばしば過ちを犯すのだろうか。それは私たちが自由だからだとデカルトは答える。この自由があるからこそ、わたしたちの意志と知性は必ずしも嚙み合わないのだ。
自由とは知性と意志を調和させること
つまり、わたしたちの意欲が無限なので、私たちはあれもこれも欲しがり、知性が設定した限界を超えることまで言い出してしまう。人が自分の知らないことまでつい口走ってしまうのは、知性が止めるのを聞かず意志が暴走するからだ。意志が理性を超えて決断してしまうのは、自由のせいなのだ。神のせいではない。私たちが過ちを犯すのは、私たちが知性によって限定された世界にとどまっていられないからだ。デカルトの意志についての思想は実に巧妙だ。人は無限の意志をもつゆえに神にも近づけるし、失敗もする。
だが、当然とはいえ、本当の意味での自由とは、知性と意志を調和させて生きることにある。理性に導かれたうえで、意志を貫く。デカルトは理性の仲裁を受け入れ、熟考のうえで選択する力、欲望と距離をおく力を「自由意志」と呼んだ。
ここでも意志の力が重要になる。理性による調整が終わるまで欲望を抑えておく意志が必要なのだ。知性による選択を受け入れる意志も要る。知性と意志がかけ離れたものであることも、その二つのあいだでできるかぎり折り合いをつけることも、実存的な経験なのだ。
デカルトは極端な自説で何度も不当に告発された
デカルトは何度も不当に告発されている。直近の例をあげよう。現代人の環境破壊の大本をたどると、デカルトに行きつくという説がある。デカルトは物理学者でもあり(「慣性の法則」の名付け親は彼だ)、人間を「自然の支配者であり所有者」であるとした。
デカルトには、「物理学者」であると同時に、「形而上学者」の側面もある。そんな彼にとって自然とはただ素材が並んでいるだけのものであり、神的なものでも聖なるものでもなかった。つまり、自然を知り、技術の発展とともに人間の生活環境を改善し、生活の質を高めるのは当然のことだった。
だが、もう一度繰り返すが、デカルトは、思考の実験を重視していた。自然と稚拙な関係しか結べない一部の人間や、植物には目的や意図があるという当時まだ根強かった偏見にあらがうため、デカルトはあえて極端な自説を唱え、同時代の人たちに自然を単なる素材としてとらえ、支配者や所有者の「つもりで」自然に向き合うことを呼びかけたのだ。当然のことながら、デカルトにとって、自然の本当の「支配者や所有者」は人ではなく神であった。
たとえ話の名人デカルト
デカルトはたとえ話の名人だ。実際、「何かになったつもりで考える」のは、思考の実験として実に便利な方法なのである。『方法序説』で彼は、「暫定的道徳」として四つの箴言をあげている。不安と向き合うための四つのルールなのだが、ここにも「つもりで考える」がある。
一つ目。その国の慣習に従おう。
二つ目。何かを決断するときは、それが最善策であるというつもりで遂行しよう。
三つ目。自らの欲求を満たすために努力しよう。だが、それができないときは、世界の秩序ではなく、自らの欲望のほうを変化させよう。
四つ目。真理を求めよう。
二つ目の箴言に「つもりで」という表現が織り込まれている。決断が正しいかどうかは神のみぞ知る。私たちは神ではないが、行動せずにはいられない。だから、神になったつもりで、自分を疑うことなく、それが客観的に見て最善の策であると信じて生きるしかない。
実際、それが最善策と「なる」かもしれないのだ。限られた知性を最大限に使って熟考し、ひとたび決断したら、すべての力を尽くして行動に移す。有限の知性というちょっと短めの足と、無限の意志という壮大だが危険を伴う足、両足でバランスを取り、転ばないように歩いていく。器用に折り合いをつけて進むのが、デカルトの描いた理想の人間像である。
デカルトからのアドバイス
決断できない。優柔不断で事なかれ主義に悩むあなた。
ころころと意見が変わり、決められないあなた。
『方法序説』にデカルトのこんな言葉がある。「優柔不断は悪よりも悪い」
デカルトは森で迷った男を例にあげている。森を出たければ一つの方向を選び、ひたすら歩くしかない。何度も方向を変えてぐるぐる同じところを歩いていたら、いつまでも森から出ることができず最悪の結果を招く。
あなたが決断できないのは、絶対を求め、完全な解決を求めるからだ。必ず結果に結びつく確実な方法が欲しいから、決められない。だが、私たちが暮らし、活動している世界は絶対の世界でも、永遠の真理の世界でもない。
アリストテレスがとっくの昔に言っているように(デカルトが八歳のときに、ラ・フレシュの神学校で最初に学んだのがアリストテレスの哲学だ)、形而上学的哲学と行動哲学は分けて考えなくてはいけない。形而上学的な視点で考えるなら、絶対や完全も存在しうる。
絶対に確実なものを求めていたら一生が終わる
だが、道徳や生活のなかで哲学が目指すのは、絶対や完全を求めることではなく、行動の指標をつくることである。だからこそ、デカルトは暫定的道徳を提唱した。絶対に確実なものを求めていたら、一生何もできずに終わってしまう。森のなかでさまよいつづけるだけだ。絶対に確実な光を待つうちに、飢えや寒さで死んでしまう。
だから、今を生きる私たちは不確実であっても行動することが大事なのである。簡単なことではない。だが、それが人間に与えられた条件なのだ。私たちは真理のなかに生きるわけではないし、神様でもないのだから。
1596~1650
フランスの哲学者、数学者。方法的懐疑と、人間の理解の限界と神の存在を証明する暫定的道徳の祖。

