決算発表を遅らせたこともある
ワークマンが定量的な目標(数値目標、仕事の期限など)を社員に押し付けない、社員を追い詰めない会社であることは、前編の若いふたりの社員に対する取材で確証を持つことができた。
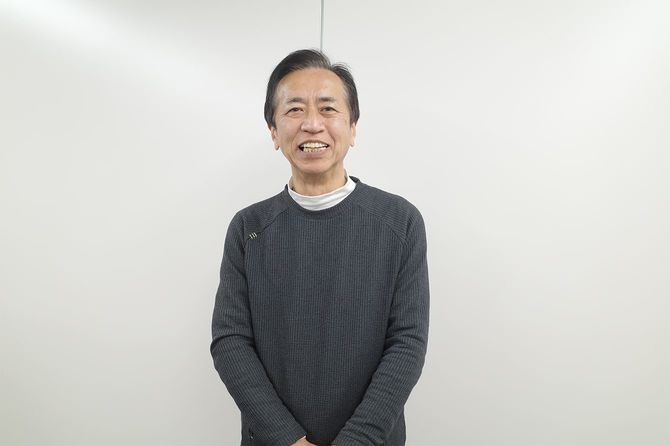
今回、土屋哲雄専務に伺ってみたいのは、なぜワークマンでそのようなことが可能なのか、そしてワークマン方式は他の企業でも可能なのかどうかである。まずは、前者について質問をしてみた。
「数値目標や期限を決めないといっても、いわゆる制度対応、たとえば、消費税率の引き上げとかレジ袋の有料化といったことは、期限内にやらなければなりませんよね。しかし、そんな仕事は全体の10~20%しかありません。残りの80%の仕事は、基本的にいつやってもいいんです。実際、ワークマンでは新店舗のオープンが間に合わなければ遅らせるし、決算発表を遅らせたことさえあります」
経理部社員の負担軽減を優先した
オープンの日や決算が遅れれば、対外的な信用を落とすことに繋がりはしないだろうか。
「たしかに上場会社が5月15日ギリギリに決算を出すと、監査上の問題があったんじゃないかと勘繰られるかもしれない。しかしその一方で、時間をかけてしっかり監査してもらうことのメリットも大きいんです。毎年きちんと監査をしてもらって1億、2億の修正をする方が、5年分まとめて10億も損を出すより企業の傷ははるかに小さい。決算を遅らせたのは、言い換えれば、IR的にいい会社であるという「決算早期化」の指標を捨てて、監査法人に質の高い仕事をしてもらい、経理の社員に残業させないことを選択したわけで、あらゆることはトレードオフの関係にあるんですよ」
納期がないので意地でも催促しない
つまり、ワークマンでは常に定量的な指標は捨てて、定性的な目標だけを追求しているということだろうか。
「対外的な制度対応を除いた80~90%の仕事に関しては、基本的に納期はいつでもいい。そう宣言している以上、私も意地でも催促をしません(笑)。その代わり、ワークマンの目標達成率は100%なんです。だってできるまでやるんですから。2、3年かかっていいからと言えば、たいていの目標は達成できますよ」
40年前から「しない系」の会社
それがワークマン方式であるのはいいとして、ではなぜ、時間や期限といった定量的な目標ではなく、仕事のクオリティーを上げることや社員のストレスを軽減するといった定性的な目標が選択されるのか、いや、選択することが可能なのだろう?

「ワークマンは余計なことは一切しない会社です。もちろん社内行事もしませんが、この場合、社内行事をやることで社内のコミュニケーションが良好になることと、そのしわ寄せで残業が生じることのトレードオフになり、ワークマンでは社員の働きやすさ、つまり残業をさせない方がより価値が高いと判断をするわけです。社員の働きやすさを優先するという考え方は、加盟店のオーナーさんの採用にも反映しています」
どういう意味だろう。
「売り上げを最大化するようなガツガツした人は採用せず、自然体で人柄のいい人を選んでいるのです。いくら売り上げが増えたって、人柄が悪くてガツガツした人だと、社員がSVとして訪店した時にプレッシャーがかかるじゃないですか。お客さまに対しても同様で、売り上げ売り上げ言ってるオーナーが、まごころを持って接してくれるとは思えません。だから、人柄で選ぶんです。
このように、どちらか一方の指標を捨て去るには勇気がいりますが、なぜワークマンの現場がそうした勇気を持てるかといえば、ひとつには、ワークマンがすでに40年前から『しない系』の会社であり、90%はしない系のDNAになっていたということがあります。そこに私が、働き方改革や社員のウエル・ビーイングといった要素を10%だけ付け加えたと、こういうことだと思います」
ワークマンが40年前から続く「しない系」の会社であるのは、当然、ワークマンが個人向け(法人を対象としていない)作業服というニッチなジャンルをほぼ独占してきた企業であることと深く関連しているだろう。
売り上げではなく客数を増やす
作業服は消耗品だから常に一定のニーズがあり、機能優先でデザインに流行り廃りがない。そうした業界特性の中、ワークマンは高機能な商品を最安値で販売するというポリシーを貫くことで、高い支持を集めてきた。
「別な言い方をすれば、ワークマンは売り上げを増やそうとせずに、客数を増やそうとしてきたのです。売り上げを増やすために製品単価を上げれば儲かりますが、儲かるとなると新規参入が増えて競争が激化してしまう。だから、ワークマンの経営指標は売り上げではなくて客数なんです。客数が増えて売り上げが増えたら、その分をお客さまに還元してさらに値段を下げてしまうのです」
そこまで徹底して低価格を追求していれば、競争者は簡単には現れない。その結果、ワークマンと常連客との間には、絶対的な信頼関係が成立することになる。
値札を見ずに買っていく顧客
「店舗を観察していて気づいたことですが、ワークマンのお客様は滞留時間がとても短い。なぜなら、値札を見ないで商品をレジに持って行くからです。良心的な価格であることを信じて下さっているから、値札をチェックする必要がない。みなさん、デパートで値札を見ずに買い物をしますか? 値札をチェックするのは価格に不安があるからですよ」

低価格の実現に貢献しないことは徹底的に「しない」ことで、ワークマンは40年という長きにわたって客の信頼を獲得し、その圧倒的な信頼が安定経営の支えになってきた。だから、客の信頼を裏切るようなことはしない。そして、裏切りの最たるものが、「短期的に売り上げの拡大を図ること」なのだろう。
トレードオフの関係にある選択肢のどちらを選ぶかという判断には、常に「低価格の実現」と「長期的な信頼の構築」に資するか否かというモノサシが当てられる。現場が勇気ある選択を下せるのは、暗黙のうちに、こうしたモノサシが共有されているからではないだろうか。
急拡大するつもりはなかったのに、売り上げが上がってしまった
ワークマンは現在、10期連続で最高益を更新するという快進撃を続けている。2014年に成長の限界を見越した土屋専務が中心となって「客層の拡大」という新たな経営ビジョンを打ち出し、ワークマンプラス、#ワークマン女子という新しい形態の店舗を生み出した結果だ。
これは一見「売り上げの急拡大」に見えるし、実際、ワークマンの売り上げは急拡大しているが……。
「ワークマンは売り上げにこだわっていませんし、私も急拡大をしたいとは思ってはいません。どうせホワイトマーケット(空白の市場)なので、本来は20年、30年かけてゆっくりと耕していけばいいのです。しかし、客層の拡大を図った結果として売り上げが拡大してしまったと。ここで、あまりにも仕入れや生産(PV商品を生産している)をチビって欠品ばかり出していると、『ワークマンは消費者の方を向いていない』と受け取られてしまう。そうした『評判のリスク』があるので拡大をしているのであって、あくまでも売り上げの拡大自体が目標ではないんです」
とてつもなく大きい覚悟
「客層の拡大」とは、作業服のユーザーであるプロの職人以外の層にワークマンの商品を販売していくことを意味する。冷静に考えてみれば、これはとてつもなく大胆なデシジョンである。
「プロのお客さまには朝と夕方売って、昼間は一般のお客さまに売るなんていう二毛作みたいなことが、本当にできるのかと。先ほどのトレードオフの議論では、判断には現場の勇気が必要だと言いましたが、こうしたデシジョンを下すためには経営陣の覚悟、それも大きな覚悟が必要です。2年、3年で売り上げを増やすなんていうのは小さな覚悟であって、『客層の拡大』は、経営者が2代、3代引き継いで100年かけてやることですから、とてつもなく大きな覚悟なんです。裏返して言えば、多くの大企業が掲げる目標のほとんどは軽いもの、小さな覚悟しかいらないものなのです。そういう目標をいくつも立てたって、何がやりたいのか社員にはよくわからないのです」
「しない系」の神髄
仮に経営者がそのような大きな覚悟ができる人物だったとしても、ホワイトマーケットが見つからなければ、100年の競争優位を築くことなど不可能に違いない。ホワイトマーケットを持たない企業は、コンペティターとの激しい競争を勝ち抜くために、それこそ社員を数字で追い込み、プレッシャーをかけ続けるしかない。
要するにワークマン方式は、ホワイトマーケットを持つワークマンにしかできない方式なのではあるまいか?
「それは、順番が逆なんです。先にホワイトマーケットがあったから大きなデシジョンができたのではなく、たっぷりと時間をかけさせてもらったからホワイトマーケットを発見することができたのです。実際私は、2012年にワークマンに入社してから2年間というもの、社員教育以外の仕事はまったくやりませんでした。何も仕事をせずにひたすら店舗を観察し、社員の話を聞いた。なぜそんな時間を持てたかといえば、土屋嘉雄会長(当時)に『何もしなくてもいい』と言われたからです(笑)。これがまさに、しない系の神髄なんですよ」
土屋専務は、たとえ大企業であっても部門単位ならば、ビジネスの軸をずらすことによってホワイトマーケットを発見することは可能だという。
常に競争のないホワイトマーケットでビジネスができれば、たしかに、社員は納期やノルマに追われることなく、納得のいく仕事ができるのかもしれない。しかし、ニワトリと卵ではないが、ホワイトマーケットを発見するためには、土屋専務がそうだったように、「納期やノルマ」に追われていない長い時間が必要になる。
そうした時間を思い切って社員に与えられるかどうかも、とどのつまりは、経営者の「覚悟」にかかっているのではないだろうか。
