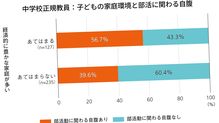繊細な人はネガティブな結果がでやすい
「社会的比較」をすればするほど、好ましくない比較対象にぶつかる可能性が高くなります。そして、「社会的比較」をする人が、繊細であればあるほど、ネガティブな結果がでやすくなるでしょう。「社会的比較」は、とりわけ不公平な結果をもたらすものです。というのも、どれほど成功したり金持ちになったり、幸運に恵まれても、自分よりも優れている人はつねにいるからです。
人をうらやましく思っていたら、幸せにはなれません。「社会的比較」に注意を向けすぎる人はいつも傷つきやすく、何かにおびえ、不安を感じています。
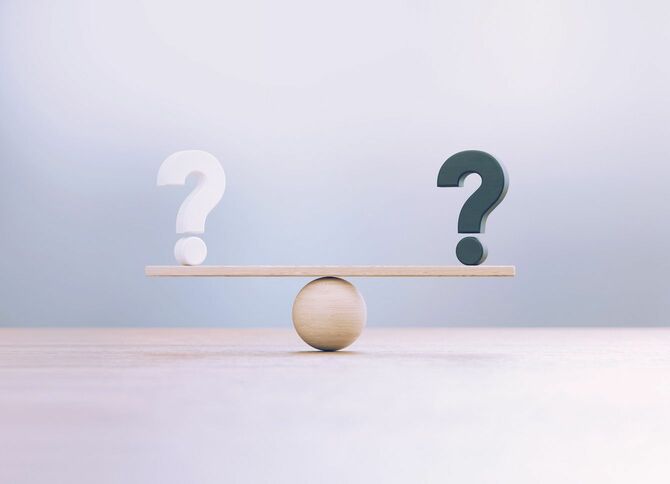
「とても幸福である人」と「とても不幸である人」の違い
興味深いことに、自分を他人と比較するという現象は、科学者となって私が最初に研究の対象にしたものでした。私がスタンフォード大学の大学院に入った最初の年、アドバイザーだったリー・ロスと私は、知り合いや友人のなかから「とても幸福である」または「とても不幸である」と指摘された人を探して、両方のタイプの人々に詳細なインタビューをしました。私たちの最初の仮説(あとから考えると、とても単純なものでした)は、「幸福な人は、自分よりも劣った人と自分を比較する傾向があり、不幸な人は自分よりも優れた人と自分を比較する傾向がある」というものでした。
けれども、「社会的比較」について私たちが周到に用意したいくつもの質問を参加者にしたところ、幸福な人々は、そのような質問が何を意味しているのかわからなかったのです。もちろん、自分を他人と比較することの意味は彼らも理解していました。毎日の観察や人との交流、そして他人の成功や失敗、意見、個性、ライフスタイル、人間関係などについてメディアが伝えるあふれるほどの情報から「社会的比較」は簡単にできるし、避けがたいものです。