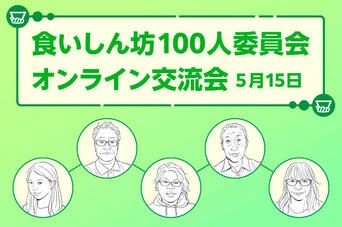売り上げに大きく作用するBGM
このように、音は聴覚以外の感覚も動かしていきます。これを踏まえて背景音や環境音をうまく使えば、場所やサービスの雰囲気を作れます。ここからは、商業の実例を挙げながら見ていきましょう。
マーケティングにおける背景音や環境音の研究は、企業と消費者との接点である小売店などでよく行われてきました。
小売業界では、周囲の音を意図的にコントロールするケースはふつうのことになっています。
わかりやすい例がBGMです。
BGMが消費者の気分、態度、行動にどのような影響を与えるかについては広く研究されてきました。大きく分けて、
①音楽のテンポ
②音楽の種類
③音量
の大きく3つを対象にした考察があります。
まず、店内の音楽のテンポは、買い物のペースに関係するといわれています。ゆっくりしたテンポの音楽を聴いた消費者は、ゆっくりとしたペースで動作する傾向が強くなります。ゆっくりとしたペースで動けば、もちろんサービスを受ける時間や店内にいる時間は長くなり、結果的に消費者の消費機会を増やして、購入する量は多くなります。
スーパーマーケットでそれぞれ早いテンポと遅いテンポの音楽を流した実験があります。買い物客はスローテンポの環境でより多くの時間とお金を費やしました。売上が38%増加した結果も出ています。
レストランでの音楽のテンポの考察についても以前お話ししましたが、音楽のテンポが遅い場合と速い場合を比べると、遅い場合には、食事に時間がかかりました。ゆっくり食べる傾向にあるので、テーブルで過ごす時間が増え、より多くの飲み物が飲まれるようになります。飲み物の売上が41%増加した報告もあります。
緻密な音声マーケティングの実例
身近な具体例では、日本では牛丼チェーンやコンビニエンスストアのBGMです。
これらは私たちが考えている以上に緻密に設計されています。これらの店の多くはかつては、有線放送を流しっぱなしにしていました。どの消費者に対しても、差し障りない理由でJAZZチャンネルが多く選ばれていました。
それが現在は、各企業とも適切なマーケティングによりプログラムされたBGMの導入が目立ちます。朝、昼、晩、深夜に区切って、それぞれに1時間程度の放送プログラムを作成しています。
朝は軽快でさわやかな音楽、日中は明るいポップス、夜は落ち着いた洋楽のように変えます。最近では音楽に加えてトークも多く挿入され、広告も流れるようになっています。