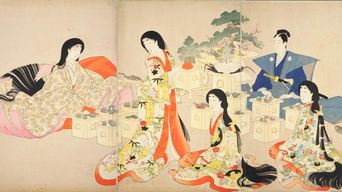戦争の最初の犠牲者は真実
自分たちの命や暮らしに直結する意味では原発事故と同様、いやそれ以上に読者は「新しい戦前」の中で何が起きているのか、国がどこに向かっているのか、「本当のこと」を知りたいはずです。
ところが政権は安保法制に先立ち、特定秘密保護法を13年12月6日に成立させました。新聞記者が国民の「知る権利」に奉仕するため、権力側の秘密やウソを暴くことを妨害するための「装置」です。なぜならば、何が秘密かは政権の意のままなのです。
成立した翌日の朝刊1面には「権力監視ひるまず」との見出しを付けた社説の責任者である論戦主幹の論説を掲載しました。ジャーナリズムの世界では「戦争の最初の犠牲者は真実」という「至言」があります。もはや、犠牲者がいつ出るか分かりません。国の秘密を暴いた記者と編集局に捜査の手が入ることも想定できますが、ひるむことなく権力の監視を続けることを、論説を通じて読者に誓ったのです。
「言いたい事」ではなく、「言わねばならない事」を書くことに徹することも、特定秘密保護法や安保法制などをめぐる報道では心掛けました。
明治から戦前にかけて軍部と権力者を痛烈に批判し続けた新聞記者、桐生悠々の教えに基づいています。悠々は信濃毎日新聞の主筆時代の「関東防空大演習を嗤ふ」の見出しを付けた社説で知られています。その悠々が個人誌『他山の石』に、「言いたい事」は権利の行使であり、「言わねばならない事」は義務の履行だと記しています。
「大本営発表」の垂れ流しではない
「戦える国」を監視する中で、東京新聞は自分たち流のジャーナリズムを確立しました。これが第4章のテーマです。
一例を挙げると14年8月に日本ジャーナリスト会議(JCJ)大賞を受けた『論点明示報道』です。受賞理由には「憲法、安保、原発―ずばり核心を突く1面の『論点明示報道』」とありました。
東京新聞は「3・11」以降、権力が発信する情報を垂れ流すのではなく、論点や問題点を明示すること、記事の本質、核心を見出しで端的に伝えることに力を入れてきました。安保法制の成立を伝える朝刊1面トップの見出し「戦後70年『戦える国』に変質」は、論点明示報道の典型例です。
本書では他にも東京新聞のこだわりの紙面をふんだんに載せました。記事と見出しと写真が一つになって、読者の頭と心に情報を伝える新聞ならではの世界が広がっています。
最終章である第5章のタイトルは「『新しい戦前』の中で」としました。東京新聞が読者と一緒に取り組んできた「軽やかな平和運動」である「平和の俳句」の紙面展開や、先の大戦の記憶の風化に抗うための「新聞記者が受け継ぐ戦争」と題したロングラン企画などを紹介しています。後者の企画は私が社会部長だった03年に、戦争の「本当のこと」を伝えたいと思って始めたものです。