三笠宮百合子妃の本葬にあたる「斂葬の儀」
宮内庁のホームページが16年ぶりにリニューアルされることになった。デザインを一新するとともに、スマホの画面に対応した表示ができるようになるようだ。
どのようにリニューアルされるか注目されるところだが、皇室のことについて記事を書く上で、宮内庁のホームページが参考になることが少なくない。なにしろ天皇皇后をはじめ、各皇族の日頃の活動ぶりがそこからわかるからである。
当然、愛子内親王がどういった日程をこなしているのかも、そこから知ることができる。それを見ると、昨年の終わりの時期にかなり多忙だったことがうかがえる。
それは、三笠宮百合子妃が2024年11月15日の朝に101歳で薨去されたからである。その当日、天皇皇后と愛子内親王は弔問のため三笠宮邸を訪れている。
本葬にあたる「斂葬の儀」は同月26日、東京都文京区の豊島岡墓地で営まれている。天皇と皇后は、皇室のしきたりによって葬儀には参列していない。このことは、少し奇異な感じもするのだが、それについては後で述べることにしたい。
「葬場の儀」「墓所の儀」にも参列した愛子内親王
一方、愛子内親王のほうは、斂葬の儀に先立って11月24日に行われた「正寝移柩の儀」から、一連の儀式に参列している。
正寝移柩の儀とは、遺体を納めた棺を寝室から客間に移す儀式のことである。その日には、三笠宮邸で通夜も営まれており、愛子内親王も参列している。翌日の故人の魂を移した、位牌にあたる「霊代」を安置する「霊代安置の儀」についても同様だった。
その後、26日の斂葬の儀の当日には、愛子内親王は豊島岡墓地での「葬場の儀」にも「墓所の儀」にも参列している。葬場の儀は一般の告別式、墓所の儀は納骨にあたる。

天皇皇后については、16日に、一般の納棺にあたる「お舟入り」に先立って、三笠邸を訪れている。また、斂葬の儀当日には、遺体を乗せた霊車が豊島岡墓地に向かう間、御所で「お慎み」になっている。27日には、豊島岡墓地に拝礼に訪れている。
ただ、通常の活動はその間も続けており、斂葬の儀当日、天皇は令和6年秋の勲章受章者に拝謁している。
愛子内親王の儀式参列はつづく
その後も、愛子内親王は百合子妃の薨去にともなう一連の儀式に参列している。
順に見ていくと、11月27日には三笠宮邸での「斂葬後一日権舎祭の儀」と豊島岡墓地での「斂葬後一日墓所祭の儀」、12月4日には三笠宮邸での「権舎二十日祭の儀」と豊島岡墓地での「墓所二十日祭の儀」、同月14日には同じく両所での「三十日祭の儀」、年が明けて2025年1月3日にはやはり両所での「五十日祭の儀」に参列している。
これで終わったわけではなく、今後「百日祭の儀」や「一周年祭の儀」にも参列するはずである。その間、愛子内親王には各種の公務があるし、日本赤十字社常勤嘱託職員としての仕事もある。
これが皇嗣の秋篠宮になると、同妃や佳子内親王とともに、正寝移柩の儀、お通夜、霊代安置の儀、斂葬の儀に参列している。ただし、斂葬後一日墓所祭には参列しているものの、三笠宮邸での斂葬後一日権舎祭は佳子内親王だけで、権舎二十日祭の儀以降も佳子内親王だけが参列している。
他に、天皇皇后をはじめ各皇族は、一年に一度、神武天皇と昭和天皇の「皇霊殿の儀」や孝明天皇から大正天皇までの「例祭」、香淳皇后の「例祭」に参列する。
さらに昨年だと、6月8日には桂宮「宜仁親王十年式年祭」、7月24日には「後宇多天皇七百年式年祭」、8月9日には「平城天皇千二百年式年祭」、10月1日には「懿德天皇二千五百年式年祭」に臨んでいる。
国費でまかなわれる百合子妃の葬儀費用
ここまで詳しく見てきたのは、代々の天皇や皇族を追悼するための行事がいかに多いかを確認するためである。
果たして皇族以外に、これだけ頻繁にそうした儀礼に参列している人間はいるものなのだろうか。儀式はこれだけではない。国事行為として規定された行事や皇室祭祀などがある。
百合子妃の葬儀費用は3億2500万円あまりで、すべて国費でまかなわれている。これだけ、頻繁な儀式があれば、ただでさえ多忙である天皇皇后や各皇族への負担も大きい。84歳になった常陸宮華子妃などは疲労のため斂葬後一日墓所祭の儀の参列は取りやめている。
宮内庁の黒田武一郎次長は、一連の儀式の簡略化について「何かもし、いろいろと課題が生じることがありましたら、それはそれで検討すべきことはあるかもしれませんけど、現時点では決められた日程で対応していきたい」と、それを否定した(TBSニュース、2024年11月27日)。

皇族の葬儀を規定する法律は存在しない
一般の国民の間では、このところ葬儀の簡略化が進んでいる。身内だけで済ませる家族葬が広がり、火葬場に直行する「直葬」も珍しくなくなった。
百合子妃の場合、101歳での薨去であり、長寿を十分にまっとうしての大往生である。果たして巨費を費やし、天皇や皇族に大きな負担をかけてまで、これだけのことをしなければならないのか。世の中の流れからすれば、どうしてもそこに疑問を感じてしまう。
逆に、なぜ天皇皇后は百合子妃の葬儀に参列しないのか。この点も、そこに合理性があるのかどうかが問題になる。先代の天皇の葬儀として営まれる「大喪の礼」で喪主は天皇である。天皇が葬儀にかかわらないという伝統があるわけでもない。
天皇や皇族の葬儀について、そのあり方を規定した法律は、現在存在しない。大正15(1926)年に、それにあたる「皇室喪儀令」が公布されているが、それは戦後の昭和22(1947)年に廃止された。
しかし、百合子妃の葬儀もそうだが、実際のやり方は、廃止されたはずの皇室喪儀令に従って行われている。皇室喪儀令を見てみるならば、そこに附式としてあげられた一連の儀式がそのまま行われていることがわかる。
「神仏分離」で一掃された皇室の仏教信仰
天皇や皇族の場合、明治に時代がかわるまで、葬儀は仏教式で営まれていた。江戸時代には、皇室の菩提寺である京都の泉涌寺で葬儀が営まれ、遺体は境内にある月輪陵に土葬された。

ところが、明治政府は、王政復古ということで、それまでの体制を改め、神道と仏教を分ける「神仏分離」を行った。それに伴って皇室からも仏教の信仰は一掃されることとなったのである。
明治天皇の父親である孝明天皇については、泉涌寺で仏教式で葬儀が営まれたものの、山階宮晃親王が明治31(1898)年に83歳で亡くなった際、「かねて帰依の仏式にて葬儀を営みくれよ」と遺言していたにもかかわらず、当時の宮内省はそれを認めなかった。
晃親王は、江戸時代に門跡寺院である京都山科の勧修寺を継ぐため一旦は出家した。幕末に還俗しているが、明治になっても仏教信仰を持ち続けていた。ただ、宮内省は認めなかったものの、古式に則って葬儀が行われた後、密かに仏教式の葬儀も営まれている。遺言はかなえられたのである。
明治期にはじまる皇室喪儀令制定の経緯
皇室喪儀令がどのような経緯を経て成立したかについては、塩川彩香の論文「近代大喪儀儀礼の成立過程 『皇室喪儀令』の附式を中心に」(『神道宗教』273号、2024年1月)で説明されている。
皇室喪儀令を制定する動きは明治のはじめからあり、さまざまな調査も行われた。明治天皇の実母ではないものの、嫡母となった英照皇太后が明治30(1897)年に崩御し、翌年まで約一年をかけて大喪儀が営まれた。このときは、崩御が急なことで、政府が望むような古儀を復活させるまでには至らなかったものの、それ以降、研究が積み重ねられ、皇室喪儀令の草案が作られることになる。
しかし、明治天皇や昭憲皇太后の大喪儀もあり、皇室喪儀令の制定は大正時代に持ち越され、すでに述べたように、その公布は大正15年のことだった。

皇室喪儀令に込められた「孝行の模範」
大喪儀の対象となるのは、天皇・皇后・上皇・上皇后・太皇太后・皇太后で、喪主は天皇と定められた。そうした体制がとられ、追悼のための儀式がくり返されることになったのには、一つ重要な理由があった。
皇室喪儀令が制定された後、宮内省が発表した「大喪に関する法規」という解説では、天皇が喪主となり、「一切の儀式を統理あそばさるゝ制度を定められたことは、実に孝行の模範を一般に示さるゝ」という趣旨だと拝察されるというのである。いわば国民に対して亡くなった親に対する孝行の模範を示す絶好の機会になるというわけだ。
そこに天皇の意思がどれほど反映されていたかはわからない。そもそも皇室喪儀令が定められた時代の大正天皇は病にかかり、大正10(1921)年から、のちの昭和天皇が摂政をつとめていた。
ただ、ここで「孝行の模範」と言われていることは重要である。仏教式の葬儀では、「追善」という考え方がとられ、故人が十分に積むことができなかった善を、子孫がかわって積むことが求められ、そのために、初七日からはじまって、四十九日、百日、一周忌、三回忌という形で供養がくり返されることとなった。
天皇や皇族を対象とした葬儀も、結局は、こうした仏教式の考え方を土台に、それを神道式で行うものであった。だからこそ、多くの儀礼が営まれ、それが一年も続くことになったのである。
土葬を火葬にした上皇の意向
果たして今も、こうした煩瑣な葬送儀礼をくり返すことは必要なことなのだろうか。
宮内庁としては、それで予算を確保できるのかもしれない。役人はいかに予算を確保するかに力を注ぐ。
だが、皇室喪儀令をモデルとした葬送儀礼を続けることは、天皇や皇族に大きな負担を強いることになる。皇族の数が減り、公務の負担がその分大きくなっているなかで、葬送儀礼の簡略化は是非とも必要なことではないだろうか。
現在の上皇の意向で、土葬を火葬にするとともに、御陵(天皇の墓)が縮小されることになったのは、まだ天皇に在位していた2013年のことだった。葬送儀礼の簡略化は、そうした上皇の意向に沿うものであるはずである。
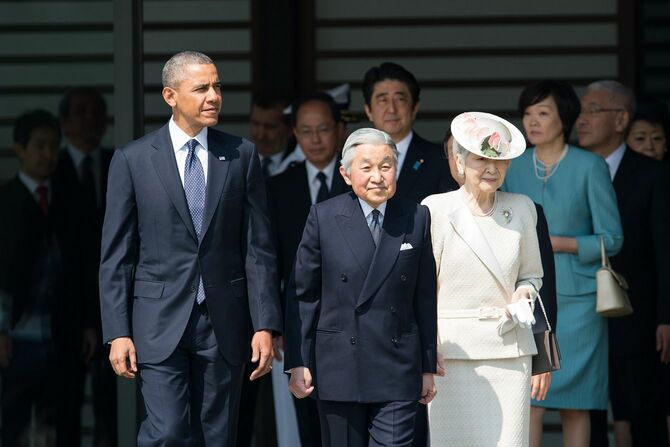
皇室喪儀令は廃止されてしまったわけで、天皇や皇族の葬送儀礼は法律によって定められたものではない。政府が決定すれば、すぐに実現される。
首相の決断が、今や求められているのである。
