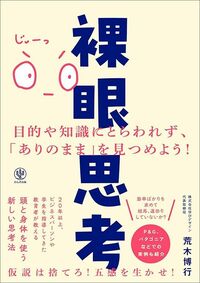※本稿は、荒木博行『裸眼思考』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
合理的な「レンズ思考」とストレートに見る「裸眼思考」
私たちは、常に合理的かつ効率的に働くために、「仮説思考」や「逆算思考」などの思考スタイルを駆使したり、これまでの経験や知識などに当てはめて判断したりしています。
言い換えれば、ノイズを排除する合理的で強力なレンズを持っていると言えるでしょう。このレンズの力によって、私たちは複雑な日常に対して余計なことを考えることもなく、シンプルに生きることができるのです。
ですが、レンズの度が強くなるほど、「今」をストレートに見ることができなくなってしまいます。ですから、時々このレンズを外して「裸眼」で物事を見る必要があります。そんな「裸眼思考」は、3つの側面から以下のように定義することができます。
2 アクティブな部位:脳だけでなく、五感を使っていること
3 意図:行動を意図するのではなく、物事を正しく理解することを意図する
目的や知識は、いずれも脳の作用によって意識することです。その作用を意図を持って弱めてみる。そして、焦って行動することから距離を置く。その代わりに、今目の前にあるものを五感のボリュームを高めて感じ取ってみることが「裸眼思考」につながります。
「仮説」を持たずにただ観察して見えてきたこと
そんな「レンズ思考」と「裸眼思考」の好例として、ハーバード・ビジネススクールの教授だったクレイトン・クリステンセン氏が好んで語る、マクドナルドのミルクシェイクの改善事例について紹介します。

マクドナルドは、非常に精度の高いマーケティング組織を抱えています。マクドナルドはそのマーケティング力を生かして、より良いシェイクをつくるために、シェイクの改善プロジェクトを立ち上げました。具体的には、数カ月にわたり顧客に詳細なヒアリングを行いました。
ヒアリングでは、ミルクシェイクを買う典型的な顧客に対して「どんな点を改善すれば、ミルクシェイクをもっと買いたくなりますか? 値段を安くすればいい? 量を多くしたほうがいい?」というような質問をしたのです。そして、その回答を踏まえて、改善を図ったのですが、残念ながら、売上にも利益にも全く効果はありませんでした。
そこで、プロジェクトに入ったクリステンセンのチームは、全く違うアプローチでこの課題に取り組みました。
それは、開店から閉店までの18時間、店頭に立って観察する、ということです。どうすれば売れるのか、という仮説を持たず、ただ観察することを心がけた結果、1つのことが見えてきました。
属性ではなく顧客のニーズに着目する
それは、9時前の早朝にシェイクが売れることであり、その顧客の大半は一人乗りの通勤ドライバーであるということです。この顧客に実際にヒアリングしてみた結果わかったことは、「勤務先まで長いドライブを退屈せず、また片手で手軽に飲食できるもの」として、シェイクが選ばれているということでした。
つまり、シェイクは、あっという間に終わってしまうドリンクやバナナに比べて長く楽しめて、ドーナツやベーグルのようにドライブ中の飲食がラクだという点で優れているという理由で、ドライバーに選ばれていたことがわかりました。
この顧客にとっては、シェイクの値段や味のバラエティは問題ではありません。それよりも、長く退屈なドライブに応えられる濃厚さや吸いづらさであったり、忙しい通勤ドライバーを待たせないような提供システムが重要になってきます。

しかし、観察の結果もう1つわかったことは、午後に売れるシェイクは顧客の属性が通勤ドライバーとは異なり、バラバラであることです。つまり、濃厚さや提供システムを変えても、午後の顧客には響かない可能性があるということです。
データ上では無味乾燥な数字としか捉えられない顧客の存在ですが、観察することによってシェイクを購入する際のストーリーが浮かび上がってきます。朝、通勤ドライバーとして買った顧客が、夕方は子ども連れでマクドナルドに来ている可能性がある。それは同じ「30代男性」というような顧客属性ですが、午前中と午後ではシチュエーションが異なるため、シェイクに対するニーズは異なるのです。
「裸眼」がかなえたブレークスルー
ここから、クリステンセンは、「その人の属性ではなく、その人が抱える用事(=ジョブ)に着目せよ!」というインサイトに至り、それがやがて「ジョブ理論」という独自のセオリーに昇華されていきます。
ここで注目するべきは、このセオリーの前提には、「観察を通じて顧客を知覚する」プロセスに大きな意味があったということです。
クリステンセンが語っていないのでわかりませんが、おそらく当時のマクドナルドのマーケティングチームには、ミルクシェイクを改善して売上をいくらまで高めるという強い目的意識と、今まで散々シェイクを売ってきたことに基づく豊富な知識があったと想像されます。
だからこそ、「おそらくシェイクを改善するポイントはここではないか?」という仮説があったはず。つまり、マクドナルドは、「レンズ」をかけたまま検討していたのです。これに対して、クリステンセンが出した価値は「裸眼」になったことにあります。
シェイクに関するさまざまなノイズを切り落として、まず顧客そのものを知覚したこと。ここにブレークスルーのポイントがあったのでしょう。
「商品やサービスありき」から離れる
ジョブ理論は、このようにクレイトン・クリステンセンが提唱したセオリーです。私たちは、とある商品やサービスに対して責任意識を持つと、その「商品やサービスありき」の視点で物事を見るようになってしまう傾向にあります。
売上や収益、もしくは顧客数が気になり、いかにしてその商品やサービスを拡散することができるかを考える。これはある意味当然のことでもあります。
しかし、そこには大きな落とし穴があります。それは、「真の顧客の姿」を見ることができなくなってしまう、ということです。この状態をクリステンセンは「プロダクトのレンズからモノを見ている状態」と表現しました。

自社プロダクト都合の曇った視界で世の中を見てしまうということを、クリステンセンは「レンズをかけている状態」と明言したのです。
そして、プロダクトのレンズを外せないから、顧客のニーズを正確に捉えることができず、結果的にローエンドからくる破壊的技術に負けるのだ、とクリステンセンは見立てました。
クリステンセンの「ジョブ理論」を実現するには
では、プロダクトのレンズを外してどうすれば良いのか? クリステンセンは、顧客の「片付けるべき用事(ジョブ)」を見ろと言います。
私たちは何かの用事を常に抱えています。先ほどの事例であれば、「出社途上の車内で手軽に長い時間をかけて腹を満たしていく」という用事です。その用事を解消するために、顧客はミルクシェイクを買うのです。
ミルクシェイクというのは、用事を解消するために選ばれた手段に過ぎません。その手段を見つめるのではなく、用事そのものに焦点を当てるのです。
では、どうやったら用事を見極めることができるのか?
それはこの事例でも語られた通り、観察をすることです。用事そのものは、顧客本人ですら認識していないことが多いので、第三者が観察して突き止めるしかありません。
「プロダクトのレンズ」を外し、まっさらな状態で、顧客の用事を探ることです。
クリステンセンが「ジョブ理論」を語る際、ミルクシェイクの事例をずっと語り続けるのは、おそらく彼が発見した顧客インサイトが、「18時間ずっと観察しなければわからなかった」ことにあるのだと思います。