39年前、三淵嘉子ら女性法曹家の人生をたどり本にまとめた
私が日本初の女性法律家たちについて取材し、ドキュメンタリーとして『華やぐ女たち 女性法曹のあけぼの』(復刻版は『三淵嘉子・中田正子・久米愛 日本初の女性法律家たち』日本評論社)を書いたのは、検事を辞めて、専業主婦をしていたときでした。

出版社の方に司法試験受験生のためのコラムのようなものを書いてほしいと言われたとき、雑談のような感じで、「日本に女性の弁護士や裁判官が生まれたのはいつですか」と聞かれたんですね。そのとき私は歴史を知らず、戦後だろうと思っていたんです。戦前は女性に選挙権もないし、「虎に翼」の中にも婚姻女性の「無能力」などが出てきましたが、結婚した女性は未成年と同じで、夫の同意がなければ、なんの法的責任も負えなかったわけですから。それで調べてみたところ、女性弁護士が戦前、既に誕生していたと知り、驚いたのです。
もうひとつ驚いたのは、三淵嘉子さん、中田正子さん、久米愛さんという3人の女性が、昭和13年(1938)に初めて高等試験司法科に受かったにもかかわらず、彼女たち3人に関する、まとまった本がなかったこと。当時すでに嘉子さんも久米先生も亡くなっておられたので、ご存命だった中田先生に当時のお話をお聞きし、書いておかないと、忘れ去られてしまうのではないかと、「私が今ここでやらなければ」という勝手な使命感がありました。
検事となり裁判官と結婚、当時は育休もなくて退職
取材を始めたのは昭和60年(1985)で、昭和62年(1987)の4月から弁護士を始めたので、その仕事と並行して残りの取材と執筆の作業をしたこと、育児もあることなどで、本が出るまで6年くらいかかりました。
私が検事になった昭和55年(1980)当時、女性検事はすごく少なかったんですね。私は裁判官と結婚したので、夫の赴任先についていく関係で、検事を1年で辞めて、主婦専業になりました。当時、検事は2年ごと、裁判官は3年ごとに全国転勤で。裁判官同士や検事同士だったらある程度は配慮してもらえると思うんですけれども、検察庁と裁判所では転勤のサイクルも人事の決定者も違うので、同居ができなくなるということで私が検事をやめたんです。
今は批判されていますが、「3歳児神話」と言って、当時は子供が3歳になるまでは母親が手もとで育てた方が精神的に落ち着くと言われていました。だから私も子供が3歳になるまでは育てようと思ったことと、「弁護士としてなら子育て後にも仕事できる」という思いもありました。実際、下の子が3歳になるぐらいに弁護士として復帰したのですが、公務員への復帰は無理。当時は育児休業なんてありませんから、検事や裁判官は結婚・出産して何年か育児に専念しようと思ったら退職しかなく、その後、職場に戻るには、もう一度、新たに採用してもらうしかありませんでした。
嘉子の実弟やひとり息子、義理の娘などに会って取材
専業主婦をしていた期間は夫の任地である横浜、土浦に同行し、6年間が経ってからは京都に落ち着きました。夫の実家が弁護士事務所だったので、私もそこで仕事をしながら、夫は東京や名古屋などを単身赴任でまわりつつ、週末だけ帰ってくる生活になりました。
本の取材では、ご本人たちのお身内にも会いました。嘉子さんの場合は、実弟の輝彦さんや息子の芳武さん、再婚相手となった三淵乾太郎さんの長女・那珂さんなどにお話をお聞きしましたが、この3人はもう亡くなっているので、あのとき貴重なお話をうかがっておいて本当に良かったと思います。
取材については皆さん好意的で、私が嘉子さんの後進に当たる女性法律家ということで、信用していろんな資料を提供してくれました。
ちなみに、女性初の検事は門上千恵子さんで、女性の検事第2号が私の義母だった佐賀小里です。佐賀小里は戦時中に明治大学法学部で学び、ドラマの穂高先生(小林薫)のモデルとなった穂積重遠先生の授業も受けたということで、佐賀小里も取材源のひとつになっています。『三淵嘉子・中田正子・久米愛 日本初の女性法律家たち』に書いたように、当時、講師だった嘉子さんが夫を亡くしたころ、泣きすぎて紫色になった顔で講義を行ったのを目撃しています。
「泣きすぎて顔が紫色に」朝ドラのモデル三淵嘉子は戦争で夫を亡くした…終戦前後に出した「4つの葬式」
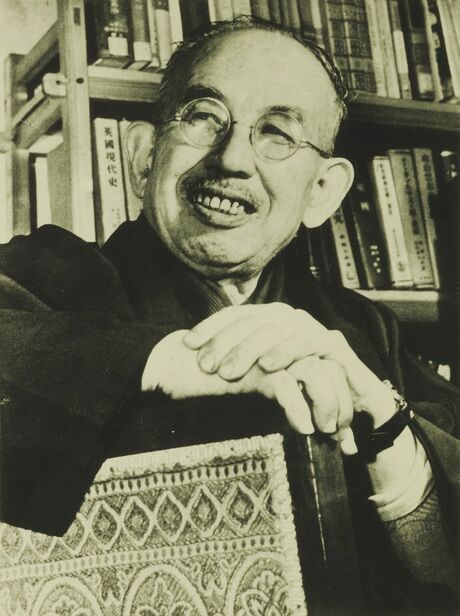
「虎に翼」の時代と現代は地続き、ドラマに勇気づけられる
私が本のために取材を始めたのは39年前ですから、三淵嘉子さんが朝ドラになるなんて予測もしていませんでしたよ。本当にありがたい話ですし、あのとき頑張って本を書いておいて良かったと思います。
「虎に翼」はドラマとしてすごく面白いですよね。かなり脚色されているところもありますが、嘉子さんの考え方など基本的な部分は、私の本も参考にして主人公に落とし込んでくださっているように感じますし、展開も面白い。俳優さんたちもそれぞれに魅力的です。
女性法律家が朝ドラになったことで、その影響を受けて法学部や司法試験を志す女性も増えるかもしれませんね。ドラマを観ていても感じますが、憲法や民法が変わっても、それで人の心や社会構造までが簡単に変わるわけではなく、人によっては今も戦前の考え方をまだまだ引きずっているところがあります。「女性が弁護士や裁判官になるなんて難しい」と目標にしていなかった人たちを、ドラマが勇気づけてくれるといいなと思います。
もちろん、嘉子さんの時代に比べると、今は女性の立場もだいぶ改善されました。とはいえ、そうではなかった時代に平等を目指し、法律家になろうと頑張ってきた人たちがどんなことを考え、どんな困難に直面していたのかは残しておく必要はあると思うんですね。その頃と今は地続きなわけですから。
そんな思いで私が本を書いたときのことが、毎朝、「虎に翼」を観ると思い出されて、感慨深いです。
実は「女性裁判官第1号」は三淵嘉子ではなかった
ドラマの寅子と同様、嘉子さんも戦後すぐには裁判官になれず、まず、家庭裁判所の準備に携わっていきました。そして、ドラマでは寅子が女性初の裁判官になっていますが、実際には女性裁判官1号は石渡満子さん。戦後の司法科試験にパスした人で、嘉子さんはそこから4カ月遅れて裁判官になったんですね。嘉子さんは裁判官になる前に、最高裁の民事局や家庭局に居た時期があったためです。
ドラマでは寅子が判事補となり、家庭裁判所で忙しく働きますが、嘉子さんが判事補として最初に配置されたのは、東京地方裁判所の民事部でした。
そこで出会ったのが、裁判長・近藤完爾さんでした。彼は嘉子さんが裁判官として配置されたとき、「あなたが女であるからといって特別扱いはしませんよ」と言った人だったこと、「私の裁判官生活を通じて最も尊敬した裁判官であった」ことを著書『女性法律家』(有斐閣)の中で記しています。嘉子さんの『「職場における女性に対しては女であることに甘えるなといいたいし、また男性に対しては職場において女性を甘えさせてくれるなといいたい」という考え方は、近藤さんの影響が大きかったのでしょう。

「女性裁判官は家庭裁判所」というジェンダーバイアスに反発
嘉子さんはみずから「お決まりのルート」を恐れ、自分の次の異動先には家庭裁判所を希望しませんでした。そのきっかけは、「日本婦人法律家協会」が発足した頃、最高裁判所長官を囲んで行われた座談会でした。当時は2代目長官の田中耕太郎さんで、そこに嘉子さんも招かれたのですが、こんな言葉に耳を疑ってしまいます。
「女性の裁判官は、女性本来の特性から見て、家庭裁判所の裁判官がふさわしい」
そこで嘉子さんは「家庭裁判所裁判官の適性があるかどうかは個人の特性によるもので、男女の別に決められるものではありません」と即座に反論したそうです。ドラマでも寅子は、女性ということで男性と違う扱いはしてほしくないと思っていますが、まさにそうした「はて?」ですよね。
嘉子さんは家庭裁判所の立ち上げにも加わりましたし、アメリカの家庭裁判所を現地で視察もしていますから、田中長官はそんな嘉子さんの能力や経験を買って、家庭裁判所の専門家に育てようと考えたのかもしれません。しかし、嘉子さんは女性法曹のトップランナーとして、女性法曹の道が家庭裁判所に限られ、狭められていくことを恐れたのです。
女性裁判官のトップランナーだった嘉子さんは、人柄も明るく、人気者だったようです。彼女の存在が後に続く女性の法曹たちを励まし、男性と遜色なく仕事ができること、頑張れば認めてもらえるという希望を与えたところはあると思います。しかも、女性で最初に家庭裁判所の所長になった人ですから、後に続く道を切り拓いた功績は大きいと思います。
そもそも三淵嘉子は本当に裁判官向きの人だったのか
ちなみに、ドラマでは戦前に判事の桂場(松山ケンイチ)が寅子を「裁判官に向いているのかもしれない」と思ったようでしたが、その時点では女性は裁判官になれませんでした。あのとき、桂場は、寅子が権力や圧力に負けない強さと公平さを持っていると見たのだと思います。
「どういう人が裁判官に向いているか」というのは難しい問題です。ただ、一つ言えるのは、裁判官は記録をたくさん読まなければならず、公平でもなければいけないということ。医療過誤の裁判もあれば交通事故も賃貸借も離婚もあるし、刑事事件を担当することもあって、その都度、その分野のことを理解しなくてはならず、勉強しなきゃいけないんですね。つまり、勤勉でなければ向かない。その点、ドラマの寅子はたしかに向いています。
実は、嘉子さんの人となりを調べていくと、そこまで裁判官向きという印象はないんです。頭脳明晰な方ですし、実績を残していますが……。息子さんの和田芳武さんはこうも言っていました。
(『三淵嘉子・中田正子・久米愛 日本初の女性法律家たち』日本評論社)

学究肌ではなかったが人が好きで、非行少年のことも信じた
法律家の中にはたくさん文献を読み、専門書を書くような勉強家がいるものです。嘉子さんが再婚した三淵乾太郞さんはそういう学究肌のタイプ。それに比べると、嘉子さんはそこまで特別に勉強好きというほうではないけれども、仕事はガンガンしたらしいですよ。家庭裁判所では、累計5000人もの少年少女と実際に向き合ったわけですから。
学究肌というより現場主義だし、人間好きだったと聞きます。どんな少年少女でも、話をすると、どこか良いところは必ずあるし、「きっと良い方向に行ってくれる」と信じていたそうです。
実際には何度も非行を繰り返す人も残念ながらいるけれど、「いつかは良い方向に行く」と信じて接するというのが信念なんですね。人間に対して、性善説的な見方をする、人間に対する期待や愛情が根底にある方でした。
嘉子さんは、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が望んだ女性解放の影響を受けた「日本婦人法律家協会」の設立(1950年)にも関わっていました。最初は少人数から始まりましたが、だんだん広がってきて、弁護士や裁判官、一部研究所や法学部の先生なども所属する団体になっています(現在の名称は「日本女性法律家協会」)。
私と司法修習生の同期だった女性は、嘉子さんの最後のキャリアとなる横浜家庭裁判所で所長としての嘉子さんを見ていますが、そのときは職員に対し「みんなどう思う?」と意見をいろいろ聞いて、すごく気を遣っていたそうです。しかし、心を許している身内や仲間の前では素で、わがままなところも見せられたんでしょうね。そんな偉大な先駆者としての業績とのギャップや人間らしさに多くの人が惹かれたのだと思います。

