
「日本史上最良のとき」を生きた芸術家
巨星墜つ。坂本龍一が亡くなった。
坂本の死をめぐって、いますでに、その偉大な歩みを総括するたくさんの記事が公開されたあとだろう。私も、それらの著者と同様に、坂本の逝去を心から悼むひとりである。
この記事は、ふたつの意味で、後追いである。多くの記事は、坂本が生きた同時代を並走し関係を持った然るべき人々が書いている。そんな中、編集部が私にくれた依頼はこうだった。私や、さらに下の若い世代にとって、坂本龍一とはなんだったか。すなわち、坂本龍一に「後追い」世代が言えることはなにか。そう、私は坂本龍一の最良のときをリアルタイムでは知らない「後追い世代」なのだ。
「その最良のときを知らない」。その思いが、長年坂本の活動を追ってきた自分の感情と距離意識を、複雑なものにしている。そしてそれは、あなたが日本という国家に抱く感情と、少し似ていたりはしないだろうか。
坂本龍一は1952年に生まれた。少し上の団塊世代が「闘争の68年」を大学生として戦っていたとき、都立新宿高校に通う高校生として同じ時代を経験する。70年代には東京藝術大学音楽学部作曲科で学び、同大学院で修士課程を修了。並行してプロミュージシャンとしての活動を開始。79年、日本発で真に「世界的成功を収めた」と形容しうる唯一のユニット、Yellow Magic Orchestraとしてデビュー。そして日本全体が好景気(バブル景気)に躍ったという、あの80年代の到来である。
後にも先にもない「アジア人のアカデミー作曲賞受賞」
83年には、大島渚監督作『戦場のメリークリスマス』で主演と音楽を担当。同映画のテーマこそは、私見では坂本作品の頂点に位置する名作だ。そこでできたプロデューサーとの関係性を延長するかたちでベルナルド・ベルトルッチ監督の『ラストエンペラー』の音楽と出演を担当。同作の音楽によって、88年、デヴィッド・バーンと蘇聡(スー・ツォン)とともに、アカデミー作曲賞を受賞。アジア人による同賞の受賞は史上初めて。坂本、若干36歳。翌年12月末、日経平均株価は現時点での史上最高値を記録する。
坂本のアカデミー作曲賞受賞は、いまの目線で見ると、いや当時の目線で見ても、明らかに例外的である。それ以前の受賞者にアジア人はいない。彼らの受賞がいかにスキャンダラスでリベラルだったことか。それ以後のアジア人の同音楽賞の受賞は、12年後の2000年、中国の譚盾(タン・ドゥン)が最直近であり、以後現在に至るまでの22年間には存在しない。

時代に翻弄された坂本龍一、愛新覚羅溥儀、甘粕正彦
1980年代当時、世界にあった緊張感を、後追い世代は直接には知りえない。1945年の敗戦後、アメリカは、日本が共産主義化し東陣営にとられてしまうことを、あるいは東西ドイツのように分裂してしまうことを恐れていた。その緊張と分裂可能性はひとたびやりすごせばなくなってしまうようなものではなくて、潜在的脅威は90年代まで続いた。「冷戦対立」とはそのようなものであったと、教科書やそれ以外で習った。
だから端的に、アメリカや西洋諸国は、いまより日本に甘かった。というのもおそらく、日本は第三世界(冷戦時代の用語。アジア、アフリカなど東西構造の外にいる世界中のたくさんの発展途上国家)に向けての、モデルショーケースだったから。「西側=資本主義側につくならば、未来は明るいのですよ」。当時の日本は、憧れられていた。しかしそれは日本を憧れられるように仕向ける、それによって利をなす外力に大きく下駄を履かされてのことだったのだろう。
『ラストエンペラー』は、ひとりの人間でありながらにして、世界の対立に翻弄され数奇な人生を送った人物、愛新覚羅溥儀を描いたフィクション映画である。中国清朝の最後の皇帝は、大日本帝国に手を差し伸べられ、満洲国の元首として迎え入れられる。「大日本帝国側につくならば、未来は明るいのですよ」。訪日した溥儀を日本は大いに歓迎する。その後、溥儀は用済みとなる。映画中では、そのことを告げにやって来るのが、坂本龍一演ずる甘粕正彦だった。
戻ろう。20世紀後半の日本は、苛烈かつ静的な――まさに冷戦的な――政治的バランスのもと、経済的文化的豊かさと平和を偶然に享受できた時代だった。坂本は1952年生まれ。今後「日本史上最良のとき」と振り返られるかもしれない20世紀後半という半世紀に、人生の大部分を生きた芸術家。それが坂本龍一である。
90年代小室ブームの中に降り立った「嫉妬する壮年」
坂本龍一と小説家の村上龍のふたりがホストとなり、各回ひとりのゲストを迎え対話する鼎談集『EV. Café』(初版は1985年)という書籍がある。同書にも登場した批評家の蓮實重彦は、(乱暴な要約だが)時代とともに「ありすぎる」ことを、「凡庸」と形容した。
坂本は時代とともにあったか? それは明確にイエスであると言わざるをえないだろう。その時代の美性と愚かさを最大限に身にまとうことが凡庸であるなら、坂本は凡庸だった。『EV. Café』は、80年代当時「ファッション」と言えるほどに人気を博したニューアカデミズム、ポストモダン現代思想の日本における主要人物たちと交歓する坂本の高揚を、スナップ写真のように活写する名ドキュメントである。時代はそれに憧れていて、坂本もそれに憧れていた。
凡庸。そうであればこそ、坂本は、自分以上に時代とともにある人に敏感だった。
私が最初に動く坂本龍一を見たのは、「avex dance Matrix ’95」という大規模ライブイベントの映像においてだった。同イベントは、90年代のJポップをすべて塗り替えてしまうほど一世を風靡した「小室系=TKファミリー」の歌手、ユニットが大集結し行われたもので、その後の大規模音楽フェスティバルの前身だったとも言われるようだ。主役はもちろん、小室哲哉。
坂本に憧れた小室は演奏そっちのけで走った
坂本の訃報に際し、「あなたに憧れてきました」という直筆メッセージを発表した小室は、95年のこのとき、坂本を唯一のTKファミリー外からの特別ゲストとして招いていた。小室が共演を求めた坂本の楽曲は、マイケル・ジャクソンが自らのレパートリーにしたがったことでも知られる、YMO時代の代表曲のひとつ「BEHIND THE MASK」だった。
「怖い顔をしたおじさま」。あまりに素朴だが、そのステージの映像を見た最初の印象はそのようなもので、もっと言えば、坂本はいらついて見えた。いま思い出しても当時の自分の印象は間違ってなかったように思える。「BEHIND THE MASK」冒頭から繰り返される有名な4小節のリフは、2小節目からさっそく同主調転調するという稀な構成になっている(だからこそクセになる)。このリフの繰り返しをバックに、アドリブでソロを弾くことがいかに厄介か、いまはわかる。
では小室が、ソロの番が回ってきたときにどうしたかというと、演奏そっちのけで、客席中央まで延びる長い長い花道を全力で走っていったのだ(こちらには当時、「こんな勝手な大人がいるとは!」と驚いた)。歓声が上がる。坂本は定位置を動かず演奏していた。このときの小室を見る目が、怖かったのだ。
「時代とともにある」ということは「凡庸」だという宿命
嫉妬だ。90年代、時代とともにありすぎるほどあった小室哲哉は、つまり当時もっとも凡庸だった。だからその嫉妬は正当な評価と表裏一体であって、まさしくその点によって、いま思えば、美しかった。94年、坂本が「大人のポップスを聴かせる」と言って発表したソロアルバムのタイトルは『Sweet Revenge』(甘い復讐)という。これが小室ひとりに宛てられたものだなどと言うつもりはない。だが、(坂本の耳からすれば)子ども向けのポップスが数字をとっていく同時代への、真剣な応答であったことは確実だろう。だから私の当初の坂本の認識は、同時代に対して嫉妬し、復讐しようとする壮年だった。若者世代に対して、と言ってもいいかもしれない。
だが――むしろ、だからこそと言うべきかもしれない。坂本の姿勢に興味を惹かれ、その音楽をゆっくりと紐解いていくことになる。その昔、YMOという比類なきユニットで世界的成功を収めたこと、日本人で唯一のアカデミー作曲賞受賞作家であること。90年代当時、「転調の小室」と言われていたが、大胆な転調といえば坂本がずっと先んじていたこと(有名曲で挙げるなら「TONG POO」、『ラストエンペラー』のテーマ。『子猫物語』のテーマ「ワタスゲの原」は、クラシックの書法からほど遠い大胆な転調を楽しめる名曲である)。
そして、自分はこの作家の最盛期には間に合わなかったのだと思い知った。
平成の日本は疲弊し坂本による強壮剤のCM曲がヒット
20世紀が終わろうとする99年、凡庸という衣はふたたび坂本へと舞い戻ってくる。「energy flow」が、ピアノ曲のシングルとしては異例の大ヒットを記録したのだ。
「癒やしの時代」に合った曲だと言われた。癒やしという言葉の語感には、たしか坂本本人が違和感を表明していたと記憶する。ただそれ以上にシニカルで、かつ象徴的だったのは、この曲が強壮剤のCMテーマだったことだ。強壮剤を名前の通りに理解する人はビジネスパーソンには少ないだろう。それは、本当は疲れていることを隠蔽し先送りにする、時間の前借りとも言われるなにかだ。いまは多くの人が知っている。平成日本はとっくに疲弊していた。その事実に気づくことを、日本は単に先送りにしていた。
忌野清志郎とキスした坂本のジェンダー表現は?
のちの時代の目線で、高みの見物のように過去を客観視する語りは、必ずしも正当とは言えない。たとえば坂本は、82年に忌野清志郎とのコラボ曲「い・け・な・いルージュマジック」を発表しているが、ビリー・アイリッシュのパフォーマンスが「非当事者によるLGBTQイメージの商業的搾取」と非難される現代の目線で見るなら、同曲のクィアネス(非規範的な性のサイン)はあまりに牧歌的で危うい。けれども、いまよりずっとジェンダー意識が保守的だった時代に、男性が耽美な化粧をし、MVの中やテレビ出演時にふたりがキスをしてみせることは、当時にあっては進歩的で、そのパフォーマンスに救われた人もいたはずだ。
かつてバイセクシュアルを公言していながら、その後セクシュアリティがよりシリアスな社会的イシューになっていくことを受けて、世にも稀な「実はヘテロセクシュアルでした」という逆カミングアウトをしたデヴィッド・ボウイ(坂本と並び『戦場のメリークリスマス』の主演格である)などと比するなら、「ちゃっかり感」は相対的に低いと評することもできる。80年代におけるクィアネスへの牧歌的な接近、という「凡庸さ」をどれだけ論難すべきかは、難しい。
ある作家のどの時点が最盛期である、と語ることには根本的な危うさがある。また、本稿は「坂本龍一は晩年に至るまでつねに進化しつづけていたのだ」という理解を否定するものではないし、それと矛盾するものではない。
坂本が最も反時代的で非凡だったのは21世紀に入ってから
筆者は坂本にインタヴューしたことがあるのだが、その折に、本人に対して近いことを伝えている。要約するとこうだ。「坂本さんはつねに前進を試みていて、すなわち更新主義的である。モダニスティック(近代主義的)だ。マイルス・デイヴィスはジャズの進化に、アストル・ピアソラはタンゴの進化に、個人の生きる時間が幸福に並走していたと思うが、坂本さんもそのような音楽家ではないか」。この理解には一定の同意を示してくださったと記憶している。
ここで言う進化には「老い」が含まれることを、坂本がいなくなったいま、改めて感じる。「若いこと」「老いながらも若くあろうとすること」「老いること」。坂本はその3つのステージを十全に生きた。そのことを通して、この社会に不足しているものを教えてくれていたようにも思う。なぜなら、現代日本は加齢の仕方を、すなわち老い方を忘れてしまった社会だからだ。であるなら、坂本は21世紀に入ってからがもっとも、反時代的で、非凡であったと言える。「自分をまだ若者だと思っている中年が増えている」という言い方がなされるようになって、もうずいぶん経つ。
正しく「老いる」ことができる幸福とその特権
しかし「正しく老いる」ことこそは、特権ではないか。上昇と、これは最良のときだ、と確信できるピークを経験しない者に、だが老いていけというのは酷ではないか。そんな声も聴こえてきそうだし、「後追い世代」を自認することから始めた本稿は、その声をむげに否定することはできない。
本稿執筆のために、「後追い世代」のさらに「後追い世代」、すなわちいまの大学生たちにヒアリングをしてみた。どの人からも名前が挙がるのが、やはりあの名曲、『戦場のメリークリスマス』のテーマだった。それだけの代表曲を持っているから、「最良のとき」を持っているから、一方では『風姿花伝』が描いた成熟さながらに、進化し老いていく余裕があったのではないか。老いることができることと、最盛期を持っていることとは、むしろ表裏一体で同義なのではないか。
坂本が我々に残した問いはあまりに大きくて、訃報からまだ日が経たないいま、冷静にそれを吟味することなど到底無理だ。けれども、私にはひとつ、かつて坂本本人からもらったヒントがある。それを、ここまで読んでくださったあなたと共有したい。
坂本に「背中を押してもらった」かつての若者世代として
「後追い世代」からの距離感だとか、日本最良の時代の追い風を得た年長者への嫉妬だとか、それらを蓮實重彦のアクロバティックな「凡庸」の用法を借りて表現してみせたが、通常の用法で形容するなら、坂本龍一はどこまでも非凡で、不世出の作家なのだ。そして私は、坂本の音楽が本当に好きなのだ。
若いころはもっと直截に憧れていた。駆け出し社会人のころ、経験を積んだら、坂本に関わる仕事をするんだと心に決めていた。すると、その機会は拍子抜けするほどにすぐに訪れた。完全に偶然のチャンスによって、坂本さんに関する出版物の手伝いをできることになった。最大の夢のひとつを早々に実現して、私はより新しい世代の音楽を探し、ボーカロイドシーンに飛び込んでいくことになる。
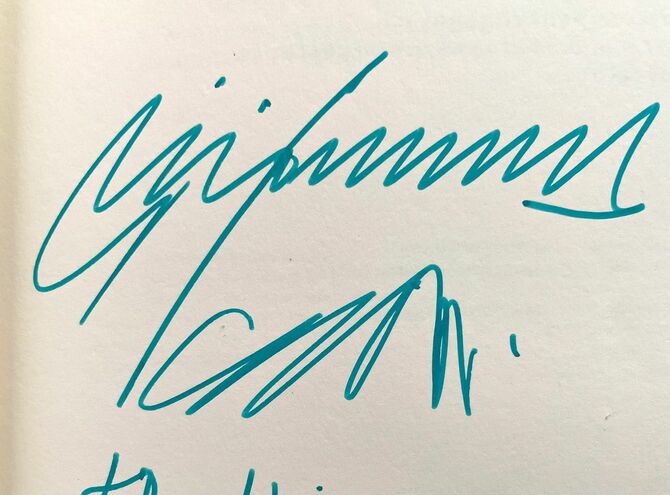
坂本は死ぬまで「若者世代に対抗する壮年」ではなかった
限られた機会の中で私が接した時点の坂本は、自分の時間を生きていた。そうであればこそ、どこか鷹揚で寛容だった。「若者世代に対抗する壮年」ではありえなかった。背中を押されたように感じた。いま思えば、次のようなメッセージを勝手に受け取っていたということなのだと思う。
あなたは決して「後追い世代」ではない。あなたがあなたの時代を生きるかぎり。あなたはあなたの後追い世代ではないのだから。
私たちは、私たちの時代をそのまま生きるだけで、坂本たちが成したことにごく自然に触れることができる。80年代、坂本龍一がメインに使っていたヤマハのDX7というシンセサイザーがある。初音ミクのビジュアルイメージには、坂本にかぎらず世界中の音楽家に愛用された(楽器の世界でも、かつて日本は強かったのだ)、そのDX7のデザインがオマージュされている。電子音楽の大衆化、すなわち大衆音楽へのシンセサイザーの導入は世界的な潮流だったが、日本におけるそのあり方のトーンセッティングをしたのはやはりYMOである。
前線のボカロPにとっての坂本は「音に対して誠実だった」
21世紀日本の音楽を代表すると言えるほどに、若者を中心に人気を博しているボーカロイド音楽カルチャー。その牽引者であるボカロP(初音ミクなどボーカル・シンセサイザーを用いて音楽活動をする作家)たちとも話をしたが、彼/彼女らの多くは「後追い」という気負いなしに、坂本の音楽に触れていた。
10年以上にわたってこのシーンの一線を走りつづけるボカロP、sasakure.UKは、自身も多彩な電子サウンドを操る先進的な作家だが、坂本に一番影響を受けたのは、具体的なサウンドの意匠など以上に、「ソウル」だと言った。「坂本さんは、09年の作品『out of noise』で、北極圏で出会った氷の音を自分の音楽に取り入れていました。何十年間にもわたって、坂本さんは新しい音への探究心を持ちつづけていた。音に対して、ずっと、真剣で誠実だったのだと思います。その姿勢に敬意を感じます」。
「音楽の根源的な役割は、鎮魂なのではないか」
最後に。私からあなたに薦めたい坂本龍一の1曲は、やはり『戦場のメリークリスマス』メインテーマである。坂本の、東京藝術大学で学んだクラシカルなハーモニーを自在に操る点を評する人は多いが(坂本の遠い後輩に当たる藝大作曲科の現役学生は、ドビュッシーやラヴェルなどフランス印象派由来の、四度堆積和音の多用を指摘していた)、私にとってはまず第一に、坂本はメロディストだった。アンサンブル全体を牽引する特権的な単旋律。その特別さを思い知り、そして実現できていることは、藝大作曲科出身者としてはむしろ珍しいとさえ言いうるかもしれない。
戦メリの「レミレラレ」よりも記憶されるメロディを書いた作曲家を誰が挙げられようか。だからこそこの曲は、世代を、階層を、国境を超え、時間的にも空間的にも広く聴かれつづける。これからも。
坂本の活動については、ほぼすべての時代における記録が残っている。戦メリの録音も、公開されているだけでもたくさんのバージョンがある。1986年発表『メディア・バーン・ライブ』収録版の、テンポの速さ、打鍵の強さ、若さ。2022年12月11日に公開された、「最後のコンサートになるかもしれない」という覚悟のもとに弾かれた演奏の、厳粛さと潔さ。
願わくばあなたにも、この1曲が作家のおよそ40年にわたる進化=老いを担ってきたさまを、複数の演奏から聴き取ってほしい。拙著『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』の終盤で引用した坂本の発言をいま、坂本龍一に送り返したいと思う。
「音楽の根源的な役割は、鎮魂なのではないか」
芸術は長く、人生は短い。だから、坂本の音楽は、長い。
坂本龍一さん、本当にありがとうございました。
