
仏で新設された、近親姦犯罪の法律
2019年3月、日本各地で性暴力事件の無罪判決が相次いだ。このうち2件は、実父による娘の性的虐待・性的暴行、つまり近親姦だったが、一審では、「抵抗困難だったとは認められない」「娘の証言に信ぴょう性がない」などの理由で無罪判決が下された(その後、2件とも逆転有罪になった)。
相次ぐ性暴力事件の無罪判決をきっかけに、全国でフラワーデモが広がり、刑法の性犯罪に関する条項を見直すべきとの議論が活発化。現在も法務省で改正についての検討が行われている。
私が暮らすフランスでも、近年の#MeToo運動の高まりから、被害者の視点から刑法の性犯罪を見直すことが求められ、今年4月21日に「未成年者を性的犯罪と近親姦から擁護するための新法」が成立した。
ちなみに、「近親相姦」という言葉があるが、「相」が入ると「互いに納得の上での行為」という印象を与えてしまう。このため最近は、「近親姦」という言葉が一般的になっているので、ここでもこの言葉を使いたい。
「18歳未満」と限定していいのか
フランスでできた新法は、「近親者と18歳未満の未成年者の間でのあらゆる性的挿入行為は、未成年者側の同意の有無にかかわらず近親姦レイプと判断され、禁固刑20年」〔性的虐待の場合は禁固刑10年と15万ユーロ(2000万円相当)の罰金〕と定めている。ここで言う「近親者」とは、親や親せきなどのうち、被害者に対して監護権がある(生活をともにし、面倒を見たり教育をしたりする権利や義務を持つ)人々を指す。
日本でも2017年の刑法改正で「監護者性交等罪」と「監護者わいせつ罪」が新設され、18歳未満の子どもに対して監護者がその影響力に乗じて性交・わいせつ行為をした場合は、暴行や脅迫の有無に関係なく罪に問われることになっている。
これまで近親姦を取り締まる法がなかったフランスで、この新法が制定されたことは、確かに大きな進歩だった。しかし、条文に納得がいかないと言う人々は多い。
例えば、「18歳未満の未成年」だけを対象とすることについて、2000年に「国際近親姦被害者団体」を創立したイザベル・オブリー氏は、「18歳以上であっても、学業を続けるために加害者から経済的援助を受けざるをえないなど、(性行為を強要されたときにそれを拒否する)不同意の表明をしにくい立場にある人もいるのです。年齢にかかわらず、すべての近親姦を犯罪と認めてもらいたかった」と、失望を隠さない。

国民の10%が被害者
フランスでは1985年ごろから数人の被害者が、著作やテレビ出演などで近親姦を証言し、注目されることはあったが、これまでは「特殊な家庭での例」としてしか捉えられてこなかった。
しかし2020年11月、市場調査コンサルティング会社Ipsosが、被害者団体の要請で18歳以上の国民を対象に調査を行い、10%にあたる約670万人が、未成年の時に近親者からレイプ、あるいは性的虐待の被害に遭っていたことが明らかになった。被害者の78%が女性、22%が男性だった。また、別の統計になるが、国立非行刑罰監査局が2020年12月に発表した調査結果によると、被害者の53%が4歳未満で、22%は5歳から9歳の間に被害に遭っている。
さらに、近親姦が社会問題として捉えられるきっかけとなったのが、今年2021年1月のデュアメル事件だ。
高名な憲法学者の加害が明るみに
憲法学者として名高く、テレビやラジオで解説者としても国民に親しまれていたオリヴィエ・デュアメル氏が、義理の息子(本の中では「ヴィクトール」と呼ばれる妻の連れ子)を、13歳頃から数年にわたってレイプしていたことを、被害者の双子の姉であるカミーユ・クシュネール(Camille Kouchner)氏が1月に出版した著作『ラ・ファミリア・グランデ』(La Familia Grande)の中で明らかにしたのだ。さらに法曹界の要人数人は「事実を知りながら告発しなかった」と批判され、次々に要職を辞した。

著者と被害者の実父が元大臣だったこともあり、この本は大きな反響を呼び、初版7万部が数日で売り切れ、1カ月で20万部を売り上げた。
今年4月14日にデュアメル氏は、警察で近親姦の事実を認めた。憲法学者、元欧州議会社会党議員、国立政治科学基金会長、さらに、法曹界の重鎮で、法の公布前に合憲性を審査する機関である憲法評議会の次期会長と噂されていた同氏が近親姦の加害者であったことに、国民は驚愕した。
そしてこの事件をきっかけに、政治家、俳優、労働組合のリーダーなど有名人数人が立て続けに近親姦で訴えられた。
これまで近親姦は、「家族全員が同じ部屋で寝るような住宅環境で起きる、貧困層に特有な犯罪」と考えられることが多かったが、実は、経済状況も教育程度も関係なく、あらゆる社会階層で起こり得る犯罪であることが明らかになった。
近親姦はほかの性暴力とどう異なるのか
先のデュアメル事件を含む3つのケースを例に、被害者団体が新法審議にあたって考慮すべきと主張していた近親姦の特徴や、日仏の法律が抱える課題について説明したい。
「あの子の方から誘ったんだ」:デュアメル事件
『ラ・ファミリア・グランデ』によれば、デュアメル氏は、妻が両親2人を自殺で亡くしたショックでアルコール依存症になった頃から、子どもたちの面倒をみるようになっていた。その一方で、著者の弟である義理の息子(当時13歳)をレイプし始めたという。
弟は双子の姉である著者に、近親姦の被害に遭ったことを打ち明ける。
「義父さんは、『ママンはとっても疲れているから、今はこのことは言わないで2人だけの秘密にしておこう』って言うんだ。おじいちゃんもおばあちゃんも自殺してつらい時だから、そっとしておこうって。だからお姉ちゃんも誰にも言わないでね」と。
「夫は悪くない」息子を責める母親
姉弟はこの秘密を抱え、やがておとなになるが、事件の20年後、それぞれ家庭を築き子どもができて初めて、母親に秘密を明かす。
若かりし日はキューバ革命の指導者フィデル・カストロ氏の恋人で、フェミニストの左派の論客として有名だった彼女だったが、「ヴィクトール(息子)は暴力で強制されたわけじゃない。だから夫は何も悪いことなんてしなかったのよ。だいたいあの子の方が私の夫を寝取ったりして、私を騙したんだ」と言って息子に責任転嫁する。
近親姦の加害者は家庭内、地域、社会で重要な人物であることが多い。そのため、子どもが被害を打ち明けても、家族から友人や知り合いまで、団結して子どもの声を抹殺しにかかる。
日本でも、「被害者(娘)の証言に信ぴょう性がない」として父が無罪となった例がある。子どもは周囲から、時には司法からも「嘘つき」扱いされる中で、「あなたが誘ったんでしょ」という言葉を真に受けて自分を責め、孤立する。
マクロン大統領の要請で2021年1月に発足した「子どもに対する性犯罪と近親姦に関する独立審議会」の会長を務めるボビニー市裁判所判事のエドワール・デュラン氏は「まず、子どもの言葉を信じるべきです。子どもが偽証する数よりも、犯罪が裁かれず、なかったことになる数の方がずっと多いのです」と言う。
思い出すまで30年かかった:ブラジリエ事件
フランスの芸術大賞であるローマ賞を受けた著名な建築家、ジャン・マリー・ブラジリエ氏(1926-2005)の娘、マチルド(Mathilde Brasilier)さんは、2019年に出した著書『朝、夜そして近親姦』(Le Jour, la nuit, l’inceste)の中で、実父による近親姦を明らかにした。
マチルドさんは、「文化的に優れた環境で幸せな子ども時代を送っていた」と信じていたが、40歳の時、精神分析を始めたことがきっかけで突然、5歳から10歳になるまで、1歳年下の弟と一緒に父親からレイプされていたことを思い出した。季節や来ていた服、弟の泣き声まで「映画のように」鮮明によみがえったという。
建築家だった父親はアトリエに、防音工事が施され内側から鍵がかかる地下室を作り、そこで2人を5年間にわたってレイプしていた。親を信用しきっている幼い子どもに対する近親姦には、レイプ罪成立の要件である強制も、威嚇も、不意打ちも必要ない。
夫の幼児性愛、それも実子に対する性愛の傾向を知りながら問題を直視できなかった母親は、後にマチルドさんにこう明かす。
「あなたが2歳の頃だった。あの人がベッドの中であなたを抱いているのを見た。『いったいなんていうことをしているの!』と叫ぶと、あの人は『いや、ごめんごめん!』と軽く言い、照れ臭そうにしていた。私は、精液で濡れたあなたの服を洗ってあげたの。『でも大丈夫よ、心配しなくていいのよ。誰にも知られなかったから』と……」
1960年代、近親姦を訴えることなど想像もできない時代だった。何よりも大切なのは「誰にも知られない」ことであって、子どもが受けたダメージではなかった。弟は24歳で自殺した。
過酷な体験から記憶喪失に
精神科医で「トラウマ記憶と被害者研究」団体の創立者であり、自らも6歳から10歳にかけてレイプ被害を受けていたミュリエル・サロモナ氏は語る。
「電線に定格以上の大電流が流れるとヒューズが飛ぶように、性犯罪の被害者は、あまりの恐怖に解離性記憶喪失を引き起こすことがあります。そのため、警察で事件について話そうにも、明確に覚えておらず証言できないことがあり、それが裁判で被害者を不利な状況に追い込んでいます」
近親姦の場合は、幼い頃から長期間にわたって加害者と同居せざるを得ないことも多い。レイプや虐待を受けても、翌朝は何ごともなかったかのように一緒に朝食を取るといった、過酷な生活の中で生き続けるために、マチルドさんのように、記憶喪失が30年も続くこともあるという。
マチルドさんの弟は、自殺前日、食卓で父親に、「なんでお前はいつも黙っているんだ?」と聞かれ、「僕たちにあんなことをしたくせに、よくそんなことが聞けるな!」と言い返したそうだ。マチルドさんは、「今思えば、『あんなこと』と言ったということは、彼は覚えていたのでしょう。鮮明なレイプの記憶を抱えて24年間生きていたのだと思う。私以上に苦しんだはずです」と言う。
「国際近親姦被害者団体」によると、近親姦の被害者の寿命は通常より20年短いという。
時効を設けるべきなのか
長期にわたる記憶喪失がなくても、近親姦の場合は、訴えるまでに時間がかかる被害者も多い。被害者と加害者が非常に近しい関係にあるため、家族や周囲への影響の大きさを懸念して悩むためだ。
新法の制定にあたって、被害者団体からは、公訴の時効廃止を望む声が多く上がっていたが、第三者が加害者の場合と同じく、レイプの場合は成年に達してから30年、性的虐待の場合は20年の時効が設けられた。
日本の場合は強制性交等罪(いわゆるレイプ)で10年、強制わいせつ罪で7年の時効が設けられており、フランスよりさらに短い。
誰もが見て見ぬふりをした:グアルド事件
2000年代にはグアルド一家事件が社会に衝撃を与えた。パリ近郊のセーヌ・エ・マルヌ県で、グアルド家の父親が、1971年から28年間にわたり、前妻の連れ子であるリディアさんをレイプし、6人の子どもを生ませていたのに、「家庭のプライバシーには立ち入れない」として地域社会全体が見て見ぬふりをしていた事件だ。
義父はトラックで巡回して注文をとる印刷工。血の気の多い乱暴者で、近所の人とも折り合いが悪かった。その反面、仕事はまじめで、しつけに厳しく「良い父親」とも思われていた。
村では、この一家の近親姦について知らない人はいなかった。リディアさんは妊娠中、病院で医師に「誰が赤ちゃんのパパ?」と聞かれると、「私の父です」と正直に答えていた。しかし誰も、眉一つ動かさなかったという。子どもたちはリディアさんの義父を「パパ」と呼び、親子関係は皆の知るところだった。
村を追われた被害者
1999年に義父が亡くなると、リディアさんは、同居していた母親を「未成年者に対する性犯罪を告発しなかった罪」で告訴。これが全国紙上で取り上げられると、村人は、リディアさんを追い出しにかかった。警察に通報してメディアに語り、村に不名誉をもたらしたからだ。「あばずれ」と呼ばれ、『村はずれで売春もしている』という噂が流され、リディアさんは村を離れることを余儀なくされた。
この事件に関する研究を、2008年の著書『平凡な近親姦』(Un incest ordinaire)にまとめた社会学者のレオノール・ル・ケンヌ(Léonore Le Caisne)氏は語る。
「(年長の男性が権威を持つ)家父長制社会では、金を多く稼いでくる者、つまり多くの場合で男が権力を持ち、家の中は彼が好きなようにふるまえる解放区と化してしまうことがあります。圧倒的に優位な立場にある彼が、一番立場が弱い者、つまり子どもを捕らえて性的に支配する近親姦が起きてしまう」。ちなみに、国立非行刑罰監査局が2020年12月に発表した調査によると、フランスでは近親姦の加害者の95%が男性だ。
「僕のパパは刑務所に行かなきゃいけなくなるの?」
フランスでは来年度から、小学校と中学校で計2回、医師の聞き取りによる近親姦予防診察が義務付けられると発表された。被害者団体やフェミニスト団体は、学校で最低1年に1回、子どもたちに近親姦も含めた性犯罪全般に対する教育を行うよう求めている。
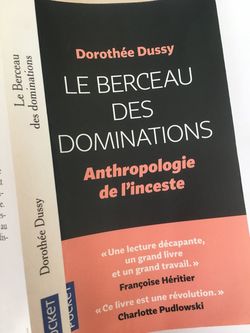
元ラグビー選手で、子どもの時にコーチから性犯罪被害を受けていたセバスチャン・ブエ氏が2013年に設立した団体「 Colosse aux pied d’argile」は、スポーツクラブや学校に出向いて、子どもへの性犯罪について特別授業をしている。静かに話を聞いていた子どもが、授業の後、「じゃあ、僕のパパは刑務所に行かなきゃいけなくなるの?」と聞きに来たり、「秘密なんだけど、○○ちゃんの家ではこんなことが起きてるんだよ」と友達の被害を伝える子どももいるという。
『支配の始まる場所、近親姦の人類学』(Le berceau des dominations)の著者、ドロテ・デュシ(Dorothée Dussy)氏は「欧米では、10歳の子ども30人のクラスのうち、平均1人から2人は近親姦の被害者がいる」と言っている。
日本の警察庁の発表では、2020年に親や親せきなど監護者を子どもへの性的虐待で摘発した事件は、前年に比べ21.5%増加し299件だったというが、おそらくこれは「氷山の一角」だろう。近親姦は性犯罪の中で一番「話しにくい」もの、実際の件数はこれをはるかに上回るのではないだろうか。
