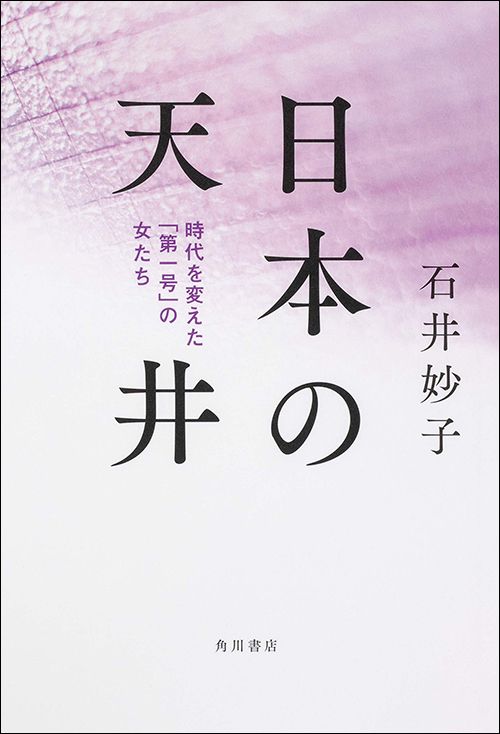※本稿は『日本の天井 時代を変えた「第一号」の女たち』(角川書店)の一部を再編集したものです。

「経済は女にはわからない」という偏見
学界、官界よりも、なお、いっそう女性に厳しく門戸を閉ざしたのが日本の実業界だった。
経済は女にはわからないという社会通念が蔓延しており、その上、日本の会社組織は軍隊に模された徹底した男社会であって、女性たちの参入を拒否してきたからだ。
軍隊に女はいらない――。上司の命令は絶対でタテの上下関係が何よりも重んじられる。そんな日本型企業は男だけの戦場であり聖域であって、女は就職しても結婚までの腰かけの状態と見なされ、同等の戦力としては受け入れてもらえなかった。
男女雇用機会均等法ができる前まで、女性を正社員として男性と平等に雇う会社は、ほとんど皆無。入社させても極めて限定された補助的な仕事を短期間のみ任せ、定年までは働かせない。そうした日本社会で役員にまで上りつめたのが高島屋百貨店に入社して常務取締役になった、石原一子である。
高島屋において、もちろん初の女性役員であったが、日本の歴史においても創業者の血縁でなく一部上場企業に女性役員が誕生した、初めてのケースだった。
彼女の役員就任は画期的なニュースとして、マスコミに大きく報じられた。昭和五十四(一九七九)年のことである。
その後、石原は女性として初めて経済同友会にも迎えられる。
働く女性への偏見が強かった時代に、石原は、ひとりで岩盤を砕き続け、その存在は働く女性たちにとって天に輝く星であった。
理不尽な妨害にも屈せず「働き続ける」
周囲の偏見をものともせず、「働き続ける」ことを選んだ石原の、パワフルな行動力の源泉、それは彼女の前半生に起因する。
満洲に生まれ、日本で教育を受け、敗戦を経験し、民主主義の到来を喜んだ。様々なことを青春時代に彼女は経験し、独自の人生観、仕事観を抱くのである。
高島屋で販売員から常務取締役となったが、その過程では男性社会の中を生きる、たったひとりの女性として理不尽な妨害にも遭った。
だが、そうした苦境に屈することなく、退社後も彼女は自分が実社会で培った経験と能力を今度は、一市民としての生活のなかで余すところなく生かしもした。自分が暮らす国立市で起こったマンション建設をめぐる反対運動では、多くの人が尻込みをするなかで代表を引き受け、矢面に立って闘ったのだ。「企業社会から市民社会に身を移して、改めて日本企業の、日本企業に働く人間の問題点にも気づいた」と本人は語る。
国立市の自宅を訪ねてのインタビュー時、石原は九十代になろうとしていたが、赤いセーターに同色の口紅がよく似合い、何を聞いても歯切れのいい言葉が返ってきた。キャリアウーマンとして売り場をハイヒールで闊歩していたという、往時の姿が偲ばれた。
一世紀に近い歳月を生き、今の日本社会に何を思うのか。起伏に富んだ人生の軌跡とともに、現代の社会への疑問、違和感までを縦横に語ってもらった。
誰よりも成果を出していたのに昇進が遅れた理由
昭和四十二(一九六七)年、石原はベビー商品を統括する次長になり、昭和四十五(一九七〇)年には部長になった。もちろん高島屋において、女性初の部長である。同期十二人の中でも最も早い出世だった。「会社が公平に実力を見た結果」と石原は受け止めた。入社した時から、一生懸命働いてきた、男に仕事で劣ると思ったことはなかったと振り返る。仕事はポジションが上に行くほど権限が増え、責任も増す。その分、面白くもなる。商品開発や仕入れもできるようになる。だからこそ、石原は出世したかったという。
「次長になるのは、同期の中で一番遅かったの。私は女性差別だと思った。だって私は誰よりも商品を売っていたし、それは数字で証明されていたから。そこで専務のところに乗り込んで、『私を昇進させないのは私が女性だからなのか、それとも私の能力不足なのか』と単刀直入に尋ねた。すると、専務に『君は二回の出産を経験し、それぞれ三カ月ずつ産休を取った。同期より少し後れをとるのは当たり前じゃないか』と諭されたの。確かに、と思った(笑)。
だから、以後は、女性差別だと騒ぐのをやめて、今まで以上に頑張ったし、子どもを産んだ強みを会社に還元したいと考えて実行もした。結果、部長になるのは同期で一番早かったのね。会社は公平だな、と思いました」
「部下の昇進は自分のこと以上に考えた」
管理職になり、部下の指導にいっそう励んだ。様々に工夫した。子どもを持ったことのない販売員が説得力のある商品説明をするためには育児体験が必要だと考えて、石原は愛育病院に一カ月に一度、研修生として部下を派遣することにした。病院で子どものおむつを替えたり、風呂に入れる実習を積ませてもらったのだ。
朝礼では売り上げ目標を数値で言うようなことはせず、自分が感動した本や映画の話をした。とりわけ八割を超える女性販売員に向けて、「女性にこそチャンスがある職場だ」というメッセージを送り続けた。「女に管理職は無理だ」と公然と言われることもあったが、石原は気にしなかった。
「私は部下の昇進は自分のこと以上に考えた。この人は将来、百貨店を背負っていく人だと思ったら、きちんと評価した。私と一緒に仕事していると厳しいけれど勉強になるし、頑張れば評価もされる、そう思われる上司でありたかった。百貨店の社員に必要なのは、センスと決断力。それなのに、男性社員だけにそういうことを求めて、女性社員には少しも求めない。それで男だけを出世させていくわけ。そんなシステムは、もう終わりにしたかった」
私はあなたが思っているほどバカじゃない
結婚をして、出産をして、なおかつ出世街道を歩む女、石原を快く思わない勢力も社内にはあった。だが、気にしても仕方がない。石原はただ、いいと思ったことを単純に貫いていった。自己主張をし、自分の居場所を自分で切り拓いた。
「夫が九州の朝日新聞西部本社に代表として赴任することになった。それを知った社長から『君も九州の高島屋に異動させてあげようか』と言われたことがあったけれど、私は即座に断った。夫の異動のために自分も赴任地に異動するという考えは私の中に、まったくなかったから。
大陸で育ったこともあり、男尊女卑的な日本の価値観を知らなかったからね。社会に出てからは驚くことばかり。あんまり女だというだけでバカにする相手には、こう言ってあげた。『そう、あなたの周りには利口な女性がいなかったのね』。このひと言に相手がびっくりしているところへ、『私はあなたが思ってるほどバカじゃありません』と重ねて反論するの」
昭和五十(一九七五)年には東京支店次長、昭和五十二(一九七七)年には理事(役員待遇)になった。石原の立場が上がるにつれ、やっかみの声は大きくなった。
「女の出世に対して、あれこれ言われたとしても、全部無視すればいい。気にしたってしょうがないし、第一、敵はこちらを落ち込ませようとしているわけだから、落ち込んだら負けでしょ。女は組織には向かないだとか、管理職には向かないだとか、男たちは言いたがる。言わせておけばいい。本当は単にライバルが増えるのが嫌なだけ。女性は自分の下にいて、競争相手にはならない存在であって欲しいというのが彼らの本音よ。
女の人がなぜ出世できないかって? それはできないようなシステムになっていたからよ。女の能力とは無関係よ」
女性の覚悟も必要
その一方で、男性たちから低く見られてもしかたのない一面が女性たちの側にもある、と歯がゆくも感じていたと語る。
「女も仕事をきちんとして、評価をされるように訴えないと。男の人に嫌われたらどうしようとか、そんなことを考えて遠慮しているようではダメですよ。それから仕事に対して、きちんとした覚悟を持っていないといけない。だいたい大学卒の優秀な女性が入ってきても、みんなよく辞めていく。仕事に対するイメージが薄いし、家庭との両立をどうしようという気持ちもない。初めから結婚したら辞めようと思って働いている。それでは会社も戦力とは考えられない。
女も仕事を結婚までのつなぎと考えたり、結婚相手を求めて物欲しそうにしていたり。そんなことでは幼稚すぎる」
1969(昭和44)年、神奈川県生まれ。白百合女子大学卒、同大学大学院修士課程修了。2006年に『おそめ 伝説の銀座マダム』(洋泉社、09年新潮文庫)を刊行。綿密な取材に基づき、一世を風靡した銀座マダムの生涯を浮き彫りにした同書は高い評価を受け、新潮ドキュメント賞、講談社ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞の最終候補作となった。16年、『原節子の真実』(新潮社、19年新潮文庫)で第15回新潮ドキュメント賞を受賞。19年、「小池百合子『虚飾の履歴書』」(「文藝春秋」2018年7月号)で第25回編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞作品賞を受賞。著書に『日本の血脈』(文春文庫)、『満映とわたし』(岸富美子との共著・文藝春秋)などがある。