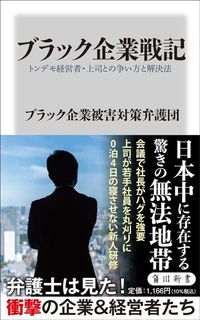同じパワハラ被害者の元同僚に証言をお願いした
2点目は、元同僚Bさんの協力である。Aさんの職場には、上司S、Aさん、派遣社員Bさんがいた。Bさんも上司Sからパワハラを受け、Aさんよりも先に退職していた。AさんがBさんに協力を求めたところ、Bさんは快く応じてくれた。Bさんは、労基署の事情聴取に応じ、裁判でも証人として出廷、Aさんがどのようなパワハラを受けていたのか、自分が目撃したことを話してくれた。これは在職中、AさんがBさんに人間的な対応をしていたからこそ。日ごろの生き方は大切である。
3点目は、上司S自身、事実関係をあまり否定しなかったことである。裁判で上司Sは、「そのような発言はあったが、それは、自分の後継者として期待していたAさんへの愛情を込めての厳しい指導だった」と、「パワハラではなく指導だった」という評価の問題として争ってきた。
記憶力に自信のない人はメモをする癖を
では、裁判で最も重要なのはどれだったのか。私は、①のAさんの記憶の復元だったと考えている。上司Sが事実関係を概おおむね認めたのは、Aさんが詳細な事実を積み上げた結果でもある。非常に詳しい事実を提示したことで、それを全部「Aさんの妄想」と切って捨てることはできなくなったのだろう、と私は思っている。
当然、パワハラ裁判では、上司が事実関係を否定してくる場合もある。協力してくれる同僚がいない場合もある。そんな場合でも、被害を受けた労働者本人のしっかりとした記憶によって、「確かにそのような事実があった」と裁判官に印象付けられるか否かが、非常に重要となるのである。
しかし、人間の記憶はすぐに薄れる。私も、たとえば今年風邪をひいたのが何月だったか、すぐには思い出せない。記憶力に自信のない方は簡単で良いので、その都度、手帳に書き込む、LINEに書く(LINEは自分だけのグループも作れて、それは日付入りの自分専用メモになる)、といった癖をつけてもらいたい。これだけでも随分違うものである。
どんなに絶望的な状況になっても、自分は仕事をしたんだという誇り、労働者としての誇りを失わずに、しっかりと生き残って、過去を冷静に見つめ直すこと。そうすれば必ず、正義はあなたに味方するはずだ。