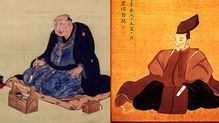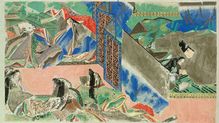朝起きると、虎の皮の上でタバコを吸ってから……
煙草を吸い終わると、政宗は「閑所」という小部屋に行く。そこには棚の上に硯・料紙・簡板・香炉、刀掛が置かれていた。そこで何をしたかは『政宗記』に書かれていないが、場合によっては何か書き物をしたのかもしれない。香を焚いてリラックスした時を過ごしたとも考えられる。閑所で過ごした後は、お風呂に入るのだが、その前に、朝食の献立表を見て、食べたくないものがあれば指示を出して修正させている。
そしていよいよ「行水」(桶やたらい等にお湯や水をそそぎ、それを浴びて体を洗う)である。まず、腰の大小刀を刀掛けに置く。そして、広蓋の上には行水の後に着る小袖や帯、印籠、巾着、鼻紙をそろえさせた。行水の仕方や、浴衣で濡れた身体を小姓に拭わせる方法も決まっていた。朝晩二度の行水、旅行中であろうと、嵐や寒い冬であろうと、その手順は決まっていたようだ。
ここまでが「寝食、休憩の場所」である「奥」での日課である。行水が終わると、政宗は「表」(公務の場所)に出て行く。表の寝間に入り、それまで着ていた小袖を着替える。そして、居間に行き、髪を結ってもらう。髪を止める緒が緩んだら、何度もやり直させたという。髪のセットが終わると、表座敷に出て行き、「相伴衆」と呼ばれる側近達を呼ぶ。小姓に呼びにいかせるのだ。側近たちと朝食をとるのである。側近たちに膳が行き渡ったことを見ると、政宗は膝を直し、箸を取り、お椀に手をかける。それと同時に側近も箸をとるのであった。食後にお酒を飲む時は、政宗はうがいをしてから、飲んだという。

体を洗うと髪をセットし朝食、家臣と続けてのトイレタイム
しかし、食事中に、親類の者が一人でもいれば、うがいはしなかったと言われる。政宗なりのエチケット・礼儀があったのだろう。政宗は大酒飲みではなく、酒はほとんど飲まなかったようだ。食事中は、家臣たちが政宗を楽しませるため、芸を披露したという。今風に言うと、宴会の一発芸のようなものか。それが済むと、頃合いを見計らって、政宗がお湯を所望する。茶菓子の用意をさせている間に、政宗はトイレに立つ。すると、家臣たちも次々にトイレに向かう。トイレタイムが終わると、茶を点て、薄茶や菓子を飲食する。茶の時間が終わると側近は席を立ち、朝食は終了となる。
その後は、役人たちが入れ替わり立ち替わりやって来て、政治向きの話をする。政務の時間である。午後2時頃までが政務の時間であった。その間に、昼食の記述はないので、政宗は昼ご飯は食べなかったようだ。政務が終わると、夕食の献立を見て、食べたくないものを修正させた。これは朝食前と同じである。政宗公は、好き嫌いが激しかったのであろうか。