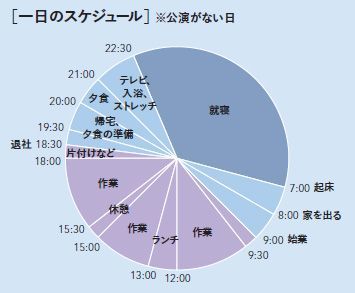JR大阪駅直結の商業施設、グランフロント大阪北館。その4階にナレッジシアターという劇場がある。その日、午前中のホールでは、15時に開演する「うめだ文楽」の準備が大詰めを迎えていた。演目は「義経千本桜(よしつねせんぼんざくら) 河連法眼館(かわつらほうげんやかた)の段」。場内に入ると、大道具のスタッフが10人ほど、忙しく動き回っている。
「そこは団子(結び)や!」
「散り花、用意しといて!」
舞台監督の指示に従って作業を進める男性たちは、おもに伝統芸能の舞台製作を手がける関西舞台の社員である。その中に、ショートカットの小柄な女性、森本加奈子さんがいた。

脚立を軽々と上っていく彼女の頭上に見えるのは「雪かご」と呼ばれる仕掛けだ。端についた紐を引くと、紙吹雪や花びらが舞台上に降り注ぐ。
「『うめだ文楽』は初心者向けの公演なので、雪や花を降らせる特別な演出になっています」
雪かごに手早く散り花を仕込み、脚立から下りてくると、森本さんはそう説明してくれた。勤続17年目の中堅だが、「私、かなり鈍くさいんですよ」と笑う。
「昔はしょっちゅう金づちで指を叩(たた)いて、血豆をつくってました」
「定式」を覚える楽しさに目覚めて
10代の頃はミュージカルの役者を目指していた。10歳からバレエを習い、高校は演劇科に通った。たとえ役者になれなくても、「どのような形であれ、舞台に関わって生きていきたい」と考えていたという。

大学に進んでも就職は考えず、地元・兵庫県にあるピッコロ舞台技術学校に入り、フリーターをしながら芝居やダンスの裏方仕事をこなしていた。だが、自分に合っていないのではという思いが徐々に強くなっていく。
「お芝居やダンスは、舞台監督によって、仕事のやり方が違うんです。前回はよくても、今回はダメと言われてしまう。怒られるのも怖いし、なかなか自信が持てずにいました」
そんなとき、講師の紹介で国立文楽劇場で大道具の仕事を手伝うことになった。欠員補充のアルバイトだったが、この経験が伝統芸能に惹(ひ)かれるきっかけとなる。
「定式(じょうしき)といって、古典芸能では演目ごとに使う道具が決まっていて、舞台転換の動きも毎回同じなんです。最初は、道具の名前もわからず苦労しましたが、一度覚えてしまえば、次は自分から動ける。『これやったらできる』ということが増えて、どんどん楽しくなって。定式1つ覚えるたびに、その演目の全体像や仕組み、どうすれば舞台をスムーズに転換できるかが見えてくる。そこに、この仕事の醍醐味(だいごみ)を感じます」
「覚える楽しさ」に目覚め、関西舞台に入社を志願した。26歳のときだ。
ベテランの先輩からも、刺激をうけた。彼らはあまり上演されない演目の定式道具まで覚えており、倉庫のどこにどんな道具があるかも完璧に頭に入っている。
「定年後も現場でバリバリ働いている70代の方がいますが、演出の内容にも詳しくて、『あそこで役者が飛び降りるから、ここには段が必要だ』と、迷いなく準備を進めていく。すごい方です」
上演中に大道具が担う重要な役割に、「きっかけ」というものがある。舞台袖で待機して、障子を開けたり、仕掛けを動かすのだ。それを合図に演者が登場したり、浄瑠璃が始まったりする。だから、演者と息が合っていなければならない。
「演者さん一人一人にこだわりがあって、演技に合わせてゆっくり障子を開けたつもりが、『タメすぎや』と注意されることもあります。稽古中には合図を出すけど、本番では出さない人もいるので、自分で浄瑠璃を覚えなくてはならないことも……。大変ですが、今はそれも楽しめるようになりました」
年に2度ほど、地方巡業に出ることもある。巡業では大道具の人数も少なくなるため、普段は「女の子だから」と男性が引き受けてくれる重い作業もこなす。
「クタクタになりますが、家に帰ってきて、ビールを飲む瞬間は本当に幸せです(笑)」
社団法人をつくって女性演者の出番を増やす
入社当初、女性の大道具は森本さんを含め2人しかいなかったが、今は4人に増えている。
「私は『やりたい』という気持ちだけで、がむしゃらに走り続けてきました。女だからと考えてしまうと、前に進めなくなるので、後輩たちにも、年齢や性別にとらわれず、思いきり仕事に取り組んでほしいです」
そんな彼女は今年1月、同じ古典芸能の世界で働く同世代の女性3人と、「関西伝統芸能女流振興会」という社団法人を発起した。邦楽や日本舞踊などに携わる女性や若者の活動を支援するのが目的で、今年の12月には国立文楽劇場の小ホールで公演を行う予定だ。
「古典芸能の裏方を続けてきて感じるのは、女性の裏方が増えている一方で、女性の演者の数がどんどん減っていることです。その理由の1つは、発表の場が少ないこと。それなら発表の場をつくっていけばいい。私たちのような女性の裏方が中心になって、演者の女性を盛り立てていきたいです」