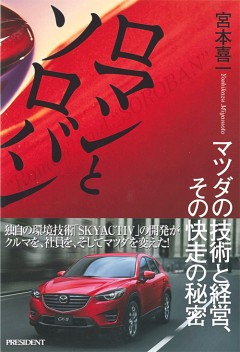ニューヨーク国際自動車ショーにおいて、3月24日、マツダの「MX-5」(日本名:ロードスター)が「2016年世界カー・オブ・ザ・イヤー(WCOTY)」とデザイン部門の「世界カーデザイン・オブ・ザ・イヤー(WCDOTY)」を同時受賞という史上初の快挙を成し遂げた。さらにそのおよそ1カ月後の4月22日には生産累計100万台を達成した。なぜマツダ「ロードスター」はこのように世界で愛されるのか、ロードスターの開発現場を徹底取材した。
「世界2冠同時受賞! なぜマツダ『ロードスター』は世界で愛されるのか」の後編。
オープンカーだからこそ人馬一体感を演出できる
四半世紀以上の歴史を経て、ロードスターは幸いなことに、初代の主査平井敏彦、そしてそれを引き継いだ貴島孝雄、そして現在の山本修弘をはじめとしてマツダのエンジニアが一貫して掲げていた開発・製品化のテーマ“人馬一体”が、市場に完全に定着した。動力性能、運転感覚の面では“人馬一体”がロードスターならではの“味”にまで成長してきた。そして今、開発エンジニアは開発中のスカイアクティブ技術を盛り込んで、その“味”をさらに進化発展させようとしている。
これによって、走りの面では、これまでの人馬一体感がさらに発展熟成することは容易に予想できた。そこで、中山はじめデザイナーの集団は、この“味”に加えて、“見た目”でも、つまりデザイン面でも“人馬一体”が明確に表現できる姿の完成を目ざすことになる。“見た目の人馬一体感”“走りを予感させる一体感”は、一般的な乗用車の場合にはすでに述べたようにキャビンの中に人が隠れてしまうため、なかなか表現するのが難しい。オープンカーの場合はこれとは違う。人の姿がむき出しであるからこそ、その人馬一体感を姿形で演出できるのだ。むしろそうすべきであって、これができれば「マツダのクルマづくりの考え方を表現する」という命題にこたえられるはずだ。

まず、スポーツカーとしては、4つの車輪が大地をしっかりと掴んでいる、そしてその車輪が車体の四隅ぎりぎりのところに配置され、クルマが低い姿勢で力強く路面を蹴って走るという印象を与えることが肝心だ。そのために、車輪は可能な限り車体の四隅に追いやり、さらに車輪を覆う前後のフェンダーをこれも可能な限りそぎ落として、クルマが路面に貼りついているというイメージを生み出すデザインを創出した。そのため前後フェンダーは、異常とも思えるほど立体的な造形になったため、当初アルミで成型するのは困難だと考えられていた。
生産サイドからは、アルミではなく、なんとか成型が可能な鉄を使ってくれという要求が来た。生産サイドに言わせれば、鉄でも成型ははむずかしい。したがって彼らはアルミではなく鉄の使用を決断するよう求めた。しかし、開発エンジニアが掲げている性能の要件<車両重量は1トン以下にする>から、アルミ以外の選択肢はなかった。アルミの成型を可能にするためには、元の立体的な造形が“甘い”方に修正されてしまい、格好が悪くなる。自分たちもデザイナーが提案したデザインが気に入っている、ところが、そのデザインが修正されて格好が悪くなるのは、デザイナーではなく、生産サイドの技術的な問題だと思われたくないエンジニアは、試行錯誤を繰り返す。その結果ついに元の造形のフェンダーをアルミでつくれる成型技術を確立してしまった。
こんなエピソードがある。昨年秋の某モーターショーのマツダブースには、あるときドイツの某メーカーのデザイナーが、展示してあるロードスターのフェンダーに磁石をあてている姿があった。鉄でも難しい造形をアルミでもこなしてしまったことに驚いている様子だったという。言うまでもなく、ロードスターは特別高い値札のついたクルマではない。マツダの掲げる、「顧客が買い求めやすい価格」の製品だ。にもかかわらず、コストの高いアルミを前後のフェンダーに採用していることに、その成型技術とともに彼らは驚いたのではないか。