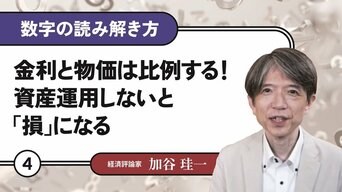1985年、東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程在籍。慶應義塾大学SFC研究所訪問研究員(上席)。有限会社ゼント執行役。専攻は社会学。著書に『希望難民ご一行様 ピースボートと「承認の共同体」幻想』『絶望の国の幸福な若者たち』、共著に『頼れない国でどう生きようか』などがある。
〈いま・ここ〉にある社会は、私たちが思うほどには自明のものではない。だからこそ、その「常識に見えるもの」を相対化すること――社会学の役割とはそのようなものだと古市憲寿さんは語る。
「少しずらして世の中を眺めると、社会が秘めている可能性、ありえたかもしれない別の形が見えてくる。僕らを取り巻く〈いま〉が決して変わらないものではないことがわかるんです」
本書で古市さんが描いたのは若手起業家たちの仕事観だ。登場するのは自身も働く会社「ゼント」の社長・松島隆太郎氏、ファッションショー「東京ガールズコレクション」を主催する村上範義氏、俳優であり映画監督の小橋賢児氏の3人。一見すると特別な彼らの生き方には、働くことへの新しい価値観が象徴的に表れているという。
「彼らに共通するのは、信頼できる仲間との繋がりをセキュリティベースにしながら、複数の業界を跨いで活躍していること。そして会社を大きくしようとせず、『居心地の良さ』を追求していることです。起業家というと多くの人がイメージするホリエモンのような起業家とは全く異なるんです」
日頃から「会社」の枠を飛び越え、身近な仲間との人間関係を重視する。将来よりも〈いま〉が幸福であることを追求する。彼らのそんな働き方は、今後の若い世代が「普通」だと感じるようになる価値観を体現している、と古市さんは続ける。
「企業に入って組織の一員として働くのを良しとする時代も、振り返ればこの40年間くらいの『常識』でしかありません。日本では高度経済成長期以降、そのシステムが上手くいきすぎたがゆえに、それが『当たり前』のように感じられるんですね。従来の価値観が崩れ始め、年功序列・終身雇用のモデルが素朴に信じられない若者の多くが、いずれ彼らのような生き方を志向するようになっていく。いまはその過渡期なんです」

グローバル化と流動化が進む時代、大企業はこれまでのようにすべての人材を社内に抱え込めなくなった。一方で専門性を持つ少数精鋭の企業や人には、大企業と対等な立場でともに働く活躍の場が生まれる。本書が見据えるのは、これまで交わることのなかった双方が共存しながら、再編成されていく未来の社会像でもある。
「社会学は頭の中で考える理論よりも、実際の社会で起こっていることを優先する学問。『日本の働き方の過渡期はこんなふうだった』と、後から振り返ってもらえる1冊になっていればいいな、と思います」