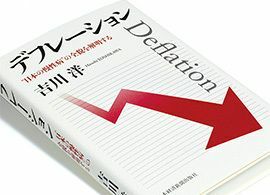日銀総裁の名前を冠した「黒田サプライズ」なる大型金融緩和の余韻も冷めやらず、株価は急騰し、円は急落、そして賃金や企業収益についても明るい話題がちらほら見えてきた今日、こんな表題の1冊を取り上げていては、時流に乗り損ねると揶揄されても文句は言えないかもしれない。
だが、仮にアベノミクスやらサプライズやらでデフレが解消に向かっているとしても、本書は十分に一読、いや二読、三読にも値する。東京大学大学院経済学研究科教授である著者は、遠くは『高度成長』、近くは『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』などの好著からも知れるように、理論的な思考力に加えて、歴史的な感受性も豊かな優れた書き手なのだ。
本書では、まず第1章で争点を明確にしたうえで、第2章ではいわゆる失われた20年について、政府の報告書や新聞記事、コラムを多数引用して、読者の記憶を(若い読者にとっては基礎知識を)補充してくれる。次の第3章では、1873年から1896年までの長期デフレ(ケインズも含む第二次大戦前の経済学者たちにとっての「大不況」はこちらだった)の分析を行っているが、こうして大昔の話が上手に紹介されるあたりは著者の面目躍如と言えよう。
第4章では、現在のデフレ退治についての主流的学説、言説の基礎をなす貨幣数量説を検討し、粉砕する。「マネーは効かない」といった、鈍器で殴りつけるような小見出しは痛快である。第5章では価格がどう決定されるかについて様々な理論を紹介するが、これは第6章で展開される議論――本書の「肝」――の前提だ。
著者は、日本の長期デフレは長期停滞の原因ではなく結果だと考えている。そして、長期停滞の根っこにあるのは日本の労働者、特に大企業の労働者の賃金の抑制と低下だという。このくだりのデータの提示は迫力がある(1997年を境に自殺者数が激増した事実をグラフで示すのは、いきすぎの気もするが)。「医療・福祉の雇用は02~10年の期間に38%増えたが、1人当たり賃金は13%も減った。不動産の雇用も9%増えたが、賃金は4%減った。(中略)みずほ総研は『雇用を増やした成長業種ほど賃金が下がる日本独特の傾向がある』と分析する」など引用記事の中身も衝撃的だ。

ここから読み取れるのは、かつて「家族的」などと形容された日本的労使関係(戦後日本の社会契約でもあった)の崩壊である。著者はそこまで激しい結論には持っていかず、日本企業が再び技術革新(シュンペーター!)を盛んに行うようになることが解決策だと主張する。筆者は再分配が日本経済の成長軌道への復帰の鍵だと思うので、この処方箋には不満が残ったが、最終章の現代経済学批判は、単なる正論を超えた「コク」さえも感じた。大満足である。遅かれ早かれ戻ってくるデフレに対する心の準備という意味でも、必読の1冊と言えよう。