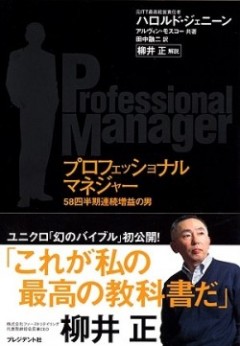クロックは思い立ったら即実行する。客がひける午後2時30分ごろになってあらためて店を訪れ、マクドナルド兄弟に自己紹介する。そして2人をディナーに誘い、根掘り葉掘り聞き出す。実にシンプルで効果的なビジネスモデルだと感動する。バーガーのメニューはハンバーガーとチーズバーガー2種類だけで、価格はハンバーガー15セント、チーズバーガー、4セント増し。その日クロックはモーテルに泊まるのだが、翌朝、起きたときにはもうマクドナルドを大きく展開する具体的なプランが出来上がっていた。
このエピソードのポイントは、そもそも新しい商売を始める計画があって視察に行ったのではなかったということだ。マクドナルド兄弟の店に行ったのは、あくまでもマルチミキサーの営業のためだった。店の評判を聞いて、マルチミキサーの商売相手としてよいのではないかと見込んでとりあえず見に行っただけなのである。そこで頼まれもしないのに観察力、取材力、企画力をばりばり発揮して、一人で勝手に大興奮している。
商売勘が抜群である。マクドナルド兄弟の店の観察で、クロックは即座にフライドポテトに注目している。フライドポテトはハンバーガーのつけあわせと考えられていた。しかし、マクドナルドの評判のカギはプライドポテトにあると、クロックは見抜いていた。すぐにピンときて、マクドナルド兄弟に「あなたがたはポテトにこだわっていますね」と水を向ける。マクドナルド兄弟にしてみれば、我が意を得たりという言葉だった。実際、2人はフライドポテトにはあふれんばかりの情熱そそぎ、アイダホ産の最高級ポテトを使って、専用の油で揚げていた。クロックは、本職でもないのに、そういう商売全体のキモの部分に直観的に目が行ってしまう人だった。
レイ・クロックは当時52歳。この日ばかりではなかったはずだ。この年に至るまでのセールスマン生活で、こんなことばかりやっていたに違いない。現場を自分で直接見て、聞いて、触って、手足を動かしながら考える。商売勘に火がつけば、即座に動いてみる。こうした徹頭徹尾ハンズオンのスタイルは一朝一夕に身につくものではない。マクドナルドの店に行くはるか以前から、この人の芸風として確立していたに違いない。
全編を通じてこうしたエピソードは枚挙にいとまがないのだが、もう一カ所だけあげておきたい。本のタイトルにもなっている話である。「競争相手のすべてを知りたければゴミ箱の中を調べればいい。知りたいものは全部転がっている」。
競争相手にスパイを送り込んで儲かるアイデアを盗めば?というアイデアに対し、そんな必要はないと烈火のごとく怒って吐いた言葉である。実際クロックは「深夜2時に競争相手のゴミ箱を漁って、前日に肉を何箱、パンをどれだけ消費したのか調べたことは一度や、二度でない」と告白している。スパイなんて送らずとも、自分の目と手で取ってくることのできる情報はいくらでもある、というわけだ。
この姿勢はマクドナルドがアメリカ全土に4000店を展開する巨大企業になってもまったく変わらなかった。ある役員が地図に売上別に色違いのピンを刺しているのを見て、自分にはそんな地図は必要がないと豪語している。「どこにどういう店があるか、フランチャイズオーナーは誰なのか、売上はどれぐらいか、問題点は何か、といったことはすべて頭の中に入っている」。
クロックは、店舗候補地を探す不動産活動をするのがとにかくスキ(もう一つの大好物は商品開発)で、いつも現地で店舗を視察し、状況を細かく把握していた。不動産開拓のために、会社のヘリコプター5台を使い、それまでの方法でどうしても見つからなかったような出店立地を探しだしたりする。
本社のコンピュータには、出店立地調査専門のプログラムが入っていたが、そんなデータはクロックには不要だった。彼はマクドナルドがいくら巨大になっても、最初にサンバーナーディーノのマクドナルド兄弟の店に行ったときと同じメンタリティで同じことをやり続けているのである。周辺を車で回り、近所の人が行くスーパーに足を運び、地元の人と言葉を交わし、あれやこれや観察する。そのうえでマックがその地域でどう成長するか、即座に頭の中でストーリーを組み立てる。
「もしコンピュータの言うことを聞いていたら、自動販売機がズラッと並ぶ店にていだたろう」とクロックは言う。「我々は決してそのような店はつくらない。マクドナルドは人間によるサービスが売り物で、オーダーを取るカウンターの店員の笑顔が我々の大切なイメージなのだ」。クロックにとっての店舗とは、人間が人間を相手にモノを売る舞台である。どんな暮らしをしているどんな人を相手にするのか、その理解なしに商売はできない。コンピュータや調査会社に教えてもらうものではなく、自分で見て、感じて、自らの手で掴む。レイ・クロックは最初から最後までハンズオンの経営者だった。