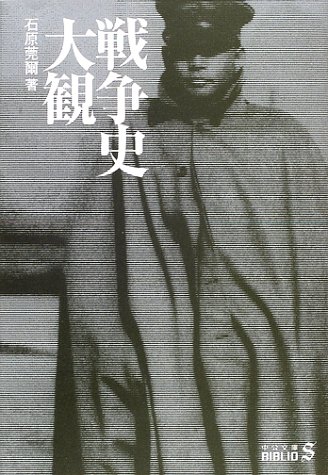『最終戦争論』は、文字通り人類の「最終戦争」に向けて日本がとるべき戦略構想を思いっきりぶち上げた本である。戦争をなくすことは全人類共通の祈念である。しかし、それができないということは歴史が繰り返し証明してきた。そうである以上、絶対平和への唯一の道は、最高の戦術と最先端の兵器で最終戦争を行い、だれが世界を統治するのか、決着をつけるしかないというのが石原の基本的な世界認識である。

石原に言わせれば、第一次世界大戦(本のなかでは「第一次欧州戦争」)は、世界大戦でもなんでもない。世界大戦はまだ先の話であり、欧州戦争はせいぜい準々決勝にしか過ぎない。その後世界はソ連、ヨーロッパ、アメリカ、東亜の代表たる日本の4強による準決勝を経て、その後にはいよいよ決戦として世界最終戦争が行われる、という筋書きである。
石原はこう考える。ヨーロッには、偉大な国が多い。しかし、地勢的に問題がある。狭いところに陸続きで有力な国がひしめいている。一時的に運命共同体を目指したところで(第一次世界大戦の後の動きを指している)、そのうち戦争を始めて共倒れになるだろう。スターリン支配下にあったソ連はどうか。共産主義は理屈としてはよくできている。ただし、人間の世の中がうまく使いこなせるものではとうていない。早晩内部崩壊するだろう。結局、準決勝を勝ち上がるのは西洋のアメリカと東洋の日本で、この二国で人類最後の決勝戦で雌雄を決することになる。この闘いは「東洋の王道と西洋の覇道のいずれが世界統一指導原理たるべきかを決定する」ものであり、それを経て日本の天皇か、アメリカの大統領、どちらかの支配の下で世の中は平和になるであろう、とこういう気宇壮大な話である。
この世界最終戦争は、「空軍による徹底した殲滅戦争」となり、「老若男女、山川草木、豚も鶏も同じようにやられる」すさまじいものになる。しかしそれを耐え、乗り越えれば「人類はもうとても戦争をやることはできない」という境地に達し、本当の平和に達することができる、と石原は言う。人間の闘争本能は決してなくならない。しかし、最終戦争を経験した後では、人間の闘争本能は、戦争ではなく経済、芸術、学問などの文明的な仕事に向けられ、その結果として世界は一つになる、というわけである。
だとしたら1940年前後の時点での日本の戦略はどうあるべきか。石原の考えはこうである。まずは、準決勝を勝ち抜き、東亜の代表選手にならなければ話にならない。そのためには東亜大同が決定的に重要になる。そのうえで、最終戦争に備えた決戦兵器の開発を急ぎ、それと並行して徹底的な防空体制を固める。なぜなら、最終戦争は「無着陸で世界をぐるぐる廻れるような飛行機」と「大都市が一撃で壊滅するような強力兵器」で戦われるものになると石原は考えていたからだ。そのためには、徹底した国家統制をきかせなければならない。国民にとっては、長くつらい生活が続くことになる。しかし、これはスポーツ選手が決勝戦の前に厳しい合宿生活をしているようなものであり、致し方のないことである。だから今はひたすら我慢をして、世界最終戦争に備えなければならない…。