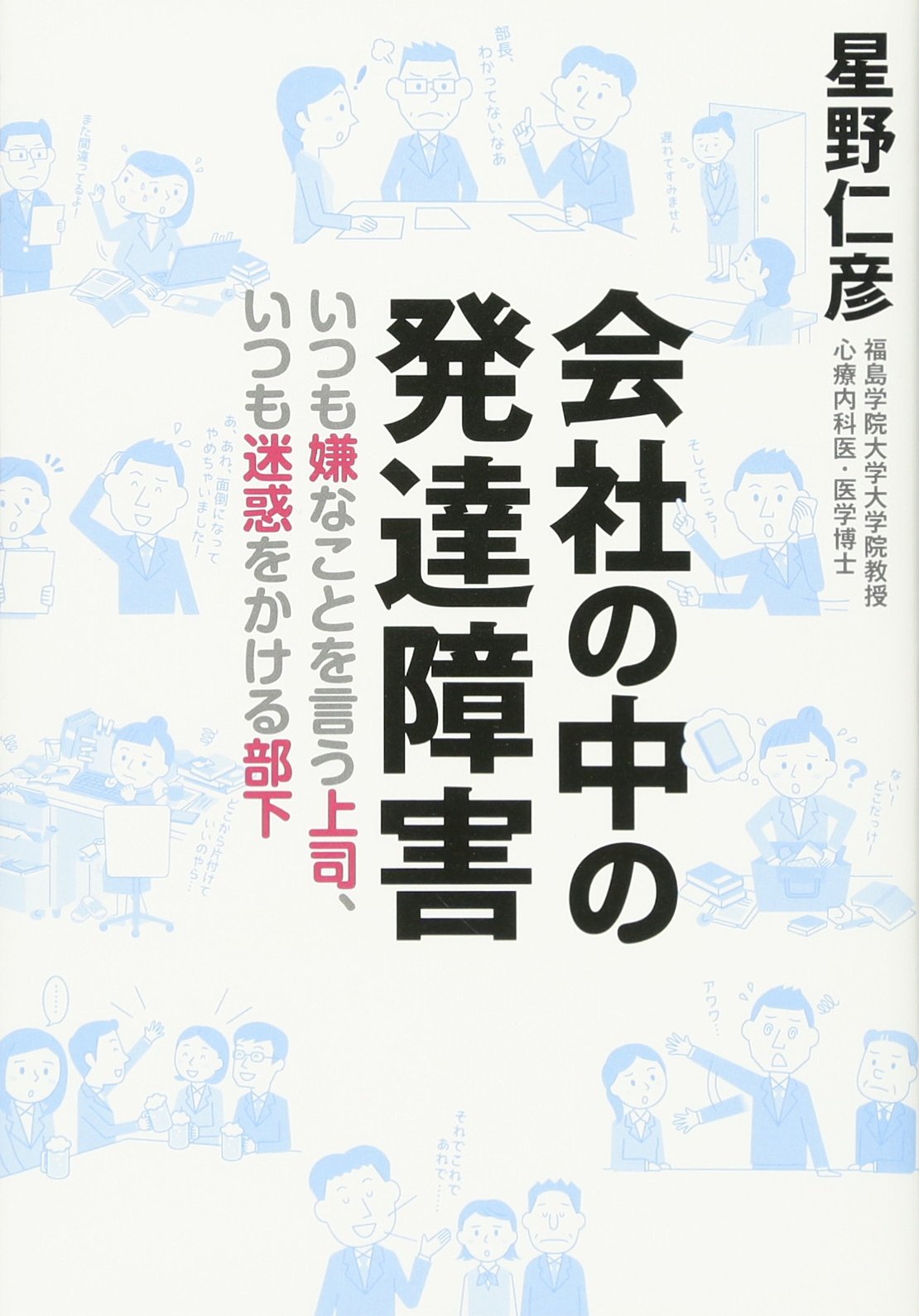小学生の私は、同年代の児童に簡単にできることがことごとくできず、始終ぼんやりと空想にふけり、話せば吃音があり、服装はいつもだらしなく、ポケットの中はがらくたでいっぱいで、口を開けばとんちんかんなことばかり言うので、学校では常に嘲笑の的であり、いじめっ子たちからは毎日のようにいじめられたり、からかわれたりしていました。そんなときどう返したらいいのかわからず、うつむいてただ黙ってやり過ごし、家に帰って悔し涙を流したこともあります。ぼんやりした性格とはいえ、やはり心は傷つき、悲しく悔しい思いをしました。
小学校の高学年になるといじめられた後にこみあげてくるものは、悲しみや悔しさより、「自分はダメな人間だ」という絶望や空しさでした。落ち込むことも多くなり、「生きていたくないな」と思うこともありました。一生懸命努力してもだらしないのです。
しかし、当時、ひとりだけでしたが、私をかばってくれる親友がいてくれたおかげで、学校に通うことができました。たったひとりでも、自分を理解してくれる友人がいることは、私にとっては大きな希望でした。その後も交友関係は狭く、決して友人の数は多くはありませんでしたが、中学、高校、大学時代にできた数人の親友にどれだけ世話になり助けられたことでしょう。彼らには当時も今も感謝の気持ちでいっぱいです。
興味のある分野を見つけた中学生時代
不器用さは一向に変わりませんでしたが、中学では得意科目と呼べる教科ができました。英語と社会です。自分が興味を持った科目の勉強をしたり、大好きな本やマンガを読むときなどは、わくわくと心が躍り、何かのスイッチがカチリと入り、頭の中が研ぎ澄まされるのが感じられました。
英語とは別にこの時期に私がこだわりを持ってのめりこんだことに、高校野球の勝利予測があります。全国の都道府県で行われる予選大会の試合を観戦し、データを分析し、優勝高校を予測するという作業は、この上なく楽しい時間でした。
得意科目ができ、打ち込める趣味もみつかった私は中学、高校と学校へ通うことがかなり楽になっていました。吃音もあまり出ないようになったことで口数も次第に増えました。
医師だった父の影響を受け、小学生のころより医者になることを目標にしていた私は、大学医学部を目指し受験しました。3校受けましたが結果はすべて不合格。しかし迷うことなく浪人することを決め「石にかじりついてでも絶対に医者になってやる!」と強く心に誓いました。カチリと例のスイッチが入った瞬間でした。