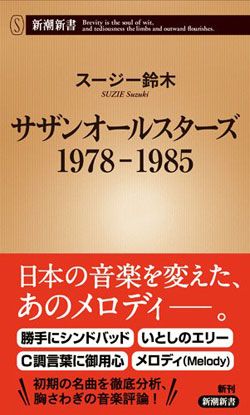今となっては信じられないが、70年代の半ばまで、「日本語はロックに乗らない」と、真面目に考えられていたのである。そんなつまらない固定観念が、≪勝手にシンドバッド≫1曲によって、ほぼ完全に抹殺された。「日本人が日本語でロックを歌う」という、今となっては至極当たり前な文化を、私たちは享受できるようになった。
「胸さわぎの腰つき」という桑田語
例えば、「早口ボーカル」「巻き舌ボーカル」と言われるほど、日本語を、口腔内を自在に操って発声することが普通になったこと。
例えば、「胸さわぎの腰つき」という、おそらくは英語に訳せないであろう、意味から自由な新しい日本語=「桑田語」が受け入れられるようになったこと。
例えば、それまで、日本のお茶の間に、決して響いたことのない16ビートや不思議なコード進行が、ブラウン管から流れ出したこと。
これらすべてが、桑田佳祐率いるサザンによる「革命」の結果なのである。
次項より、≪勝手にシンドバッド≫の凄みを、より具体的に見ていくこととする。
桑田ボーカルの源流
あの≪勝手にシンドバッド≫の衝撃を多面的に分解すれば、その最も大きな要素は、桑田佳祐の、あのボーカルスタイルではなかったか。
ここでは、その源流を探る。ただし、桑田という人は、音楽的知識・経験が非常に深い人で、ボーカルスタイルの源流も多岐にわたってしまい、やや複雑な話になることを、ご了解いただきたい。
ボーカルスタイルを「発声」(声の出し方)と「発音」(舌の使い方)に区分する。
桑田の「発声」。こちらは当時「しゃがれ声」「ダミ声」などと形容された。一般的には、リトル・フィートというアメリカのバンドのボーカル=ローウェル・ジョージや、エリック・クラプトンの影響が指摘されるのだが、幅広い音楽を聴いてきた桑田のこと、洋楽だけでなく、日本人からの影響も大きかったと思われる。
はっぴいえんどの大滝詠一。デビューアルバム『熱い胸さわぎ』に収録された≪いとしのフィート≫は、はっぴいえんど≪春よ来い≫へのオマージュだろう。ということは、≪春よ来い≫の、大滝のダミ声をしっかりと聴いていたはずだ。
ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの宇崎竜童。桑田は、デビューが決まった後に、宇崎を訪問し、事務所に入れてくれとお願いしたことがあるという。サザンのアルバム『タイニイ・バブルス』収録≪Hey! Ryudo!(ヘイ!リュード!)≫は、宇崎のことを歌ったもの。ボーカリスト、ひいては人間として、リスペクトしていたと思しい。
そして柳ジョージ。桑田よりもしゃがれたあの声。これは、ゴダイゴのミッキー吉野氏から私が直接聞いた話。当時ある歌番組で、ゴダイゴの楽屋を訪ねた桑田から、「柳ジョージさんを紹介してほしい」とお願いされたという(吉野と柳は、伝説のバンド=ザ・ゴールデン・カップスの出身)。
更には、のちに≪吉田拓郎の唄≫(アルバム『KAMAKURA』収録)を捧げることになる吉田拓郎の影響もありそうだ。